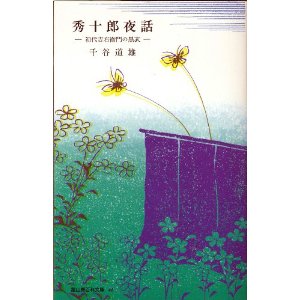歌舞伎といえばバブルの頃、『ヤマトタケル』を観てそれなりに感動したもののその後特には劇場に向かわず、伝統芸能系の映像にも触れることがなかった。ところが海外生活を経たせいか数年前に歴史に目覚め、M氏の「『国姓爺合戦』を観るように」の言葉で、文楽に通い出した私。近松節のあまりのリアルさ(後から考えるに、それは義太夫さんの技でもある)に、息が詰まるほど揺すぶられていた。
すぐ後にご縁があり、歌舞伎座建替のさよなら公演に誘われたのが2009年。正直最初は、文楽に比べて妙にバタ臭い気がして、馴染めなかった。しかし何回目かに観た『義経千本桜 大物浦』で、登場人物たちの「喪失」に引き込まれてしまった。観客も静まり返り、最後の、平知盛が錨を身体に巻き付けて海に飛び込む姿を、固唾を呑んで見詰めていた。その時私は中村吉右衛門という役者を、初めて意識した。それまでは『鬼平犯科帳』も見たことがなかったのだ。
そして片岡仁左衛門の一世一代、近松の『女殺油地獄』。大阪の身勝手なぼんぼんの犯した衝動殺人劇をニザ様は異様な迫力で演じていたが、ご本人60代後半って、有り得ない!最後には舞台中を油まみれで転がり回るのだが、どう見ても、むかーし大河で後醍醐天皇を演じていた時よりも、若いのだ。歌舞伎には人間SFXか特殊CGか、何か仕掛けがあるんじゃなかろうかと、私はしばらくの間疑っていた。それが「芸」の力だと、やがて知るようになるのだが。
その後国立劇場に出向いた日の最初の演目が、真山青果の『頼朝の死』。全く内容を知らないのに、冒頭に中村歌昇さん(その後襲名して又五郎さんになった)が花道を泣きながら進んで来た時、奇妙に私も哀しくなった。その瞬間の空気の変わり具合は、忘れらない。どうも私は、播磨屋一座の芸風がいっとう好きなようだ。特に、台詞が三味線とぴたっと張り合う時の、めくるめく恍惚!昔通ったライブのエッジ感と同じ、至福の時なのだった。
こうして私は一気に歌舞伎にハマっていくのだが、この間次々に老齢の名優が亡くなった。しかしまさか、勘三郎さんが居なくなるとは。中村屋の一門は華々しく話題の中心でい続けると思っていたし、それがどんなに歌舞伎界にとって重要なのかは、理解できるようになっていた。
歌舞伎座をめぐるドキュメンタリー『わが心の歌舞伎座』は、どっぷりのメロドラマ仕立てである。が、そこには松竹の戦略を超えて余りある、人々の並々ならぬ歌舞伎への想いが溢れている。特に、舞台裏の人々の奮闘や、三階さんと呼ばれる大部屋の役者さんたちの頑張りに、泣かされる。そして最後の、勘三郎さんと、ある劇場スタッフの何十年にもわたるエピソードで、ダムは決壊するのです。
役者さんは連日の昼夜公演と同時に、踊りや楽器の練習をこなす。そして千秋楽を終えると翌日から次の演目の通し稽古で、地方公演にも旅立っていく。そして当初その数に驚いた裏方さんも、日の当らぬ役割を黙々と果たしている。時々怖ろしいほどの「何か」が降りてくる舞台は、こうやって創られていくのだ。
こうして歌舞伎の訳のわからぬエグさが快感になり、常に脇役を務める人々にも自然に目が行くようになった頃、『秀十郎夜話』を読んだ。没落した豪商の家に生れ、初代吉右衛門に仕えるものの、黒衣や「馬の足」としてしか舞台に立てなかった人物の物語。「馬の足」を理解する観劇経験者が読むと、面白さが倍増するはずの本である。
千夜千冊288夜でも「いろいろ歌舞伎めく本を読んできたが、これを読んだときの驚きは、その後にはない。」と取り上げられているように、「禁断の園であり、影の王国」としての、歌舞伎の裏側が描かれている。本来ならば、一般に挙げる歌舞伎解説本には渡辺保氏の本などが相応しいのだろうが、その渡辺氏による「解説」が、素晴らしい。
渡辺氏が少年時代、歌舞伎に惹かれはじめ陶然となっていた頃、楽屋裏を初めて見た時の衝撃。舞台で艶やかに微笑んでいた女形が目の前を通った時の、グロテスクな化粧と、薄汚れた衣装の大股歩き。薄っぺらい張りぼての美術。この本は、そんな「かくも危険な舞台裏」を、一人の無名なる者を通して描いた、明治、大正、昭和という三幕の物語だという。商家、庶民の家、吉右衛門劇団、松竹という舞台装置での場面で、そのドラマの波紋が響き合っていくのだと。そしてそのすべてを支えているのは、主人公の秀十郎とともに著者の「無名性」である、と氏はのたまう。キャスト、スタッフ、そしておそらくは観客、その背後に数多くの無名性の上に成立するのが演劇である、と。

『半ズボンをはいた播磨屋 (PHP文庫) [文庫] 』
『秀十郎夜話』と同様に「昭和」を描いているのが、初代吉右衛門の孫であり養子となった二代目の、『半ズボンをはいた播磨屋』。黒衣とは対極にある御曹司ながら、生まれる前からの宿命を背負い、鬱々とした少年時代だったことが読み取れる。その彼を肉親以上の愛情で育てたのが、お手伝いさんの「ばあや」だった。
ばあやへの鎮魂歌として吉右衛門丈の達者な絵が添えられているのだが、この絵がなにか物哀しい。ルオーが好きというだけあって、戦後の昭和の空に少年の孤独を塗り重ねた、夕刻の踏切のような、切ない絵が続いている。そんな二代目の半生の葛藤もすべては役者の血となり肉となり、今はあたたかい家庭を得て立派な人間国宝となり、描く絵まで光に満ちるようになった。新しい歌舞伎座でも、あの緩急自在で雄大な台詞回しを、たっぷりと堪能させてくれますように。
(ウミウシ)

歌舞伎座さよなら公演 記念ドキュメンタリー作品 わが心の歌舞伎座 [DVD]
十河壯吉 (監督)
by 牛丸