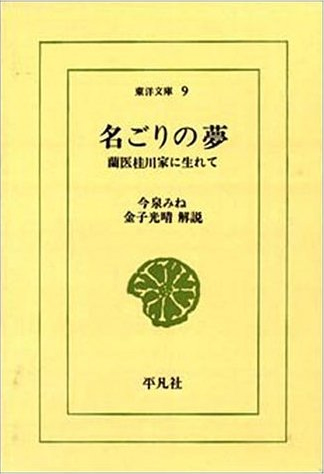どうも明治維新後の近代日本より敗れた江戸時代の文化、社会の方がとても豊かな感性が感じられるのはなぜだろう。
『名ごりの夢 蘭医桂川家に生まれて』今泉みね著 金子光晴解説 東洋文庫 を読む。
この本を40年ぐらい前に読んでいるのだ。そして、先日古本屋の店先に300円で出ていたので、また買って来て読んでみた。
本書は今泉みねの聞き書きである。今泉みねは幕府に仕えた蘭方医桂川家の幕末の7代目桂川甫周の娘である。甫周は有名な蘭日辞典「ズーフハルマ」を編纂した人物である。その父の家での子供時代の経験を孫が聞き書きしたのであるが、四部に分かれていて「維新前の洋学者たち」「桂川家の人びと」「名ごりの夢」「嵐のあと」としてまとめられている。80歳を超えた老女が語った若き日の記憶が、実に鮮明に多彩に語られている事に驚くのである。そしてそのエピソードには特別な主義主張からの偏向もなく、本当に見たままであることが歴史書を読むよりも何倍かの事実を知らせてくれるのである。
桂川家は幕府の唯一の蘭方医であった事で、桂川家はかなり当時としては自由な雰囲気で営まれていたようである。家の位は低かったが、将軍に直接接するという身分の位置は微妙であったようだ。生活は非常に質素で、食事も「桂川家のやまぶき汁」といわれるほどの味噌汁。つまり「実の一つだになきぞかなしき」の太田道灌の古事同様に実の少ない味噌汁や切干大根や煮ものがほとんどであった。先祖の何かの関連で御蔵島との縁故があり、年に一度御蔵島から島人が訪ねて来た時にシイタケが山のように届けられ、それが非常な楽しみであったという。しかし、甫周は穏やかな人格が慕われていて幕末に甫周の周辺に洋学者が出入りしていた。中には福沢諭吉もいて、みねはその背中におぶさって遊んでもらったといい、大きな背中であったと書いている。その福沢も実に貧乏で、洋書を買うのに金は皆使い果たし、肌着を代金の代わりに置いてきたという話も書かれている。「ズーフハルマ」も私は幕府の一大事業でなされたと思っていたのだが、大違いで、甫周が自力でなされたもので弟の甫策となんと妹香月が実務を担い、邸宅に二階をつくり、完成したが幕府は刊行を認めず、幕府にその必要を認めさせるために多大の努力と年月を要し、安政五年ようやく15部を番書調所に献じたがこの間の費用は265両費やしたのだそうだ。先駆者の苦労はかくなるものなのだと、深く感じるところがあった。甫周は維新後は明治政府の役職には就かず、浅草に繕生薬室(実体はよく分からない)をつくり民間の医療衛生の普及に努めたということであるが、将軍家との密な関係から新政府に出仕することは心が許さなかったのだろう。将軍家への帰依は絶対であったが、甫周やみねにとってのそれは政治的徳川体制へのそれというよりは生身の将軍への献身であったようだ。甫周は将軍が病気であった時、大名幕臣が居並ぶ江戸城で、気がせいて、彼らが平伏している頭の上を飛び越えて病床へ駆けつけたのだという。みねものちに結婚した夫が佐賀藩士であり夫が徳川家に批判的な言動を吐くと必ず夫婦げんかになり、一度などは自分から離婚を言い出して夫に驚かれたりしている。
みねは母親が早くに亡くなり一人娘として叔母の香月に育てられたがその叔母も若くして亡くなり、自由奔放に育ったようだが、桂川家では教育というものに意を用いなかったということである。むしろ自由に学びたければ学べという姿勢で、周囲の洋学者たちも、教えられるのではなく自分で学んでいた。そしてみな猛烈に遊んでいた。その遊びはとてもユニークで、歌い、踊り、また頻々と芸者衆が邸内に来ていたがそれは桂川家では芸者衆が心から自由になれたからなのだという。仕事で来ていたのではないのだという。みねがみた江戸末期の人びとの姿はきびきびとして、それでいてどこか柔らかい人間味のある人たちで、それでいて毅然としたたたずまいを見せていた。何度も出てくる話として、明治維新の上野の戦いで戦死した夫を死体の山を乗り越えて探しに行き夫の首を袖に包んで持ち帰ってきた知り合いの妻は僅か22歳であったという。武家の心得はみな骨身にしみていたようだ。維新後、桂川家の屋敷を移ることになるのだが、それまでの屋敷は貧乏とはいえ広大で、庭には池もありなんと鶴(甫周はこうの鳥と言っていた)が遊び、亀が多数いた。みねはいよいよ家を離れる時この亀を置いて行くのが忍びなく「お前たち、みんな連れていっしょに行きたいのだけれど、今度行くとこにはお池も何もないからおいてゆくのよ。お前たちはこのお池を離れないで、いつまでも仲良くおあそび」と言い、皆泣いたと記している。
みねが昔を思う時、明治期の総じて人びとが派手になったことを嘆じている。たとえば私たちは不思議にも思わないが、雛人形。みねの持っていたのは木製であったという。そもそも内裏雛という想定がなかった。天皇には全く想いが至らなかったようで、佐賀藩士の夫がみねを京都に連れて行き初めて天皇について認識したという点は、天皇制は維新以後新たに作り出された制度となんら変わらなかったようだ。
この聞き書きの優れた点はほんの小さな事が人の心に長く残り、人生を豊かにしているのだということである。お月見を厳格にしていながら、下げられた三宝に載せられたおだんごがいつの間にか誰が食べたのかだんだんなくなっていたというおかしさや、厳しき学問にはげんでいた洋学者たちがはめをはずして遊びこけているすがたや、芝居見物の日は皆が盛大に着飾って行く楽しさや、驚いたのは、洋学者たちが何かの拍子に外国語を使った歌を歌い、みねがそれを憶えていたことや、偉そうにしている人をゴッド(神)と言っていたそうだが、これなど冗談のように面白い。両国の花火、七夕、隅田川、粋な芸者衆みねが語り残してくれた江戸の残映は実に美しい。
魔女:加藤恵子