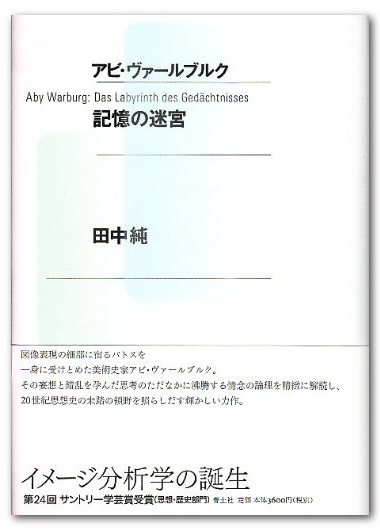ヨーロッパ精神の根源は何か?妄想と錯乱の中からヴァールブルクに見えたものは世界精神の基底だったのか?
『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』田中 純著 を読む。
ヴァールブルクについては彼の死後、彼の遺した書籍をもとに運営されているヴァールブルク研究所からフランセス・イエイツが出たり、彼の研究手法を受け継ぐカルロ・ギンズブルクの書籍を読んだりすることが多く、ヴァールブルク本人の業績についてと、その生涯についてはあまり詳しくなかった。数年前死後に残されたパネル「ムネモシュネ・アトラス」がヴァールブルク著作集の別巻として出版された時に、東大駒場で記念のパネル展がなされて、見に行ったことがある。それは実に壮大であったのだが、モザイクのように色々な写真、新聞切り抜きなどがバラバラに配置されていて、素人には何をどう見たらいいのか分からなかった。これを主宰したのがこの本の著者田中純氏の研究室であった。ヴァールブルクの伝記はヴァールブルク研究所を引き継いだエルンスト・H・ゴンブリッチによる詳細な『アビ・ヴァールブルク ある知的生涯』があることは知っていたが未読である。
田中氏の本書はゴンブリッチが研究面でのヴァールブルクの生涯を綴って、現在の美術史学や文化史、すなわち「イコノロジー」の創始者としての意味を確定したのに対して、田中氏はかなりヴァールブルクの精神的な揺れによる魂の彷徨からくるヨーロッパの運命と歴史的変遷を描こうとしたところに、困難さとともに興味深い点もあったと言える。
ヴァールブルクの辿った道は、それは精神錯乱も含めて、自らがヨーロッパの運命を映しだす鏡のようであり、彼が向かった先にあるものが、当時はほとんど「謎」のように理解不能であった。しかしその核心にあるのは「古代の再生」であり「古代の残存」をあらゆるメディアから収集し、繋ぎあわせることによって、現在に表出させようとした。彼は古代の残存は当然のことながらルネサンス芸術の身体表現の分析に意を注いだのであるが、ルネサンス絵画の細部(たとえば、描かれた足が地面につく時の反り返り)からその激しい情念を表す古代の形態言語の復活を追求している。ヴァールヴルクのこうした思考は、彼の身体を襲う受苦、避けがたい狂気と切り離せないと言う点を田中氏は中核において本書は書かれている。その狂気はニーチェやフロイト、さらにはベンヤミンなどの思想と交錯し、「古代」という記憶の表象とヨーロッパ近代とがワープしてみずからを襲ってくるその葛藤を追跡するとともに、「身ぶり」という身体イメージを通じたヨーロッパの歴史を貫き情念(パトス)の分析と、イメージに依拠した精神分析学の作業ともなった。
ヴァールブルクの研究業績の重要性もさることながら、その研究がなぜ生まれたかという点で、ヴァールブルクの背景が実はかなり面白い。田中はこう書いている「ドイツ帝国の成り上がり者」。
在野の学者であるアビ・ヴァールブルクの名を高めていたのは、ルネサンス美術をめぐる独創的な研究や国際美術史学会の企画・運営の実績とともに、個人所有としては異例な数の貴重な蔵書であった。定職をもたない身分にもかかわらず、自分自身の研究機関で研究に没頭し、貴重品を蒐集することが可能だったのは、銀行家一族という出自ゆえの豊富な財源による。ヴァールブルク家とは18世紀末から19世紀前半にかけて基盤を固め、ヴィルヘルム2世の帝国で繁栄の頂点に達したユダヤ系経済エリートの一族であり、典型的な「成り上がり」タイプのユダヤ人であった。19世紀にはドイツ社会へのユダヤ人の文化的同化が社会・経済的統合と同時進行したため、マックス・ヴェーバーの言う「賤民(パーリド)的資本主義」の担い手から近代的ブルジョアへのこの変身の過程で、成り上がり者としてのユダヤ人はあくまで既存の政治・社会秩序を尊重する順応主義を採用することになった。賤民としてのユダヤ人が根なし草的な無国籍者であったのに対して、成り上がり者は逆に、祖国としてのドイツに決定的に帰属することを夢見た。彼らは周囲の社会に受け入れられたいという欲望に憑かれ、支配的制度に順応しようと努める一方で、みずからのユダヤ性を必死に抑圧しようとした。葛藤に満ちたこうした関係は、時として自己否定、自己憎悪というかたちをとり、あるいは東欧ユダヤ人に対する嫌悪や拒否となって表れた。なぜなら、東欧ユダヤ人は自分たちが同化によってつちかったイメージとは正反対のユダヤ性のイメージを想起させるものだったからである。成り上がり者はむしろ反ユダヤ主義者に受け入れられたがル傾向にあった。東欧ユダヤという「ユダヤ人としての他者性の顔」は彼らにとって、」いままでの同化の努力をすべてを無駄なものにしかねない危険な存在に思われたのである。そして、当のアビ・ヴァールブルクもまた、この「精神的両極性」に引き裂かれ、ユダヤ人であることの矛盾に囚われていた。二つの対立する性質の分裂した共存状態である「両極性」はヴァールブルクの思想における鍵概念となる。ヴァールブルクの生涯において、ユダヤ教との関係はほとんどつねに、過剰なほどの敵意をともなって緊張を孕んだものであるつづけた。父モーリッツは自分が生まれ育った環境である正統派ユダヤ教の信仰を忠実に守り、家族にもそれを求めたから、アビのユダヤ教批判は同時に父に対する反抗という性格をもつことになった。ヴァールブルクは、ドイツ国民の自己同一性に欠如、同一化の失敗こそが反ユダヤ主義となって表れることに気づいている。ヴァールブルクは「ユダヤ人ノ血ヲ引キ、心ハハンブルク人、魂ハフフィレンツェ人デアル」と自己規定した。「ドイツ人」であることはそこからは抜け落ちている。そして、より「ドイツ人」であろうとすることによって、彼はほとんど反ユダヤ主義のまなざしに同一化しかねないところまで進んでゆくのである。そしてシオニズムと同化の狭間で1908年に書かれた或る手紙でアビ・ヴァールブルグは自分を、もはやユダヤ共同体にはまったく関係しない「棄教者」と呼んでいる。あるいは1912年の手紙では、自分は「シオニスト」と「同化ユダヤ人」のあいだに位置する「未来派」であると規定している。彼はユダヤ教を拒絶する一方で、ついにキリスト教に改宗することもなかった。彼は、プロテスタントの女性と結婚し、さらにはイタリアに住み、ルネサンス研究に没頭する。この事による精神的な葛藤が、彼を狂気にさまよわせることになる。
ヴァールブルクは1908年頃から占星術の歴史に関する研究を始める。古代末期の神々のイメージが初期ルネサンスを媒介するメディアとして占星術の図像に転移している事を分析した。イタリア・ルネサンス芸術は、異教古代文化のイメージとの関係で語られなければならないというヴァールビルクの天才的インスピレーションであった。さらに、異教=魔術的古代も実は単なる古代を見出したものではなく、ヨーロッパの歴史において、再認の過程によって生み出されたものであるという認識は彼のアイデンティティーの揺らぎを生み出す事ともなる。少し飛躍するようだが、古代的魔神のイメージはフロイトがE・T・A・ホフマンの『砂男』の分析を通して無気味さの根源を書いたのと同じような感情をヴァールブルクは「古代的」魔神の復活に見ていたようなのである。
ヴァールブルクは1895年アメリカに渡りニューメキシコのプエブロ族の村々を回るのであるが、30年ほどのちにこれが「蛇儀礼」として発表されることになる。そこに至る彼の生涯でやはり興味を引くのは、膨大な書籍の蒐集とその分類のエピソードである。彼は銀行家の跡継ぎを放棄する見返りに、生涯買いたい本はすべて購入できる権利を弟に約束させそれを果たさせた。その膨大な書籍は、ラベルも貼られず彼の思考が繋がるように配置されていたという。この本の配置が彼のイメージの展開になっていたということは、生涯の終わりに「ムネモシュネ・アトラス」として残された、パネルの構造と同じである。ヴァールブルクは新聞の切り抜きなども膨大に集めていたということであるが、ある思考を開くたびにそれを入れ替え、配置換えをしていた。確かに平面として見ればたんなる平たい張り紙でしかないが、その距離感やずれなどが、彼の頭の中では立体的に捉えられるようになっていたようである。現在であれば、コンピュータで三次元に見せることは可能で、思考をそのように表記しようとしたヴァールブルクの先見性(というよりは、実務的かもしれない)がとてもユニークである。書籍は後に助手を務めたハイゼが色分けなどを取り入れたようであるが基本的に隣接する書物とのリンクに意味があることの分類は活かされた。
また、彼の研究所の建物にも触れられていて、あまり実用的ではなかったようであるが楕円形で、つまり焦点が2つあるような構造になっていたということである。これは田中純しが建築出身の方らしい記載で興味深く読んだ。
細かい研究の成果については、本書やゴンブリッチの伝記を読んでいただくとして、狂気からの脱出が精神病院で行なわれた「蛇儀礼」に関する講演にあったという点には、驚かされた。また彼が心臓まひで亡くなったのが、一九二九年十月二十六日で、十月二十四日はニューヨーク株式市場が大暴落し、大恐慌が始まった直後であったと言うことも又驚きであった。
ハンブルクにあったかれの研究所は第二次世界大戦を避けて現在はロンドン大学に移設され多くの俊英を輩出している。
魔女:加藤恵子