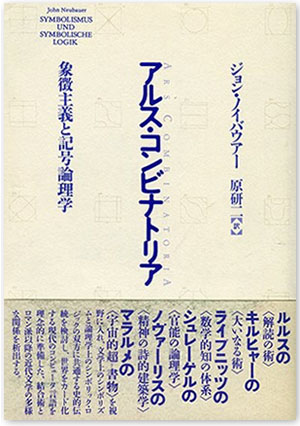
訳者あとがきを読むと明白なのだが、本書、いやアルス・コンビナトリアという概念を強調し、その意味の重要性を広めたのは学魔高山師である。それゆえ、この概念についての大まかな見取り図は理解していた。しかし、ちゃんと読まない奴は死ねといわれていたし、もうすぐ死にそうな気分なのでがんばって読んだわけである。あとがきからもわかるが、アルス・コンビナトリアって何?という点から、さらには象徴主義と記号論理学がどうして「と」という接続詞でつなげられるのか?原書の副題が「アルス・コンビナトリアの現代文学への展開」というのだそうであるから、これはいったい文学書なのか?もう題名の時点で混乱をきたしかねない。帯にはルルスの「解読の術」、キルヒャーの「大いなる術」、ライプニッツの「数学的知の体系」、シュレーゲルの「官能の論理学」、ノヴァーリスの「精神の詩的建設学」、マラルメの「宇宙的超――書物」が論じられていることになっている。ルルス、キルヒャーは魔術的知だろう、ライプニッツは数学的知だろう、その後のノヴァーリス、マラルメはどう繋がるのだという不安が生じる。しかし、学魔高山師からはこの筋道は大体教えられていたから、驚きはしなかったが、聞くと読むとは大違い。驚愕の本だった。
アルス・コンビナトリア(結合術)の歴史は神秘主義との関連として出現している。かつ言語問題とのかかわりが深い。さらにいえばこの宇宙の創造者たる神の意思についての認識に関わる神学も重要な要素である。かくも壮大な問題を簡単にのべられるものではないが、神を恐れずに言ってしまうと、この宇宙を創造した神は宇宙を物質で充満させた。それを表しているのが言語である。新しいものを作り出すということは単に神が充満させている物質の中からいわば掘り出すことなのだ。そこにかかわるのが結合術というものであるという考え方が神秘主義である。その基盤にあるのが数である。ピタゴラス以来、人間の神秘は数の中に隠されているという考え方は実は近代結合術の創始者たるライプニッツによって提唱された認識なのである。しかしライプニッツ自身の宇宙概念はむしろ前近代的な範疇であった。つまりライプニッツは「ピュタゴラスの神秘主義とカバラのそれは、しばしば誤用されてきたが、「数、記号、あるいはある種の新言語によって」奇跡は発見可能であるという信仰は根深く生き残っている。ある者はこの言語を「アダムの言語」と呼び、ヤーコブ・ベーメにとってはそれが自然言語であった。結合術によってライプニッツはこの根源的であるとともにラディカルでもある新言語の根拠を与えようと望んでいる。こういう企てに彼を駆り立てたのは、言語もコスモスも合理的な構造を持つ、という信仰である」。このライプニッツの観念の自然科学の構造を文学の形式に持ち込むことが可能なのかが本書の中核となる部分だと言える。
さて、ロマン主義問題にである。その中でもノヴァーリスについて、作家を含めて多くの人々は、本書によれば全く理解していない大馬鹿ものばかりと言うことのようである。ロマン派と言えば、反近代の想像力に育まれた幻想文学派として絶大な人気を誇って来た。これをライモンドゥ・ルルスからバロック文学、ライプニッツに注ぎ込み、ロマン派に受け継がれ、フランス象徴主義に至る(日本の場合には北村透谷から奥泉光まで)まで、世界を記号としてとらえすべてを演算運動として記述する、それがノヴァーリスであり、マラルメ、ヴァレリーである、と。
ノヴァーリスってどう考えても、憂いを含んだ、死にそうな軟弱なロマン派的なイメージであるが、これが大間違い。彼はそもそも鉱山技師。科学者であることが先なのだ。彼はカント、ヘムステルホイスを読み進めるうちに(1797年)、早くも数学と記号論の問題に出会い、1798年にはフライベルク鉱山アカデミーに滞在し、この方面の研究に没頭している。さらに神秘主義と新プラトン主義の伝統にとどまらず、ライプニッツに関する情報を集めて読書を進めている。「1799年春フライベルクからのノヴァーリスの帰還はひとつのシグナルである。彼のシステマチックな科学研究の終結、そして新たな課題への転換。岩塩業運営への専従、予定される結婚のための準備、改めての宗教への専心、自然哲学から文学の理論と実践への移行、ついには死に至る病・・・と、すべてが彼の全精力を消耗させていった。彼の自然学上の知識は、なるほど鉱山技術の課題を解決するために、あるいはまた神秘学的、歴史哲学的、病理論的思弁を進めるために適用されはしたが、彼の思弁が厳密な自然科学的思考の尺度でなお計れるかどうかは、当然な疑問であった」。
さてその前に、ライプニッツは何を目指したのかも触れておかなければならないだろう。彼は概念計算という思考を規定する枠組みを提起している。世界を認識する手段は複合されている物事を「分解」し、そこで獲得された基本概念を結合術/順列組み合わせによって「統合」し直す事である。重要点は、概念を字母で表記したルルスとちがって、ライプニッツの理想は数字による記号システムだった。数字ですべてを理解できるか?当然現代なら即コンピューター言語が想像されるであろうが、批判は当然現れる。「概念計算は文学的言語使用には耐えられないとしばしばいわれるもっともな理由がある。それは文学、とりわけ抒情詩が一義的な語義決定ではなく、隠喩的アナロギーを求め、言語の多層的な性格から生まれることに由来する。とはいえ、ライプニッツの概念記号を適用して意味を一義的にしてしまおうという試みばかり見ていては、ロマン派によって発掘利用された結合術というレヴェルを見逃すことになる。形式―論理学的構造がもたらす何にでも適用できる抽象的性格は、特殊な内容や一定の意味を断念することになるが、まさにそのゆえに連想と解釈の可能性を豊かに提供してくれる。
あのノヴァーリスがライプニッツの結合術・順列組み合わせの精神についてこう言っているのである。「数学のシステムは、純粋言語記号システムの母型である。-われわれの文字は数字に、われわれの言語は算術になるべきである」。すでに1797年にカント研究との関連でも同様のことを言っている。「概念はいわば判断のエレメント、言葉を形づくる文字のようなもの」。結合術、順列組み合わせ、それが数学としてではなく文学へと展開する契機を作ったのがノヴァーリスという流れになるだろう。ノヴァーリスがこんなことを考えて『青い花』を書いたんて、びっくりだ。ノヴァーリスが執心していたのはラヴォアジェの新しい化学における元素の組み合わせであったらしいのだ。ノヴァーリスは次のように書いている。「完全に定義された認識は記号に変えることができる。比喩的表現は、われらの定義づけ、同時に図表化する術を指している。完全な比喩を介すれば、精神数学は基礎を得ることになるだろう」、と。ノヴァーリスについては『青い花』の一節「もはや数字と図形があらゆる被造物の鍵ではなくなる、そしてあのように歌い、キスする者たちが深い学識の者たちよりもっと知っているなら」という一文から数学の支配する現代批判として日本には紹介されているのだそうだ。しかしノヴァーリスの数学について、本格的に書かれたのはこのノイバウアーしかないと訳者は書いている。ライプニッツはドゥルーズやセールがとりあげていて、いまや現代へ続くみごとな先行者として語られるのであるが、その間のノヴァーリスの代数学による世界の記号化と演算可能性はライプニッツのコンピュータリズムへの連続性より一歩進んだ、人工知能時代のコンピュータリズムへの架橋を読み取れるといえる。さらに世界を記号化する先に期待されたのはすべてを書きとめるということ、つまりは「百科全書化計画」ということになる。ライプニッツの意図は、結合術があらゆる可能世界の構造を捉えることができると言う点に出発点があり、経験を得る領域は現実世界であり、矛盾を内包しないのが可能世界であり、その両世界を神の理性が包み込んでいる。前近代の神の概念から当然の認識である。この点がノヴァーリスが本質的に変更を加えた部分である。
つまり、ライプニッツの「百科全書」とは結合術・順列組み合わせの学であり、分析の果てに得られる基本概念のことをいい、これに対して、ノヴァーリスの百科全書は結合術的な結びつきによって検証される概念の複合体であるという真逆の認識である。そこからノヴァーリス以降のロマン派文学のキー・ポイントになるポエジーへの道が析出される。私には詩的なものが全く欠如していて、絶望的に音痴なのだが、ヨーロッパの詩における音韻論、詩形式がすさまじく数式に似ている事は承知している。だから分からないのではあるが、芸術を論じるものは詩を論じられなければ全く意味がない世界を驚異をもって垣間見ているだけである。ドイツロマン派がノヴァーリスによって示された言語の可能性を詩的に表象し得たこの系列はフランス象徴派、とりわけステファン・マラルメによって実現される。マラルメにとっては文学は神秘的・知的救援行為であり、世界から失われてしまった意味の捜索、数学的計算によって偶然と戯れ、言語の実験的探求を意味し、世界から抽象化することを意味した。マラルメは新しい配列を探求した。「言語形式は諸関係と演算のもたらす模様なのだ、それはーー任意の対象と異質な質を持った記号の結合と連合を可能にすることによってーーわれわれの知的宇宙の構造を発見するための有用でありうるのだ」と。ここにもあきらかに結合術による世界理解の手段とするイデオロギーが見て取れる。
書けば書くほど結合術とは何を意味するかは単純でありながらもっとも深く宇宙内存在を理解する手段に留まらず、神概念の変化にもかかわらず、すべてをいかに理解の下におくかという人間としての哲学の根源にかかわる問題である点に思いが至るであろう。ロマン派認識のかなりの間違いは、いまや明らかであるが、この宇宙を記述したいという欲求について、アルファベット順に世界が配列される、無機質な百科事典的な網羅に意味はあるのか?ここには結合術の出る幕はない。ノヴァーリスの志向したのは、実際に存在するものが併記される代物ではなかったであろう。この微妙意味を体現しているとも言える松岡正剛の『フラジャイル』にはこうあるという。たしかに読んでいたけれど、そこまで読み切れていなかったが、「自然をアトミックに分割して、その分割されたものの総体をもって全体性をさししめそうとする還元主義の立場と、断片そのものに全体の香りを聞こうとする立場は、けっしておなじものではない」。と。
ここに至る論の構成にかかわる書物は、まずもってホッケ『文学におけるマニエリスム』、フランセス・イェイツの魔術的ルネサンスに関わる著書、パウロ・ロッシ『普遍の鍵』、高山宏『メデューサの知』、エーコ『完全言語の探求』。訳者によれば、すべては高山師が引っ張りまくって、自分でかってに乗り越えていったアルス・コンビナトリアであったようだ。学魔恐るべし。
魔女:加藤恵子



