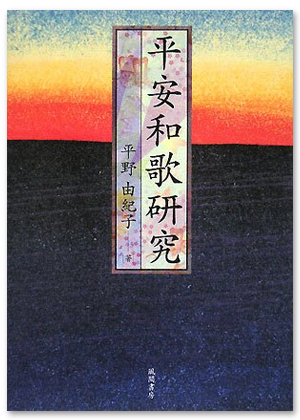
古今和歌集における掛詞の重要性を理解できなかった正岡子規への反論の書だ
長年に亘り、平安時代の和歌の研究に取り組んできた著者の論文集だけに、『平安和歌研究』(平野由紀子著、風間書房)には、いろいろと教えられることが多い。
個人的に、とりわけ勉強になったのは、●紫式部の没年についての考察、●「物を書く女房たち」と「読み手としての女房たち」の存在の指摘、●古今和歌集における掛詞の重要性を理解できなかった正岡子規への反論――の3点である。
紫式部の没年については、●岡一男の長和3(1014)年説、●萩谷朴の寛仁3(1019)年説、●角田文衛の長元4(1031)年説――の3つが発表されている。「寛仁3年5月には存命だった紫式部を、この歌群(=紫式部が晩年、越後に在任中の父・藤原為時のもとに見舞いの便りを送ったが、当の紫式部が先に亡くなってしまい、その手紙を祖父から見せられた娘・賢子が物思いに沈んで詠んだ4首)のように3月3日に娘賢子がしのんでいるところからは寛仁4(1020)年春没したと推定されるのではないだろうか。紫式部の没年の上限は、寛仁4年と考えたい。下限は万寿2(1025)年とみる」。これまで、私は角田説を支持してきたが、平野説に変更せねばなるまい。
「和泉式部続集の巻末に、日次歌群と呼ばれる72首の歌がある。9月上旬から11月3日ころまで日次を追って詠まれている。わずかな例外を除き、毎日その日の歌を1首〜3首ほど記している。近年にわかに注目されてきたこの歌群は、忍ぶ恋に悩む女の独詠が、日毎に深まりゆく秋の雲や霧、風に舞う紅葉や弱りゆく虫の音とともに示される」。著者は、この歌群が詠まれた背景を考察している。
<たねをとるものにもがなやわすれぐさ生ひなばかかるあともみえじを>と<とをつらにたつるなりけり今はさは心くらべに我もなりなむ>。「日次歌群の終末に近いこの2首は、身を焦がす恋の切なさと、その人に会えぬ嘆きが、晩秋の風景とないまぜに縷々記されてきた中にあって、その恋がどのような類いのものかを知る重要な内容を持っている」。
「日次歌群は、宮仕えする女の、会うことの叶わぬ貴人を恋う秘めた心のゆらめきが、日毎の秋の深まりと初冬の景と融合しあい独自の世界を呈している。文のやりとりに一喜一憂し、夫や侍女たち朋輩の女房など周囲の人々の目をはばかり、こちらの慕う程、相手にとって自分は特別な存在ではないと思い知らされ、こんな苦しい恋を断念しよう、自ら断ち切りたいと念じても、出来ない。仏の教えに救いを求め、すがろうと勤行しても鎮められない」。恋の苦しさは、平安時代も現代も変わらないのだなあ。
「冒頭と末尾の趣向、歌にも詞書や左注にも引歌の多いことを考えると創作された連作ではないのか。・・・日を追って1日1詠ないし2、3首詠を記すのは、一見、日毎に歌を記した素朴な歌日記と考えられがちだが実はそうではない。・・・日次に歌を記すというアイディアは、必ず編集という作業を伴うはずで、これは全く新しい文芸形態の開始であったのだ」。芭蕉の『おくのほそ道』にも編集が施されていることが思い起こされる。
「女房として或る邸に仕えている作者が、近くにはいない貴人への秘めた恋の煩悶を形象化したと考えてはどうだろうか。誰に向けて書いたかを考える時、ごく限られた範囲、つまり同じような女房生活を送っている人、そして、漢詩句や古歌・近き世の歌などを共有している女房たち、書き手でもある才能豊かな女房に読まれることを予想して書かれたものではないか。・・・紫式部には物語を書いては見せ合う女友達がいた。・・・当時宮廷社会には『物を書く女房』たちが層をなしていた。・・・日ごとに1首ないしは2首配すことは編集という作業を伴うのであって、過去の作や今の作をとりまぜながら、あたかも一日一日進行する日々の、秘めた恋に懊悩する女の心の動きを、読者は隠れ蓑を着たかのように共に味わうべく、歌は配列されるのである。・・・源氏物語はすぐれた超越的な主人公の物語であるが、身分のちがう貴人に愛される女房、源氏物語でいえば、中将・中務・中納言の君のようなクラスの女房たちを、この『日次歌群』の読者と考えるのである」。出仕先の異なる女房間の交流、「物を書く女房たち」と「読み手としての女房たち」の存在という、著者の大胆な主張は説得力がある。
「古今和歌集に始まる平安時代の和歌において、最も重要な技法は、いわゆる掛詞にあるといっても過言ではない。江戸時代の洒落や地口と区別できなかった正岡子規には、古今和歌集の歌の本来の輝きは見えるはずもなかった」。
「古今和歌集において、広義の掛詞すなわち共通音声部分に二重の意味をもたせることは、明らかに詠み手の意図したところである。一首が歌として成り立つかなめに、その広義の掛詞が存在している例はいくつもあげることができる」。
「古今和歌集は、一首の中心の掛詞を軽視しあるいは無視した後代の読者によって誤解されてきた。しかし明らかに作者たちは広義の掛詞を核として歌を詠んでいた」。
例えば、<いとによる物ならなくに別れ路の心ほそくもおもほゆるかな>と<わがこひはしらぬ山路にあらなくにまどふ心ぞわびしかりける>について、こう解説している。「『糸に縒るもの―ほそし』と、『別れ路の心ほそくもおもほゆるかな』という2つの想、『わが恋―まどふ心ぞわびしかりける』と『しらぬ山路にまどふ』という2つの想は、全く同じ強さで同時にたちあらわれる。この2つの想は、一方が他方に組み込まれたり、従属したり、一方が他方の比喩であったりすることはない。2つの想は論理的関係は少しもなく、独立して、しかも同時にたちあらわれるまま、読み手もそのおもしろさを楽しむのがよいのではなかろうか。その不思議なことを可能にするのが『掛詞』なのであって、古今和歌集にはその方法的自覚が明確にあらわれている」。正岡子規ではないが、私も古今和歌集の掛詞は技巧に走り過ぎと冷たい視線を送ってきたが、今後は好意的に鑑賞することができそうだ。



