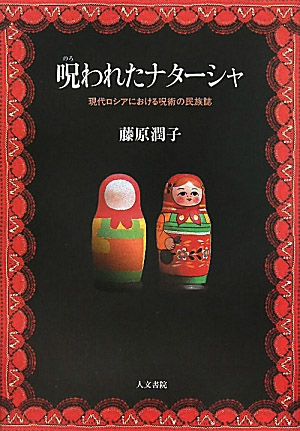
『呪われたナターシャ 現代ロシアにおける呪術の民族誌』藤原潤子
『呪われたナターシャ 現代ロシアにおける呪術の民族誌』藤原潤子 を読む。
題名に引かれて買ってしまった。そして読んでしまったが、はっきり言って、つまらない。これは文化人類学の博士論文であるということで、体裁がアカデミズムの枠内に収まるように構成されていて、刺戟的な題名にもかかわらず、フィールドワークの成果がメインになっていることで、平板な印象がぬぐえない。それでも、現代ロシアにおいて呪術が非常に盛んであり、特に呪文が非常な効力のあるものとして行われているということの事実にはなかなか興味がわいた。
問題はその呪術がどこから来ているかである。ソ連時代、呪術は禁止されていた。ロシア正教さえ弾圧されていたわけで、いわゆる宗教はアヘンであるという社会主義の近代化には、迷信は排斥される存在であり、ロシア革命以来徹底して教育されて来た。にもかかわらず、特に農村部では呪術が暗黙裡に行われ、病気治療や農作業の占いのような生活の支えてなって来ただけではなく、魔術として、人を陥れる手段や不幸を投げかける呪いが行われていたようである。本書のメインであるナターシャという女性は姑に呪いをかけられ夫は愛人を作り、子供はいずれも離婚に至り、妹の夫も湖で溺死し、遡って母親の兄妹3名が死亡していて、この不幸の連鎖が呪いをかけられたことによるという認識にいたる経緯を追ったものである。その根柢には結婚の際に旧来のロシアでは祝福のための魔術が行われていた。しかし、社会主義の下ではそのような儀式は迷信として排斥されていて、ナターシャも関心ももたなかった。しかし続いて起こる不幸には呪いがあると魔術師に指摘された時、ナターシャは疑いながらも、次第に信じるようになる。ナターシャはソ連時代にそのような大事な儀礼が「隠されて」しまったために、呪いから身をまもるすべを知らないままに来たことで、ソ連時代の社会主義教育批判にいたる。
ナターシャの例は限られたものではなく現代ロシアでは、ソ連崩壊後無神論から大きく
様変わりをして、呪術リバイバルの様相を成しているという。呪術「体験」の「リアリティ」が支持されるにあたっては、ポスト社会主義という時代性が深く関わっている。ロシアでは、教育、医療、農業などにおける近代化は、科学を標榜した無神論の名の下に推し進められた。それが崩壊したことにより、ソ連時代の近代化のあり方への疑問や科学概念へのゆらぎが生じ、結果としてふたたび呪術が入り込む余地が生じてきたのである。
ロシアにおける呪術師の特徴は呪文が重きを成している点が興味深い。この呪文は呪術師が血縁を主に伝承されるが、この呪力は必ず死ぬ前に伝承されなければならずそれが行えないままに呪術師が死亡すると、非常に悲惨な死が生じるとされている。また呪術は教会の洗礼を受けた者にしかその効力は発揮されないという点で、キリスト教との混淆が見られる。
いろいろ興味深い事例が書かれているが、本当に知りたいのはこの呪術の深層である。多分予想されるのは、この魔術はキリスト教以前からあったものに後にキリスト教と乗り合わせが起こったのだろうと言うことであるが、そのような視点が本書には希薄である。たとえば呪術の伝承の儀式が風呂場で行われ、十字架をはずして行われるという点などはもっと追求されるべきだと感じる。
人類学といえば山口昌男のフィールドワークによる目の覚めるようなパラダイス・チェンジを実感したものとしては、人類学がこの程度の記述でいいのだろうかと感じてしまう。とはいえ、現代ロシアの深部の不思議な世界を垣間見るにはいい本ではある。
魔女:加藤恵子



