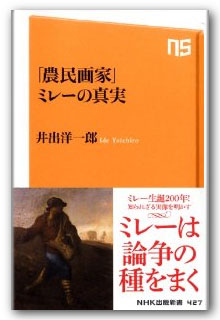「道徳・信仰・清貧・農民」というミレー神話への挑戦状
幼い頃からジャン・フランソワ・ミレーの「落ち穂拾い」と「晩鐘」に親しみを感じてきた私は、パリに行った際、オルセー美術館で待望の実物に対面したが、これだけでは満足できず、その舞台となったパリの南60kmのバルビゾン村の畑まで出かけていったのである。
こういう私が、『「農民画家」ミレーの真実』(井出洋一郎著、NHK出版新書)を手にしたのは、当然の帰結であった。そして、本書によって、私が抱いていたミレー像は粉々に打ち砕かれてしまったのである。
「センチメンタルな農民画を描き、聖女のような祖母と母に対して献身的な息子であり、たくさんの子供たちのよき父親であり、彼が生まれ育った生活を単純に描いた農民であり、19世紀版のフラ・アンジェリコのような、聖書を熱愛した信心深い人間である。また、極度の貧困と生涯闘わなければならなかった美徳の人でもある」。著者も当初は私と同様の印象を持っていたことを知り、ホッとした。
著者は自ら4つの疑問を挙げ、それぞれの回答を提出している。疑問1は、ミレーは道徳的な人物か。疑問2は、ミレーは信心深いか。疑問3は、ミレーは清貧か。疑問4は、ミレーは農民か――である。「(アルフレッド・)サンスィエ(=ミレーの親友、マネジャー、画商にして、大部のミレー伝の作者)はミレーが画家以外の何者かであるかのように(ミレー伝に)書いたが、ミレーはあくまでも優れた才能を持った大画家であって、聖人でも道徳家でも、隠者でもない。頑固者だが社交性もユーモアもある、普通の人格の持ち主である」。
バルビゾンのミレー家に客として数日宿泊したアレクサンドル・ピエダニエルが、その訪問記にこう記している。「娘たちは、昼間は林や庭で母の仕事を手伝う。彼女たちが集う花の棚はいつも玉を転がすような笑いでいっぱいで、生きていることの幸せを感じさせる。父親ミレーはアトリエで魅力あるこの騒音を聞いている。子供たち(=3男6女)は彼にとって力であり、希望なのである。気分が乗らなくなると画家は扉を開け放ち、子供たちに駆け寄る。一人を抱き上げてキスし、みんなに声をかけておしゃべりする。・・・家族の皆が父の仕事と瞑想を尊敬している。アトリエの扉は閉ざされていないけれども、誰も許可なしに入ろうとしない。私は7歳にもならないジャンヌが、かわいい指をバラ色の唇に当てて、『シーッ、パパはお仕事中なの』と言うのを聞いた。・・・ミレーは美辞麗句を嫌い、一般に最も短い言葉こそが最善の表現だと信じている。彼の言葉遣いは胸にしみこむような独創性を常にはらんでいる。・・・世間はミレーの芸術を誇張したレアリスムだと言って、彼を先入観で非難した。しかし、彼の芸術は何ら意図的なものではない。ミレーが理解し、その壮大さを見事に表現したのは、彼の自然への愛であり、まさに真実に基づいたものであった」。「ピエダニエルは、いかにミレーがよき父親であり、多くを望まず、社会の無理解にもめげずに寡黙に自己の芸術を高めていったかを述べている」。
著者は、ミレーが柔軟かつ研究熱心な画家だったことに着目している。「カチッとした新古典主義から出発したが、たちまちそこから外れて、ロココ・リバイバルのふんわりソフトな18世紀様式に戻り、それから写実主義の『種をまく人』でコテコテの厚塗りを極めて、パステルのサラッとしたグラデーション表現に行き、最後は印象主義に通じる風景画の光の分析の際で倒れている。つまり、常に研究熱心で、絵画の新傾向にすこぶる敏感であり、年寄り臭い頑固一徹のイメージとは全く違う。注文も意外に柔軟に受け、顧客の反応や場の空気も読み、バルビゾンにあってもパリの美術界の情報収集は友人たちに依頼して実に素早い。画料が上がって余裕ができれば、その分をさっそくほかの絵画や美術写真、そして浮世絵の収集などの自己投資にかけている」。当時の最先端メディアである写真やカメラを活用したに違いないというのだ。
著者は、ミレーは先端的なエコロジー思想の持ち主であったと述べている。
さらに、ミレーは女性のパワーを認めた、当時としては珍しい画家だと評価している。「この時代、農婦を含めた女性のイメージは、まだ都会の男性鑑賞家によるエロティックな愛玩物であった、しかし、ミレーの絵の中で彼女たちは、あくまで農村共同体での男女の役割分担の範囲内であるとはいえ、見事に労働を担い、女性像はたくましく変革されている。・・・例えば男たちが木を伐り、それを背より高い薪の束にして女たちが森から運ぶように、ともに作業をしないと生きてはいけない森の掟を、ミレーは尊厳をもって訴えたかったのだと思う。当時では先端的な女性像の表現として評価してよい」。この箇所に至り、私がミレーの絵に惹かれる理由が分かったような気がする。
「ミレーを神格化せず、あくまで一人の優れた(等身大の)画家として扱う」。この著者の目的は十分達せられていると思う。