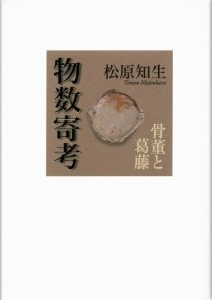古物に魅せられること。それは何も高価な骨董とは限らないようだ。骨董と葛藤とは、絶妙な副題である。
学魔が「凄い面白いぞ」と言いながら、不満げでもあったこの本を読んでみた。多分自分からは手に取る可能性の絶無である本である。驚いたことに、日本の骨董について文化史あるいは美学として考察されたものは今までないということであった。読んでみて、多分学魔が喜んだのは、言葉の語源や意味のずらしや、最後に述べられる写真とカメラ・オブスクーラ(暗い部屋)に身を置く数寄者という象徴などではないかと思われた。一方気にいらない側面とは、がらくたの蒐集に没入して行く数寄者を単にキッチュとしか評価できていない著者の眼ではないだろうか。キッチュこそマニエリスムの極致であり、そこに身を投じる数寄者こそマニエリストとして正統に扱えない美術史家の限界に学魔はいら立っているのではないかと感じた。
さて、「物数寄」であるが、著者はこう規定している「ここにいう「物数寄」とは、単に「もの好き」な人々のことではない。「すき」の語には長い歴史がある。平安期、「好」とは「好色」を意味すると同時に、芸能や風流への系統を指す語でもあった。それが鎌倉時代になると「数寄」と表記されるようになり、意味するところももっぱら芸道や風雅の趣向、さらに桃山期には茶の湯そのものとほぼ同義となった。つまり好/数寄とは、原初的なエロス、およびそれが「昇華」されることによって成立した文化的な実践の両方を含意する、振幅をはらんだ語なのである。
数寄という語がもつ揺らぎはこれにとどまらない。「数寄」はかつて「数奇」とも表記された。「数」が運命を、「奇」が異常をいみするとすれば、「数奇」とは単なる当て字ではなく、過度の執着や偏愛がもたらす変転や波瀾、あるいはそこまではいわずとも、「奇」への傾きすなわち「傾奇(かぶき)」を内包しているともとれる。数寄/数奇とはそれゆえ、何かにとり憑かれ、そこから逃れることのできない情熱=受苦(パッション)の謂いなのであり、利休的な「わび」のみならず、織部的な「ひづみ」すなわち逸脱への志向性も、本来的に裡に秘めているのである。
さらに「物数寄」、つまり物への偏愛という場合、今ひとつの両義性がそこに加わる「数寄」という語の響きは「隙」・「透き」・「空き」、つまり空虚や余白、間を連想させるものがある。だとすれば物/数寄とは、空間における物のしつらえ、物と物との取合せに意を払う者のことであり、さらにいえば、物と隙、現前と不在、実と虚の間を自在に往来し、そのあわいに目を凝らす者でもあるだろう。あるいは「数寄」を「梳き」・「漉き」・「鋤き」と読み替え、「数寄」とは何か通過する/させることととるならば、数寄者とは単に主体的に物を「好く」だけでなく、自ら「隙」をはらんだフィルターあるいはパサージュと化すことで物に通過される経験をも指し示す」。と。この本の内容はこれに尽きる。その各論として選び出されたのが、川端康成、小林秀雄、青柳瑞穂、安東次男、つげ義春、杉本博司である。
川端は、敗戦による自らの精神的な危機を古美術を買い求める事で、生の世界に自らを繋ぎとめた。川端にとっての古美術は死者の棲む世界への橋渡しをする媒体であった。彼は特に書画の類に入れあげ、嘘かまことか、誰も信じていなかった頃にノーベル賞の賞金まで担保にして書画を買い集めたのだそうだ。小林秀雄は戦前に一時期、狐につかれたように骨董を買いあさったのだという。小林の骨董への偏愛は、その物質性に対する情熱で、そこから歴史を手触りとして探り出し、戦争という苛酷な状況を超越するよすがとしたという。この二人はいわば文学と骨董という範疇に属するものであるが、次の二人、青柳瑞穂と安東次男の場合は「いずれもある欠如(隙=数寄)(こう言う言葉のずらしが学魔に好まれる所だろう)への執心」を特徴ずけている。瑞穂を虜にしたのは骨董に付帯している偽物の内的意味であり、安東次男のそれは物理的な欠損、すなわち「キズ」であった。この偽物とキズに関する論考は非常にスリリングで興味深い。瑞穂は美しければ真贋の問題などどうでもいいとする一種の芸術的なエリートの考えに対して「美しかったら、偽物とていわぬというのは、美を第一に見きわめようとする態度として健気であるとしても、結果からいって、ギブツが美しかろう筈はありません。美しかるべきものは、ホンモノのなかにこそ存在していると思います」と述べながら、実は真贋の光と影とを内在するような、いかにも白黒をつけられないような、真贋を超えたところに美術品を見る。言い換えればギブツの暗い影が存在するからこそ骨董の美は存在するというアンビバレントな精神を生きた。すなわち骨董は、存在自体が曖昧であるほど存在感は増す。この「あいまいさ」への偏愛が青柳瑞穂の骨董偏愛の心だと言える。
これに対して、安東次男は古美術の世界での「残欠」の名で呼ばれる不完全なものに身を投じたところに大きな意義を見出している。疵物を賞玩する態度は、茶道には古くから見られたものであるが、この特異な精神構造を厳密に語ってみせたのは安東次男だという。かれは究極において陶片への趣味を深めて、昭和の陶芸史に大きな意味の或る美濃の古窯発見にまで至るのである。さらには陶片をはぎあわせて新たな器を作るというところに行き着く。日本古来の陶器の直し方には「共継(ともつぎ)」といわれる欠けた部分を元通りに嵌めこんで修理する方法と、欠損部分に別の陶片を「呼んで」きれ継ぎ当てる「呼継(よびつぐ)」という技法があるのだそうで、呼継は陶片による新たな創作にまで至るのであるが、そこからは、われものに潜む時を埋め込むことにより転生あるいは死の超越を込めているとみられる。
ついでつげ義春の場合は、いわゆる金額の張る骨董とはかなり位相を異にしている。つげは実際アンティークカメラを収拾し、それを商売にしようとしていたり、変哲もない石を集めて、売ることを作品に書きこんでいたりする。彼は古道具屋を「景色」として、自己の住まうトポスとして偏愛した。漫画の分析によれば、そのトポスは通過・移行の場としての境界にあり、「異人」の棲みかであり「アジール的な境界性」が深くしみ出している。つげはそんな場に自己を描き込むことで彼岸と此岸の間をたゆたう姿を提示した。骨董というよりは、廃品回収や古道具屋にこそ彼の居場所はある点で、とても論としては面白い。
さいごに杉本博司である。現代アートの成功者は実は骨董店を経営したこともあり、次々と骨董を買い集めている。しかしそこにはノスタルジックな懐古趣味とは無縁で、彼の写真やインスタレーションに嵌めこむという点で、古代と現代、夢と現のさかいを取り払い、時間を撹乱するものとして、創造的数寄者といえるであろう。著者は杉本が古物をどう利用するかという点で、それを死者の霊を召喚する依り代としてのしつらえであるとみている。写真において人類がその始原において見たであろう海の眺めを現代に再現する「海景」シリーズは原始的なアニミズムから日本的な神道の霊性が発生するプロセスを可視化した護国神社プロジェクト、「観音廻り」を再現した「杉本文楽 曽根崎心中」。彼の起源への遡行は骨董偏愛に起源を持つことが考えられるが、杉本自身はこのような原点回帰は「もどき」であり真正なものの再現とは認識していないという点が興味深い。杉本はまた大金をはたいて写真の発明者タルボットの残した陰画を買い集めそれを陽画へと転換する試みもしている。杉本はこれについて「銀塩写真の終焉を看取る」と言っているという。写真の葬送と賦活、古美術の蒐集と現代見術の創造とが杉本の場合は溶け合っており、数寄者の古くて、新しい真正の数寄の在り方かもしれない。
魔女:加藤恵子