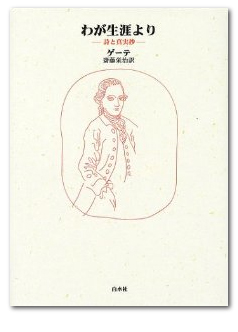私を恋愛至上主義者にした本
私は恋愛至上主義者である。憧れの女性にふさわしい男になろうと努力することで、男は成長していくと確信している。
57歳で亡くなった父は、本の虫であった。とりわけゲーテが好きで、私が大学1年の時、「誠、これは面白いぞ」と譲ってくれたのが、『詩と真実(抄)――わが生活から』(ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ著、高橋健二訳、新潮文庫。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)であった。時が経ち日焼けで色褪せてしまったこの文庫本を手にするたびに、いつも和服姿で読書していた父を懐かしく思い出す。
『詩と真実』はヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの自叙伝であるが、ゲーテが26歳でヴァイマル入りするところまでしか書かれていない。本書は、ゲーテ研究の第一人者・高橋健二の手に成る抄訳(原著の約4分の1)だ。この本が私を恋愛至上主義者にしたのである。
料理店での友人たちとの晩餐会で、「しまいにブドウ酒がなくなったとき、だれかが女中を呼んだ。ところが、女中のかわりに、ひとりの娘がはいってきた。その娘はなみはずれた美しさで、一座の連中のあいだにおいてみると、信じられないほどの美しさだった。『なんの御用ですの?』と娘は愛想よく、今晩はのあいさつをしてから言った。『女中は病気で寝ています。私でお役にたつんでしたら?』」。ブドウ酒を取りに行く「彼女のうしろ姿は一段と美しかった。ちいさいずきんがちいさい頭にいかにも愛らしくのっていた。そしてほっそりした首が頭を背くびや肩といかにも優美に結びつけていた。・・・静かなまごころのこもった目や、かわいい口もと・・・」。「この少女の姿がこの時からどこにいっても、私の念頭をはなれなかった。それは私が女性からうけた最初の永続的な印象であった」。このフランクフルト郊外の料理店「薔薇屋」の娘・グレーチヒェンは、15歳のゲーテの初恋の人(年上)だが、この気持ち分かるなあ。
『詩と真実(抄)』を読んでから14年後に出会ったのが、『ゲーテをめぐる女性たち』(高橋健二著、主婦の友社・TOMO選書。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)である。当時、主婦の友社に勤めていた母からのプレゼントであった。この本は『詩と真実(抄)』の理解を深めてくれるだけでなく、ゲーテが82年間の生涯で愛した女性たちのことを詳しく教えてくれる。
21歳のゲーテが地方の牧師館を訪ねた時、「妹娘が戸口にはいってきた。すると、このひなびた空に一つのたぐいなく愛らしい星がのぼったのである。・・・からだに何もつけていないような身がるさとしなやかさで、彼女は歩いた。かわいらしい頭の大きな金髪のおさげには首が細すぎるように見えた。快活な青い目をぱっちりあけて彼女はあたりを見まわした。・・・麦わら帽子が彼女の腕にぶらさがっていた。こうして私はうれしくも、最初の一目ですぐに彼女の優美さと愛らしさを残りなく見、かつ知ることができた」。この気持ちも分かるなあ。この18歳のフリーデリーケに送った抒情詩「野薔薇」は、世界中で歌われている。そして、ゲーテが60年かけて完成させた『ファウスト』のヒロインにはフリーデリーケの面影が反映している。
「その女性は、母の死後、多ぜいの子ども(=弟妹)をかかえた家庭の主婦役として、この上なくまめな働きぶりを示し、やもめ暮らしの父をひとりで支えていた・・・。彼女は、激しい情熱は起こさせないけれど、皆に好感を抱かせるようなたちの女性のひとりだった。すんなりした愛らしいからだつき、純な健康な性質、そこから生じる快活なまめな暮らしぶり、日々の用事の屈託のない処理、そういういろいろな点を、彼女は授かっていた。こういう性質を観察しているのは、いつも私にとって快いことであった」。22歳で弁護士を開業したゲーテは、舞踏会で知り合った19歳のシャルロッテ(ロッテ)に魅了される。ロッテに婚約者がいることを知ったゲーテは、切ない思いを抑えてロッテのもとを去る。ロッテの身近で起こった知り合いの青年の失恋自殺が『若きヴェルテルの悩み』に採り入れられている。
「この(名門の)令嬢はもちろん愛らしいというほかはなかった。からだつきは、大きいというより小がらですっきりした作りだった。のびのびした優美な格好、黒々とした目、これ以上清らかにはなやかな色は考えられないような顔色をしていた」。ロッテとの別れからほどなく、ゲーテは16歳のマクシミリアーネ(マクセ)に惹きつけられる。このマクセに対する思いが、『若きヴェルテルの悩み』執筆の直接の動機となったのである。
「彼女の優美さと愛らしさは私のものであった。・・・彼女の性格の価値、揺るぎない自信、何事にかけても危げのない手堅さなどは、彼女固有のものであった」。『若きヴェルテルの悩み』で一躍有名になった26歳のゲーテは、フランクフルトの富裕な銀行家の16歳の令嬢・リリーと婚約するが、結婚には至らなかった。リリーは、その肖像画からも明らかなように、十指に余るゲーテの恋人たちの中で最も美しい容姿に恵まれていたというのに。後年、81歳のゲーテが、「まだ生きていた恋人のための配慮が妨げなかったら、私はリリーに対する愛の幸福と苦悩の物語をずっと以前に書きあげて出版していただろう。私はどんなに深く彼女を愛したかを、全世界に言うのを誇りとしただろう。・・・彼女は実際、私が深くほんとに愛した最初の女性であった。最後の女性であった、とも言える」と語っている。
高橋は、「ゲーテほど多くの女性を愛し、また愛され、その女性を詩に歌い、戯曲や小説に描いた人は少ないであろう。・・・愛し愛された女性の数々を多彩な作品によって永遠にした男性は、他に見いだしがたいであろう。・・・それらの女性によって体験した愛の幸福と悲しみを詩化すると共に、そのつどゲーテは人間的に豊かに成長して行った。そして愛し愛された女性もまた、ゲーテによって生きる喜びを味わうと共に、別れの悲しみを余儀なくされながら、やはり人間的に成長して行った」と記している。
ゲーテは、愛する女性との別れに打ちのめされるたびに、恋人との愛の幸福と苦悩の体験を作品に描くことによって、死ぬほどの苦しみの渦中から不死鳥のように甦ったのである。