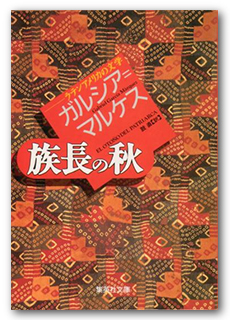独裁者の蛮行と孤独を執拗に描いたガルシア・マルケスの長篇小説
2014年4月に亡くなったガブリエル・ガルシア・マルケスの著作について、ある識者が、「先ずは短篇から読むことをお勧めする。慣らし運転をした後に『百年の孤独』を読み、最後に最も手強い『族長の秋』に挑もう」と書いているのを読み、天邪鬼の私は『族長の秋』(ガブリエル・ガルシア・マルケス著、鼓直訳、集英社文庫)から取りかかることにした。
読了して感じたのは、このあまりにもユニークな長篇小説は「考えながら」読むよりも「感じながら」読み進むべき作品だということ、そして、権力者は大変だなあということだ。
大統領に就任してから100年になろうかという老独裁者の一代記の形を取りながら、過去と現在が入り乱れ、大統領を初めとする複数の人間の独白で物語が紡がれていく。その上、現実的なものと幻想的なものが渾然一体となり、独裁者と取り巻きたちの蛮行、醜行、奇行、愚行が悲劇的に、あるいは喜劇的に、下品で猥雑な表現を交えた熱っぽい饒舌な文体で、止めどなく語り継がれていく。マルケス自身が、「想像力は現実を再構築するための有効な手段だ。しかし、創造の源泉は結局のところ、つねに現実だ」、「自分の書くものでラテン・アメリカの現実に基づかないものはない」と語っている。
主人公は、独裁者ではあるが、睾丸ヘルニアで、ガラスと化した動脈、砂の詰まった腎臓、亀裂の入った心臓を抱え、限度を遥かに超えてしまった高齢に苦しみ、死を恐れる、孤独で哀れな老人である。
権力者であるがゆえの孤独、猜疑心、不安に苛まれて、想像を絶する理不尽な仕打ちを繰り返す。部下や民衆の忠誠心を試すために、影武者を使って頓死を装い、大統領府に乱入した者たちを虐殺する。最も信頼していた将軍が叛逆を企んだと知ると、丸焼きにしてパーティの馳走として供する。宝籤の一等賞の賞金を自分の懐に入れるためのいかさまに利用した二千人の少年たちを爆殺させた後で、この汚れ仕事を実行した部下たちを銃殺に処する――という無軌道ぶりである。
例えば、大統領の唯一の正妻に成り上がった女のエピソードはこんな具合である。「ただ一瞥しただけだったが、大勢の怯えた修練女(修道女)のうちの一人が彼(大統領)の記憶に焼きついていた。・・・小柄で骨太、がっしりしていた。大きな尻、盛り上がった豊かな胸、無骨そうな手、こんもりした陰部、剪定鋏で刈った短い髪、隙間があるが斧のようにしっかりした歯、低い鼻、平べったい足。そこらにざらにいる、平凡な修練女だけれど、裸の女の群れのなかで彼女だけが女だと、彼は直感したのだった」。「夜っぴて彼女の肉体からあふれるものを独りで楽しんだ。月がたつにつれてますます熱くなっていく、牝の山犬のような息を嗅いだ。下腹の苔をまさぐった」。これが二人の馴れ初めであるが、やがて、彼女と二人の間にできた息子は無惨な最期を遂げる。「二人の副官が執務室に駆けこんできて、恐るべき事実を報告した。レティシア・ナサレーノと子供が市場をうろついていた犬に八つ裂きにされ、食われてしまったというのだ。生きながら食われてしまったのです、閣下、しかし、いつも見かける野犬ではありません。それは、怯えたような黄色い目と鮫のようにすべすべした肌をした、狩猟犬の群れだった。何者かが、(彼女の襟巻きの)青狐を見たら襲うように訓練したものだった」。大統領の権威を笠に着て、やりたい放題の彼女に反感を抱く何者かの犯行であった。
正妻と息子を惨殺した犯人を捜し出す役目を買って出た男のエピソードはこうだ。「あるとき、奴は大統領府に頭陀袋を一つ送りつけて来おった。ココナッツでも入っていそうな感じがしたな。というわけで彼(大統領)は、そのへんの、じゃまにならんところに置いておけ、壁にはめ込みになったカードボックスのなかがいいだろう、と命令し、それっきり頭陀袋のことは忘れてしまった。ところが三日たつと、死人の発するような悪臭が漂いはじめ、とても我慢ができなくなった。それは壁を貫いて、鏡の表面を鼻持ちのならない臭気で蔽った。われわれは調理室に悪臭の発生個所を求めたが、牛小屋でもそれに出くわした。執務室を燻蒸してそいつを追い払ったと思うと、謁見の間で鉢合わせをした。悪臭は腐ったバラの匂いと混じって、目につかない小さな隙間にも入りこんでいった。疥癬の発するかすかな臭気が、夜のいやな臭気が他の芳香にまぎれて忍びこむことのないところまで、そいつは潜っていった。悪臭の発生源は、われわれがまさかと思って当たりもしなかった場所に、ホセ・イグナシオ・サエンス・デ・ラ・バッラが例の取り決めによる初仕事として送ってきた、頭陀袋にあった。ココナッツが入っていると思われたそのなかから、それぞれ死亡証明書の添付された六個の首が現われたのだ」。
どのページからもエピソードが溢れ出し、どのページも目いっぱい活字がぎっしりと詰まっている本書は、我々読者に深く考える遑(いとま)を与えず、とにかく次から次へと感じ続けることを強いる、真の意味で恐るべき長篇である。