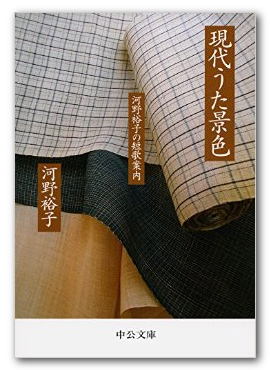短歌に込められた一途な思いが、私を勇気づけ、私を慰めてくれる
「ブラウスの中まで明かるき初夏の日にけぶれるごときわが乳房あり」といった瑞々しい短歌で知られる河野裕子が、歌人としても、選者としても、非凡であったことを、『現代うた景色 –河野裕子の短歌案内』(河野裕子著、中公文庫)が示している。
62回に亘り、有名歌人から、雑誌、新聞の投稿歌人のものまで、河野が選んだ短歌が本書に収められている。
「階段を二段跳びして –青春」の項で挙げられている「ひかりごけのように漏れている図書館のあかりを見つめる君を見ている 岸本由紀」は、女子学生による現代の相聞歌といった味わいがある。
「男尊女卑に怒る太腿」の「リクルートスーツを脱げばあらはるる男尊女卑に怒るふともも 辰巳泰子」には、「このひとは、ふとももで怒っている。一番我慢がならないのが、男尊女卑でそれはこの世の不条理そのものだと怒っている。女に生まれただけで卑しめられるのなら、生まれたそのことさえも、呪ってやる、と啖呵を切るくらいの迫力だ」。「短歌」で「啖呵」というわけだ。「自活するためには、リクルートスーツを着て就職活動をしなければならない。職場を獲得する前段階から、こんなに男尊女卑を味わわなければならないのなら、実際に仕事を始めたらどんな目にあうだろう。そう思うと、辰巳はよけいに腹を立てる。辰巳のように、こんなに過激に怒りを表す人は多くはない」という言葉が添えられている。
「乳房の歌」では、「着古した君のTシャツわが着ればほのかに胸のふくらみ現わる 石井瑞穂」が選ばれている。「与謝野晶子や、阿木津英の乳房の歌を読んできた目で、『着古した・・・』を読み返してみると、何かとても自然な感じがする。石井瑞穂は、何かに反発するために、自分を主張するために歌っているのではない。恋人が着古したTシャツを着てみたら、ほのかな形に浮き出た自分の乳房に、ふと気づいたというのである。ことさらに女性という性を意識し、気負って表現しているのではない。Tシャツの歌の作者は、去年大学を卒業したばかり。まだ23歳である」。
「子供の無い夫婦は」では、「するすみの夫とわれに子のなくて人におよばぬしあわせがある 落合けい子」だ。「『するすみの』という、見なれないことばが気になる。広辞苑をひいてみると、『匹如身』という字があててあり、『資産も絆もなく、無一物なこと』とある。従って、この歌の意は、係累のない天涯孤独の夫と私には、子供も居ないが、二人きりのこの暮らしには、二人きりならではの、人の及ばぬ仕合せというものがあるのだよ、ということだろう。落合けい子の歌は、夫という生涯の伴侶との、子供という介在を持たないがゆえの、個と個の向き合った関係について、様々なことを考えさせてくれる」。子のない我々夫婦にとっては、とりわけ感慨深い歌である。ただ、「人におよばぬしあわせがある」の部分は、「人がおよばぬしあわせがある」のほうがいいと思うのだが。
「会社やめる、会社休む」の「『会社やめる、会社休む』と昨夜言いし夫が定刻に出勤してゆく 亀谷たま江」は、会社勤め時代を思い出させる。
「単身赴任」の「ダンボールにわが家の空気も詰めやらん単身赴任をする夫のため」に対しては、「掲出歌は、単身赴任の夫のために細ごまと身のまわりのものを荷造りしている歌だが、『わが家の空気も詰めやらん』に、妻の切ない気持ちがよく出ている。わが家の空気とはすなわち、妻自身のことでもあるだろう。いっしょについて行きたい。体の半分を、もぎ取られるようなつらい気持ちである」とあり、妻の切なさがひしひしと伝わってくる。
「去りゆく君 –失恋」の「耳つけて君の心音(しんおん)聞きしこと夢と思ふまで遠くなりたり 正古誠子」は、「妻子ある人との恋を歌い続けたこの人の歌には、激情のほとばしるような歌はほとんど無い。内省的であり、淡々とした静かな諦めが歌の表情に、或るおちつきを与えているようにさえ見える。どのように愛しても、妻子ある人との恋には無理がある。そういう恋を選んでしまった女性の自我は、別れの予感のなかに、常に寂しく醒めたものであったのである」と解説されている。男女の仲は難しいなあ。
「老い」の「するすると夕闇くだり見て居れば他人の老はなめらかに来る 斎藤 史」は、現在の私の心情を代弁してくれているかのようだ。
「別れたるのちの歳月 –夫の死」の「別れたるのちの歳月長くして夫の知らざるわれとなりたり 辻下淑子」では、「夫と別れてから長い歳月が過ぎた。夫と暮らした日々。その歳月。夫が知っていた私。その私ではない私が、夫を忘れず夫を思い続けて生きている。共に暮らした日々の夫は、そのまま変わらない。その後の歳月を生きた私だけが、歳月と共に変わってしまったのだ。あたかも、歳月そのものが、夫に代わる伴侶であったかのごとく。この歌は、人生における歳月、人生における伴侶について、さまざまのことを考えさせてくれる。愛し信頼しあえる人と、人生を全うさせて生きられる人は幸せである。しかし、その伴侶と、いつどのような形で別れることになるかわからない」と、夫婦のあり方に思いを馳せている。「夫ありし頃をしのべばときどきの小さな不幸さへ輝きて見ゆ 遠藤淑子」には、「50年間つれ添った夫であった。その50年の歳月のあいだに起こったさまざまなこと、その時々の小さな不幸でさえ、今は輝いてみえる。それも、夫が傍に居てくれたからこそであった」とあり、「次の世もわれを娶れよ君の辺に飯炊き鳥飼い花を育てむ 白岩ゆり」には、「戦争をはさんで、40年共に暮らした夫であった。次の世も私を娶り、また一緒に暮らしましょうよ、と残された妻は歌う。あなたの傍に居て、煮炊きをし、鳥を飼い、花を植え育てて」とある。我が妻も、こういう妻であってほしいなあ。