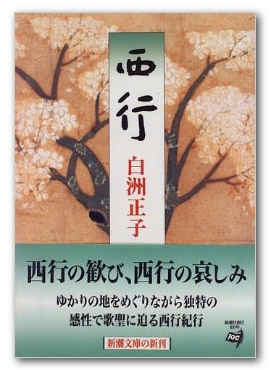西行は、生涯を懸けて「数奇」を追い求めた「数奇者」であった
白洲正子が書いたものを読むたびに、この人は本当に精神的に自由な人なんだなあと思わされるが、『西行』(白洲正子著、新潮文庫)では、その感を強くした。
その道の先達たちの研究成果は尊重するが、それに囚われることなく、自由に自分の感じたままを記していく。この場面では、西行はこう感じたに違いない、こう考えたはずだと、自分の感性を拠り所として書き進めていく。従って、本書に登場する西行は、文字どおり白洲が思い描く西行なのだが、西行の実像はまさにこうであったのではないかという思いに囚われてしまう。
「ごらんのとおりの伝記とも紀行文ともつかぬものになってしまったが、私としてはそういう形でしか西行は語れなかったと今では信じている」。白洲は正直な人でもあるのだ。
西行と明恵の関係は、このように描かれている。「『西行法師常に来りて物語りして云はく』は、いつ頃のことかはっきりしないけれども、西行は建久元年(1190)73歳で没しており、明恵はその時18歳で、神護寺の文覚のもとで修行をしていた。・・・その時以来、明恵はふっつり歌を捨てて、仏道ひと筋に専心するのである。そればかりではない。その翌年から、『夢の記』を書きはじめるのだが、・・・西行の死によって、忽然と目覚めた彼の数奇心が、歌から夢へ向かわせたといっても、間違っているとは思われない」。「一番似ているのは、二人とも非常に女に持てたことである。こんなに女性に人気のあった坊さんたちを私は知らない」。恋歌が多い西行と、一生不犯の清僧・明恵と、こと女性に関しては両極端にいた二人であるが、「今も昔も女というものは、動物的なカンが発達しているから、世俗的な外観にとらわれず、ひと目でそういうもの(『智恵もあり、やさしき心使ひもけだかき』数奇の精神)を見抜く」と、白洲の面目躍如である。
西行と待賢門院との関係については、こうだ。「私が知りたいのは、在俗時代に体験したさまざまの思いが、西行の歌の上にどのような影響を与えたか、ことに失恋の痛手は、誇り高い若武者を傷つけ、生涯忘れがたい憶い出として、昨歌の原動力となったような気がしてならない。・・・西行が(鳥羽天皇の中宮・待賢門院を)『永遠の女性』として熱愛し、崇拝したことに、疑いをはさむ余地はないのである」。著者は、西行と待賢門院との間で「間違いが起ったとしても不思議はないのである」というのだ。「切々としたこれらの歌に接する時、西行の恋がどんなに辛く烈しいものであったか、相手を手のとどかぬところにいる『月』にたとえ、みずからを『数ならぬ心』と卑下したのも、身分の差を意識して涙を呑んだのであろう。・・・その思いが束の間の契りで終ったために、恋心はますますつのったであろうし、ついには作歌の源流となって、多くの美しい恋歌を遺す起因となった」。待賢門院の死後のことであるが、「西行にはそういうしたたかなところがあった。女院(待賢門院)を失うことは最大の痛恨事であったが、生前には秘めに秘めていた恋慕の情を、公然と(待賢門院に仕えた)女房たちと語り合えることに、いささかの慰めを見出したのではあるまいか」。「待賢門院の女房たちと取交わした歌は、このほかにいくらでもあり、何十年経っても女院の面影が忘れられなかったことを語っている」。
西行と在原業平の共通点について。「現代人は、とかく目的がないと生きて行けないといい、目的を持つことが美徳のように思われているが、目的を持たぬことこそ隠者の精神というものだ。視点が定まらないから、いつもふらふらしてとりとめがない。ふらふらしながら、柳の枝が風になびくように、心は少しも動じてはいない。業平も、西行も、そういう孤独な道を歩んだ。そういうことを想わせる歌は山家集の中にいくらでもある」。巧まずして、鋭い現代人批評になっている。
西行の生き方について。「『おろかなる心にのみや任すべき 師となることもあるなるものを』。専門家は、この『おろかなる心』を、仏道を求めない愚昧な心、という意味に解しているが、そんな一方的に考える必要はなく、恋をしたり、桜にあこがれたり、ふらふらと旅に出たり、要するに『空になる心』のことを『おろか』といったのではあるまいか」。「西行の『数奇』は、その祖父(源清経)から受けついだということが、今や定説になっているらしいが、特別な修行者は別として、僧侶が遊里へ足を向けることは珍しいことではなかったであろう。特に西行のような自由人は、気が向けばどこへでも行ったであろうし、そこに西行の心の広さと偏見のない生きかたが見出せるように思う」。「そこに西行のほんとうの姿があり、僧侶でありながら仏教にもとらわれなかった真の自由人の気概が見出されると思う」。西行というのは、ごくごく真面目な歌人、旅人と思い込んでいた私の目から鱗が落ちた瞬間である。
西行にとっての歌とは。「西行が一生かかって達したのは、『歌は数奇のみなもとなり』という信念で、神様もお喜びになると信じていた。当り前のようなことだが、老年に及んでそういう確信を得たことをけっしておろそかに思ってはなるまい」。
西行の、1歳年下の崇徳院(待賢門院の息)への思い。「保元元年といえば、西行が高野山で修行していた時代で、鳥羽上皇の葬送に参列したばかりか、(保元の乱の)敗残の崇徳院のもとへも馳せ参じているのである。当時の情況としては、これは中々できにくいことで、まかりまちがえば殺されかねない。西行は覚悟の上で実行したのであろう。この歌にも、止むに止まれぬ崇徳院への思いがこもっており、世が世なれば自分も院に味方して、命を落したであろうにと、生きて今宵の月を見ることが悔まれたに相違ない。ここで私たちははじめて崇徳院に対する西行の真情を知ることができるのであるが、それは単なる判官びいきとか、主従の情愛とかいうのではなくて、長年の間に育くまれた人間同士の理解の深さによるのではないかと思う」。「崇徳院はすぐれた歌人であり、数奇の好みにおいても西行と共通するところが多かった」。敗者となった者に対しても変わらぬ西行の姿勢には、共感を覚えるなあ。
西行と源義経は出会ったことがあるのだろうか。「二見浦の草庵で、目と鼻の先にいた(義経の家来の)伊勢の三郎と(西行が)面識がなかった筈はなく、もしかすると彼の仲介で、義経とも会っていたかも知れない。そして、(当時、不仲になっていた源)頼朝への取りなしと、(義経の強力な支援者であった藤原)秀衡への伝言などを依頼されたのではなかったか」。
西行の最期について。「建久元年(1190)2月16日、西行は弘川寺において73年の命を終った。その報に接した都の人々の間には、一大センセーションを巻き起した。『ねがはくは花の下にて春死なむ』と歌った人が、あたかも『そのきさらぎの望月』、釈迦入滅の頃に死んだというので、(藤原)俊成以下名のある歌人たちはみな感動して、多くの歌を残した。以来、『ねがはくは』の歌が西行の辞世となって今に伝わったが、地下の西行は苦笑しているのではあるまいか。花を愛するあまり、いっきに詠み下したこの歌には、それなりの魅力はあるが、何となくロマンティックに流れた嫌いがあり、人を沈黙させるような美しさに欠ける」というのだ。「そのような評価(『生得の歌人』、『不可説の上手』)は一般世間に大きな波紋を及ぼし、西行物語や西行絵巻が次から次へ作られて行った。その殆んどが西行を仏教の聖者の如く祀りあげているのは、『ねがはくは』の歌によったのはいうまでもないが、当時としてはその方が通りがよかったし、今でも一般の人々はそう思っているようである。だが、西行の真価は、信じがたい程の精神力をもって、数奇を貫いたところにあり、時には虹のようにはかなく、風のように無常迅速な、人の世のさだめを歌ったことにあると私は思う」。著者による、西行の一種の偶像破壊は、十分成功していると言えるのではないか。