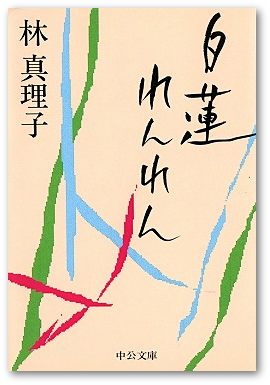柳原白蓮と宮崎龍介の往復書簡が語る白蓮事件の真実
柳原白蓮(やなぎわら・びゃくれん)と宮崎龍介の門外不出とされてきた700通に亘る恋文を目にした時、この幸運に作家・林真理子が身震いしたであろう姿が思い浮かぶ。『白蓮れんれん』(林真理子著、中公文庫)は、これらの書簡に基づき、白蓮(燁子<あきこ>)の内面を飾ることなく明らかにしている。この点だけでも一読の価値があるが、加えて、同時代の美しく貞淑な上流婦人として名高い九条武子の不倫が記されているのには驚いた。
燁子は、15歳で嫁がされた子爵家の北小路資武との最初の結婚に破れ、九州・筑豊の炭鉱王・伊藤伝右衛門と再婚する。大正天皇の従妹に当たる、華族で、美貌で鳴る26歳の燁子が、51歳の大金持ちに金で買われたと噂されたこの結婚は全国に知れ渡る。やがて、白蓮という雅号で短歌を発表し始めた燁子は、「筑紫の女王」と呼ばれるようになる。夫との満たされない生活を送る中、彼女作の戯曲を上演したいと申し入れてきた、7歳年下の東京帝国大生・宮崎龍介と愛し合うようになる。そして、遂に夫への離婚宣言を新聞に発表し、出奔してしまう。姦通罪が存在していた当時としては、これは命懸けの恋であった。
再婚当初の燁子は、新しい環境で自分の人生をリセットしようと頑張るが、好色な伝右衛門の家庭は人間関係が複雑で、苦労する。「希望の糧というのは、東洋英和での師、メアリー・シーガル先生が教えてくださった言葉だ。どんな不幸の中にも、見渡せば必ず幸福の種子は見出すことが出来る。そうだ、この家の中にも、自分が愛することの出来る存在はきっといるに違いない」。「この九州の地に嫁いで、自分がいちばん望んでいたのは『新規蒔き直し』という言葉だったのだ。今までの人生で得られなかったものをこの土地で手に入れたいと考えていたのだ」。
ところが、夫との関係はうまくいかない。「ところがどうしたことか、燁子の躰はぴったりと閉じられたままだ。長いこと夫に裏切られたことを燁子の心は許しても、燁子の躰はまだなじり続けている。夫の手が最後の紐を解こうとする時、燁子の目は固く閉じられ、一刻も早くそのことが過ぎないだろうかと息が止まる。すると必ず伝右衛門と関係した女たちの顔がうかぶのだ」。
親しさを増した龍介と燁子との間で倉田百三のことが話題に上る。「『倉田さんは、あなたととても親しくされていたと聞いていますけれど』。『ええ、あの方が療養のためにしばらく博多にいらしていたことがあったので、その時におつき合いをいただいていましたの』。燁子は倉田から貰った恋文めいた手紙を思い出した」。
龍介と燁子との会話の一節。「『(燁子作の)<指鬘外道>に出てくる男や女たちは、みんな肉の欲に負けてしまいますが、柳原さんはその心を怖しいと思ったのですか』。燁子は目を見張った。肉の欲という言葉をこれほど明るく口にする人間を見たことがないからだ」。
「4日後、早くも燁子は男(龍介)からの手紙を受け取った。燁子と小倉で別れ、夜行で大阪に着いた日に書かれたものらしい。・・・『小倉以后、私の頭には様々な幻が往来致しました。淋しげに見ゆるあなたの魂の傷、人間苦に悩むあなたの心臓の囁、疲労したようなあの體躯の歩み・・・。私はぼんやりし乍ら関門海峡を渡って了いました』。・・・燁子が考えあぐねている間に、また次の手紙が届いた。日付けは5日となっている。最初の手紙の次の日に書かれているのだ」。
「燁子はいま困惑と幸福を味わっている。といっても、その困惑は幸福と言いかえることが出来そうな、その幸福は困惑と紙一重であるような、極めて曖昧な気分の中にいる。ただひとつ確かなことは、男(龍介)からほとんど毎日のように届く手紙を待ちわびていることだ」。
「燁子は正直についこう漏らしてしまう。『貴方のお手紙にハともすれば私の魂を脅かすものがある。でなくてさえ微かなひびきにもおののきやすい私の魂を、どうぞもうこの上に脅かさないで下さいまし』。『本当にいつまでもいつまでも永久の春に別れ度くない。死ぬる日までも、貴方ハそうであろう。尼僧のやうに冷い私の胸にも、ふところに抱く冷い念珠にも、悲しや、人肌のやうなぬくみを持つ時がある。香のけぶりに身を包ませ、菩薩のみかほ拝む日も、この偽り者奴がと、自分の心ハ鳴りひびく。私は人世の春を怖れて居りまする。私ハそれハ、いやな人なんですよ』。これは燁子の敗北宣言というものであった」。
「『筑紫の女王 柳原白蓮』という連載読み物の威力は掲載地の大阪以外にも拡がっているらしい。おまけにあの商売上手な菊池寛が、白蓮をモデルにした『真珠夫人』という小説の連載を始めると大きく新聞で予告したばかりだ。燁子の知名度は、なまじの新人女優など遠くおよばないということをつくづく思い知らされる集まりであった」。
「いま龍介はとても苛立っている。そしてその原因がやわらかい絹ものに包まれた自分のこの肉体にあることを燁子は知っている。なぜならもう既に彼にそれを与えているからだ。罪の意識はまるでなかった。それよりも燁子を支配しているのは安らぎである。あの京都の宿で、若い男の情熱に身を任せた時、燁子が何よりも案じたのは35歳という自分の年齢である。年よりもはるかに若く見られ、美人の代名詞のようにいわれる自分であるが、脇腹や首のあたりに小波のようなかすかなたるみがある。小さな乳房も静かに垂れ始めている。だから最後の布は脱がずに胸は両の手で隠し続けた。それなのに目の前の男は、何とかもう一度それらのものに触れようと欲し、こうして渇えている」。
「すべてが燁子にとって初めての経験である。男のことをその肉体ごといとしいと思う。指先のひとつひとつ、額のおくれ毛一筋も記憶に刻み、その先の行為をため息と共に思い出す。思い出せば思い出すほど、その肉体と精神を持つ男に所有されたいと思い、その男を所有したいと激しく願う」。
「龍介を愛してもうひとつ知ったことがある。それは夫というもうひとりの男に抱かれなければならない苦痛である。自分の恋を喋ることの出来ない苦痛は、中でじれて甘い。けれども夫に肌を触れられることの嫌悪は本当に痛みさえ伴うのだ」。こういう機微を表現する林の筆力はさすがである。
「二人は憑かれたように手紙を書く。特に昨年の暮れ、龍介の子どもを中絶した燁子は、情熱と時間のありったけを込め、毎日のように恋文をしたためる」。
暫く会えなかった時期の、燁子から龍介への手紙。「好きな好きな手紙を下さい。見度い見度い。わたしの人。恋しうて 淋しうて なつかしうて 悲しうて どうしたらよいやら」。
「龍介はそんな恋人をいとおしくてたまらぬように抱き締め、今日何度めかの帯をとく。燁子の夏帯は締めても締めても、彼によってすぐに性急にほどかれるのである。その激しさは病気(龍介の結核)ゆえなのかと燁子は男の背に手をまわす」。「それなのに何の防具もつけず、二人は何度も愛し合ったのだ。もしかすると自分は無意識のうちに、もう一度孕むことを望んでいたのではないか。崖の上で背中を押してくれる大きな手をつくろうとしていたのだ」。
大阪朝日新聞に掲載された伝右衛門への絶縁状の内幕も記されている。「(電話で)『燁さん、昨日、手紙を送った。赤松(龍介の親友)が書いたI(伊藤)氏への絶縁状が、中に入っているから読んでくれたまえ』。『えっ、私が書いたものじゃいけないの』。・・・『私はいま貴方の妻として最後の手紙を差し上げます。いま私から手紙を差上げるといふことは、貴方にとつて突然であるかも知れませんが、私としては当然の結果に外ならないので御座ゐます。貴方と私との結婚当初から今日までを回顧して私はいま最善の理性と勇気との命ずる処に従つてこの道を取るに至つたので御座います。ご承知の通り結婚当初から貴方と私との間には全く愛と理解とを欠いていました。この因襲的結婚に私が屈従したのは、私の周囲の結婚に対する無理解と、そして私の弱小の結果でござゐました。然し私は愚かにもこの結婚を有意義ならしめ、出来得る限り愛と力とをこの中に見出して行きたいと期待し且努力しやうと決心しました。・・・』」。
伝右衛門に問題があるのは確かとしても、彼を見直したくなるエピソードも紹介されている。「それは伊藤家育英資金のことを言っているのである。このあたりの秀才で、帝大や商大、早稲田に通う学生たちに伝右衛門は奨学金を出していた。それは篤志家としての彼の義務感に、多少の学歴コンプレックスが加味されたものなのである」。伝右衛門の年の離れた異母妹・初枝の言葉――「世間の人が面白がっていろんなことを言うけれど、兄さんは義太夫の本はちゃんとお読みになる。書類だってちゃんと目をとおされるわ。確かに学はおありにならないかもしれないけれど、頭のいいちゃんとした人です」。
新聞に載った絶縁状に怒った鉱山(ヤマ)の荒くれ男たちが、「『俺たち昨日から寄り集まって相談したが、これはひとつ俺たちに任せてつかわさい。あの淫売女、ただじゃおかねえ。あの生っちょろい間男と二つに重ねてたたき切って見せますばい』。・・・『馬鹿もん、何を考えちょる。いったんは俺の女房で、お前らも奥さん、姐さんと呼んじょった女じゃなかか。その女に手出ししょうちゅうは何ごとか。いいか、もし何かお前らがしたらな、目ん玉くり抜いて切り刻んでやるぞ。わかったか』。とても60過ぎの老人とは思えないほど張りのある声には、かつて鉱山で荒くれ男たちと共に立ち働いていた伝右衛門の姿があった」。伝右衛門は、燁子の求める離婚届けに間を置かずに判を押し、姦通罪を言い立てることもなかったのである。
「大正10年10月20日、燁子は家を出て、恋人宮崎龍介のもとへ走った。これが世に名高い『白蓮事件』である」。
「燁子はそれから長い歳月を夫と子どもたちと生きた。・・・心臓の病いで床についた燁子を、龍介は自らの手で看病した。82歳の老いた妻にいとおしげに語りかけ、自室に寝かせて他の誰にも触れさせなかった。下の世話も75歳の龍介が心を込めて行なった。燁子が亡くなった時、彼は新聞のインタビューに答え、『うちに来てからは幸せな人生でした』ときっぱりと言った」。
以上、年齢は全て数え年で表現している。
愛することの難しさ、恋することの素晴らしさを考えさせられる達意の伝記小説である。