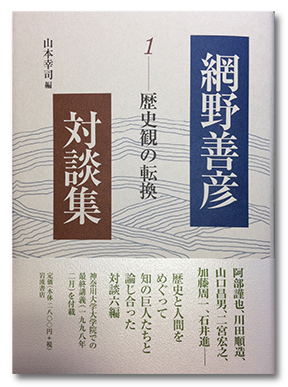70年代の歴史学界の熱い息吹が懐かしい。アナールも歴史人類学も「無縁・苦界・楽」も。
余りに多忙で、政治的運動に出るために乗る電車の中でしか、読書の時間がなくなってしまった。それでも、めげるわけにはいかない。そして読んだ網野善彦対談集。内容はほぼ70年代に知り得た知識が溢れるようにポンポンと飛び出すことで、あの懐かしく、熱い政治の季節とそれと連動した歴史学の大転換の時期を追体験することになった。対談者として挙げられている方々が、石井進氏を除いて、みな故人となられている事も当然ではあるとはいえ、火花を散らすように競い合って出されたあれこれの書物が今や古典となる時代になっている事を感慨深く思い起こしたのである。
対談相手は阿部謹也(中世に生きる人々)、川田順造(歴史と空間の中の人間)、山口昌男(歴史の想像力)、二宮宏之(歴史叙述と方法―歴史学の新しい可能性をめぐって)、加藤周一(世界史の転換と歴史の読み直しー21世紀への課題)、石井進(新しい歴史像への挑戦)。今さら紹介する必要もないが、阿部謹也氏は西洋中世史ドイツ史専門で、「ハメルンの笛吹き」ですい星のように登場した。その後は「中世を旅する人々」や西洋の被差別民を扱った書籍などで、網野善彦氏とは日本史と西洋史をお互いに横断するような仕事をされた。晩年は日本史の「世間とは何か」と言う本を出されたと記憶している。私は、阿部謹也先生とは私的にもお付き合いがあり、先生が劇作家の秋元松代さんと御近所だとかで、当時爆発的に有名になっていた太地喜和子と平幹二郎の「近松心中物語」の本読みにこっそり入り込ませてもらったり、劇中歌の森進一の「それは恋」の未発表テープのコピーをいただいたりした。当時私が勤務していた職場で私がひどく虐げられていたのをご覧になり、わざわざ、励ましていただいたのだと思う。川田順三はアフリカの無文字文化の研究で著名であった人類学者である。山口昌男はこれは今更いうまでもない知の巨人。二宮宏之はあまり知られていないがアナールの日本への紹介者で、フランスの方では有名人で、亡くなられた時、日本では社会面の下の物故者の欄に出ただけであるが、フランスの一般紙の一面を使って業績が紹介されたそうである。加藤周一は戦前からの有名な評論家で、学識豊かな評論活動が今では貴重な文化人であった。石井進は網野善彦とはほぼ同時期に東京大学で学んだ日本中世の専門家で、派手ではないが、堅実な研究成果を残している。
この書籍は論文集でも一般書でもなく対談集であるところにとても深い意味がある。対談者が変わっても何度も中心的な概念が表明されると言う点で、非常に学べる点が多いということである。網野善彦がこだわった点、それはやはり日本という国が特殊な国家ではなく、さらに天皇を戴くことの歴史的な分析なくしては世界の中で、われわれが生きて行く姿勢を示せないであろうということである。特に戦前から日本は古代から農業を主体とした国家が形成されていたという点への根元的な批判である。考えて見れば当然であり、日本は周囲が海に囲まれた島国である。また山国でもある。文献に現れた姿が農業を中心に表現されていると言う事は、農業者は土地から離れることができないために権力者に把握されることが可能になりやすいだけである。しかし、海、山の民は遊牧する。彼らを把握することは非常に難しいと言う点で、国の支配からは離脱している存在である。しかし、この遊牧する民は、中央権力からすればまつろわぬ民であり、後世に至れば差別される存在と変わる。
今回、対談集を読みながら再度考え直した大きな点は山野草木は「無所有」と言う概念についてである。即ち、農業の土地は所有の概念が早くから生じる。勿論それも、私所有と言うわけではないが、古代国家であったり荘園領主であったり、武家の領土となったりするが、おしなべて所有の概念である。しかし、そこから外れた「無所有」という非常に重要なキーワードを忘れていないかということである。なぜ今、私がこれに強く反応したかと言うのは、原発問題と沖縄の返野古の問題について考えることが多いからである。原発のような自然との共存が出来ない代物を建てるという事は、単に土地所有者が国に売り渡せば建築できてしまう。また返野古の海はさらに国は地元の意志を無視してアメリカのために基地を建造しようとしている。これはおかしいのではないか。山野草木は「無所有」なのである。そこにあるのはそこに住む人々が生活のために必要な恵みを共同で使用する場なのである。すべての民に開かれたものなのである。それが古来日本の自然との穏やかな営みを支えてきた思想であった。「公」と言う概念が今や逆転してしまったのではないかとも思った。「公」とは万民にとっての権利であるはずが、今や「公」とは私の上位に位置し、それに従わされるものを言うようになっている。例えば加藤周一氏はこういっている。「スイスの統一原理は政治的概念である市民権ですからね。市民的権利だから、日本とは違うわけだ。
一番極端な例は、小さな村で、カントンという小さな地方で、連邦政府が、軍事演習をする。地方の村長か何かに許可を求める。村長が拒否すると連邦政府のほうが退く、軍事演習をしない。そのくらい地方が強い。・・・連邦政府には法的に強制権がない」。これに対して網野氏は本来日本も村や町の自治能力は相当に高かった。「江戸時代においても、上からくるものに対して村と町の抵抗力は相当にあると思います。」と応じている。すなわち、現在のように地方の自治を国が制限するような支配のやり方は健全ではないと言うことにはならないか。
もう一つ、網野氏が70年代にこの自然と人間の関係の変化に危機を感じて発言しておられたことがまさに今原発と辺野古の海でみられるということである。網野氏はこう発言している。
「自然と人間の関係が決定的に変わってきている、人間の社会全体が転換期に入りつつあることから、それは起こってきていると思うんです。今までは人間が自然のごく一部に姿を表して、その後しだいに自然を開発して、確固とした力で自然を征服していく過程、自然との戦いに人間が勝利していく過程そのものに人間の社会の明るい未来を夢想してきた時代であった。開発をして、いろいろな力を獲得していけばいくほど世の中は良くなると考えていた時代、客観的に見てその時代は終わりをつげたと思います。人類が原子力・原始爆弾を含めて自分を滅ぼしうる道を自分で見つけ出してしまった、一歩誤ると人類は頓死する危機すらあると思うんです。ですから、長期的に考えて、人間自身が荒廃させてしまった自然と、どう調和を保ちながらこれから生きていくかという課題を、否応無しに人類全体が背負わざるをえなくなってきたという実情があるのではないか。」と。
70年代に原発が自然との問題であると書かれていたことに愕然とした。福島事故が起こるまで、私たちはただ漫然と経済の成長だけしか考えてこなかった。歴史学者がこのように社会の転機にあるべき姿を提示していたことにきづかなかった。いまや手遅れかもしれないが、せめて出来る限り、私たちは自然との共存を求めて社会の認識を変える努力を努めなければならない。
この対談集は歴史学者の対談集である。しかし、歴史学とはただ過去の事物を明らかにするだけが使命ではない。固定観念を打破して、よりよい生のあり方を見つけ出し、その正当性を求める役割も求められると思う。さらに、網野が指摘している近代史学について、マルクス主義だけではなく、近代の歴史学の根本に、人類の進歩と言う基本概念があったが、今やそれは成り立たない。この認識に立って、歴史学は何をなすべきかと言う指摘もなされている。今現在、歴史学の本が時代を牽引するようなものが出てきていないことはなぜなのだろうかと思う。多分網野が当時から危惧していた様に、研究の細分化により、大きな枠組みで歴史を観る視線が若い研究者に育っていないのか、または研究の成果主義に追われて、じっくり研究をする環境にないのか、いや私には、歴史研究者が民衆と言う存在から離れすぎたことに原因があるのではないだろうかと思う。下へ下へ、底へ底へと降りて来た時、そこには豊かな人間性と文字とは別の声の文化をもった人々がいて、進歩とは別の概念で生きるすべに長け、決して政治的な圧力に屈しないたおやかな精神をもった人々がいる。その人たちこそ真の歴史を担っている。そこへ降りて来て欲しい。研究者よ街にでよう。
魔女:加藤恵子