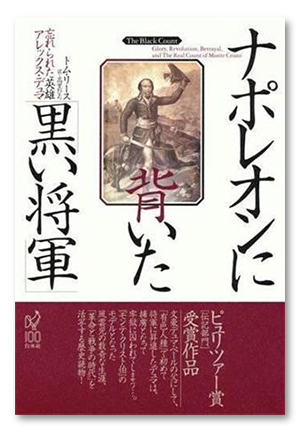『モンテ・クリスト伯』の主人公のモデルは、デュマの実の父親だった
「モンテ・クリスト伯」という活字を目にすると、30年前の夏休みの4日間、夢中になって『モンテ・クリスト伯』(アレクサンドル・デュマ著、山内義雄訳、岩波文庫、全7冊)を読み耽ったことを思い出す。
この血沸き肉躍る『モンテ・クリスト伯』の主人公、エドモン・ダンテスの人物造形に大きな影響を与えた実在の人間がいたというのだ。アレクサンドル・デュマの父、アレクサンドル(アレックス)・デュマが、その人だったのである。『『ナポレオンに背いた「黒い将軍」――忘れられた英雄アレックス・デュマ』(トム・リース著、高里ひろ訳、白水社)は、歴史の闇に埋もれていたアレックス・デュマの数奇な生涯を掘り起こした躍動感溢れる書である。
黒人(父は白人貴族、母は黒人奴隷)でありながら、フランス革命期に、革命軍に一兵卒として入隊後、その実力によって将軍にまで昇進したアレックスは、勇猛果敢な戦いぶりで大きな戦果を上げ続ける。しかし、敵軍の捕虜となり、長期間、牢獄に囚われてしまう。その後、解放されるが、彼の前に大きな壁が立ち塞がる。それこそ、当初はアレックスより階級が下であったが、やがてアレックスと同格の将軍になり、その後、あれよあれよという間に力を付け、遂にアレックスの上位に立ったナポレオン・ボナパルトであった。ナポレオンがまだ大尉だった頃、アレックスは既に将軍の地位にあったのであるが。秘かに独裁を目指すナポレオンと、フランス革命の精神「自由・平等・友愛」を守り抜こうとするアレックスとでは、その関係が平穏であるわけにはいかないだろう。さらに、世界で一番早く奴隷解放を実現したフランスの、実質的な奴隷制復活への揺り戻しがアレックスを苦しめる。
アレックスは1762年、砂糖を生産するフランスの植民地サン・ドマング(現在のハイチ)で生まれた。父は家族や司法から隠れて暮らす訳ありのフランス貴族(侯爵)で、母は彼が所有する美しい黒人女奴隷であった。
「アレックス・デュマはすばらしい戦士であり、気高い信念と道徳的勇気のもち主だった。その強靭な肉体、剣士としての腕前、勇敢な行為、きわめて困難な状況でも勝利をつかむ手腕で知られていた。だが同時に、その不遜な物言いと目上との揉め事でも有名だった。彼は兵士たちの将軍だった。敵に恐れられ、味方に愛され、軽々しく英雄という言葉を使わぬ世界で英雄と称された。だが彼は陰謀によって砦に監禁され、見えない敵に毒を盛られ、抗議の機会さえないまま世界から忘れ去られた。彼の運命が、若い船乗りエドモン・ダンテスのそれを思わせるのはけっして偶然ではない」。
「アレックス・デュマは出世しても、部下に危険な仕事を命じて、自分は安全な後方に留まるようなことはしなかった」。
「ふたり(アレックスとナポレオン)がまだフランス革命軍の将軍であったとき、ナポレオンはアレックス・デュマの働きを、テヴェレ川を渡ってローマ共和国に侵入しようとした異邦人を撃退した古代の英雄、ホラーティウス・コクレスの生まれ変わりのようだと、当時好まれた古典的な言葉で称賛した。ナポレオンがエジプト遠征に出発したとき、デュマは騎兵隊の司令官として同行したが、彼の地において、まったく異なるふたりは互いを嫌悪するようになった。対立は思想的なもの――デュマはみずからを世界を解放する戦士であり、世界を支配する戦士ではないと考えていた――だが、個人的なものもあった。『ボナパルト将軍を目にしたあらゆる階層のイスラム教徒たちは、彼の背が低く痩身であることに驚いた』。遠征の軍医長はそう書きのこした。『わが軍の将軍のうち、その見た目で彼らを感心させたのは・・・騎馬部隊を率いるデュマ将軍だった。有色人種で、まるでケンタウルスのような体格の彼が騎馬で塹壕をまたぎ、身代金と引換えに捕虜をとり戻しにくるのを見て、全員、彼がこの遠征軍司令官だと思った』」。
「身長は180センチメートル以上、筋骨たくましいからだつきの(アレックス・)デュマは、フランスの上流階級で人目をひいた。だがフランスの国富の基盤が植民地の黒人奴隷制度であった時代に、彼はどのようにして上流階級に入り――そのうえ国の英雄として褒め称えられることになったのだろうか?」。この設問に対する著者の飽くなき探求が、本書の前半のテーマとなっている。
「31歳になった(アレックス・)デュマは将軍に昇格し、ともに戦った士官や兵士らみんなの称賛を集めていた」。
「侯爵と奴隷の息子として生まれた(アレックス・)デュマは、最高の階層と最低の階層、どちらの出身でもある独特な立場だった。真に理想家であった彼は、自分の理想の形勢が悪くなっても、信じることをやめなかった。2年間にわたり敵の砦にとらわれたみじめな監禁生活――ようやく解放されても、自分の国で味方に裏切られるという、さらに屈辱的な状況に陥ったこと――は、平等と友愛の理想が、とりわけフランスの有色人種にとって、どう変わってしまうのかを予告するものだった」。
「彼(作家のデュマ)の(まだ兵卒に過ぎなかった)父親は、有力なブルジョア出身の白人女性マリー・ルイーズ・ラブレとおとぎ話のような恋愛をした。革命勃発直後の数カ月、彼が彼女の住む町を守るために派遣されてふたりは出会い、恋に落ちた」。やがて、二人は結婚し、子供を3人儲けるが、その末っ子が後に作家になったデュマである。従って、デュマは4分の1黒人のクウォーターなのである。
「わたし(著者)がまもなく見覚えてしまったアレックス・デュマのみごとな筆跡による手紙には、しばしば驚くほど率直な言葉で、未来への希望、軍への不満、彼がそのために戦っている理想へのかたい思いが語られている」。
「1794年1月から2月にかけて(アレックス・)デュマが書いた、数百ページにおよぶ報告書、覚書、命令書から、生まれつきの戦士であった彼に兵站と立案の才能もあったことがわかる」。
アレックスは上司である総司令官・ナポレオンと衝突するのを避けようと努力するが、考え方が正反対の両者の溝は深まっていく。「(アレックス・)デュマはふたりの関係の最初から、ナポレオンが特別な尊敬を期待していることを理解しなかった。ナポレオンは腹を立てていたはずだが、実利主義者だった彼は、デュマ将軍が自分にどう役立つか判断するまで目を光らせておくことにした。イタリア征服の過程で、デュマが大いに役に立つとわかり、ナポレオンはその腹立たしい態度と厄介な平等主義に目をつぶることにした――ある程度までは」。「(他の)将軍たちがボナパルト将軍をもてはやすのが気になっていた。・・・(アレックス・)デュマから見ると、『イタリアの男たち(イタリア方面軍の将軍たちの自称)』が話すのはおもに自分たちとすばらしい総司令官のことで、共和国の目標や価値観についてはほとんど話しもしない。デュマにとって『ラ・マルセイエーズ』は、ただの軍歌ではなかった。彼の心に深く刻みこまれていた」。
「『未来とは、なんと暗く無惨な秘密を隠していることか』。アレクサンドル・デュマはのちに、父の運命に思いを馳せ、回想録にそう記すことになる。・・・1801年6月にアレックス・デュマがフランスに戻ったとき、革命も、彼が愛した国も、彼自身と同じくらい変貌していた」。「ようやく城塞の牢獄から解放されたというのに、(アレックス・)デュマの祖国はそれと似たような場所に変わっていたのだ。にわかには信じがたい地位剥奪によって、彼は自分の国で危険にさらされていた。(ナポレオン)政府は有色人のフランス国民の権利を徐々に制限し、縮小し、最終的に剥奪した」。「黒人の将軍や黒人の司令官は考えられなくなった」のである。
「1802年7月24日、マリー・ルイーズは3人目で最後の子を生んだ。アレックス・デュマは人生最後の4年間を、この幼いアレクサンドル・デュマから片時も離れずに過ごした。だが、息子の誕生の喜びの最中にも、デュマ将軍は地位が格下げになったことを忘れられなかった」。
1805年、アレックスの体調が急に悪化し、腹痛はがんと診断された。そして、1806年2月26日に死去、享年43。
アレクサンドル・デュマは、生涯、父を崇拝し、深い愛情を抱き続けたのである。私は、本書によってアレックス・デュマという人物を初めて知ったのだが、理想に情熱を燃やし続けたアレックスが同志のように思われてならない。この本に出会えた幸運に感謝している。