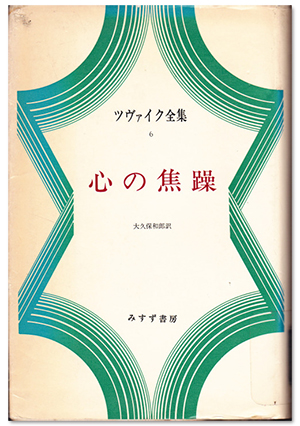同情と愛情を取り違えた令嬢と将校の悲劇の物語
シュテファン・ツヴァイクの『ジョゼフ・フーシェ』(シュテファン・ツヴァイク著、高橋禎二訳、岩波文庫)などの評伝的な作品は何度も読み返しているが、彼の手になる完全なフィクションも読んでみたくなり、長篇小説『心の焦躁』
(シュテファン・ツヴァイク著、大久保和郎訳、みすず書房。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)を手にした。
ウィーンに程近い衛戍地に滞在するオーストリア陸軍の少尉で25歳の「私」は、土地一番の富豪の晩餐会に招かれ、続く舞踏会で、この家の一人娘にダンスを申し込む。「私は舞踏に誘うしるしとして丁寧に頭をさげた。訝しそうな眼が唖然としたようにまじまじと私の上に注がれた。口は物を言いかけて半ば開かれたままだったが、彼女は私に応じようとする動作は全然しない。今のがわからなかったのだろうか? それで私はもう一度頭をさげた。それとともに私の拍車はかすかに響をたてた。『お願いできませんでしょうか』と私は言った。しかしそれに続いて起ったことは見るもおそろしいことだった」。
その17〜18歳のエーディトという娘は両足が麻痺していて、松葉杖がなければ二歩と歩けない障碍者だったのである。漸くそのことに気づいた私は、自分の無分別な行いを恥じ、深く落ち込んでしまう。翌朝、お詫びの気持ちを伝えようと、薔薇の花束を贈り届ける。「従卒は手紙を手に持っていた。青いイギリスの紙でやわらかい香水の匂がうつり、裏には紋章が品よく捺された長方形の封筒、硬く線の細い筆蹟、たしかに女手の手紙だった。私はせきこんで封筒を引裂き、なかを読んだ。『私には勿体ないほどの綺麗なお花をいただきまして心からお礼申上げます。あれを見たとき私は大変嬉しく、今もほんとに喜んでおります。どうぞ御都合のよろしい日の午後私どものところへお茶においでくださいませ。わざわざお知らせくださるにはおよびません。私は――残念なことですけど!――いつも家におりますから。エーディト・v・K・』」。
これがきっかけとなり、私は毎日、彼女の家を訪問するようになる。そして、ある日、彼女から「おやすみのキス」をねだられる。「私はできるだけ素速くからだをかがめて軽くあわただしく唇で彼女の額を掠った。わざと私は彼女の肌にほとんど触れぬようにし、そしてただ真近から彼女の髪のさだからぬ匂を嗅いだだけだった。だがそのとき彼女の両手は、明かにこれを待構えて掛布団の上に置かれていたのであろうが、やにわにさっと上った。私がからだをそむけるひまもあらばこそ、その手は締金のように両側から私の顳顬を抱締め、額から自分の唇へむかって私の唇を押下げた。歯と歯が触れあうほど熱烈に、吸いこむように、そして貪婪に、二つの唇は押しつけられ、そしてそれと同時に、下へかがんだ私のからだに触れ、私のからだを感じようとして、彼女の胸は反りかえり、迫るように擡げられた。生れてから私はこの不具の子供から受けたようなこれほど狂暴な、これほど絶望的な、これほど渇望的な口づけを受けたことは一度もなかった」。
「この病人が、この廃疾の娘が恋をすることができ、そして人から愛されることを欲するという、この一事は私は予期しなかった。この子供が、このまだ一人前になっていない娘が、この未完成なしかも無力な女が、成熟した女の持つ何もかもわきまえた肉体的な愛情をもって恋愛し欲情するという大それた真似を敢てする(としか私には言えないのだ)ということは、私は予期しなかった。・・・粗忽者の私は、自分の迂濶な不感症のためまったくお話にならないほど単純であったため、彼女のなかに女性を見ずにただ悩めるものを、麻痺患者を、子供をのみ見ていたのだ。一瞬たりとも、しかも本当に瞬きするあいだだけでも、このおもてを包みかくす毛布の下に赤裸の肉体が、ほかのすべての肉体と同じように渇望しかつ他から渇望されることを望んでいる女性の肉体が、息づき感覚し、期待しているということを思い浮かべたことは、私にはなかった」。
「自分が一人の男に持っている好意を一度さらけ出してしまった女と、その男とのあいだには、熱した、不思議な、危険な空気がうちふるえているものなのだ。愛している人たちには常に、愛されている方の人間の感情の真偽を見分ける無気味なまでの洞察力がそなわっている。そして愛情というものはその最も内奥の本質によってあらゆる場合に無際限なものを欲するから、あらゆる適度なもの、中庸を得たものはすべて愛情には厭わしく、堪えがたいものとならざるを得ないのだ。相手が何かにこだわりまた抑制されていると、必ず愛情はそこに抵抗を感じ、相手が完全に自分を委ね切らない場合には当然のことながら必ずそこに秘められた反抗を感じ取る」。
「私は、自分の弱さによって、はじめは相手を誘きよせるような、だが後には逃避的な同情によって、一人の人間を、しかも情熱的に私を愛してくれたただ一人の人間を(間接的に)殺害してしまったということを、このときまざまざと思い知らされていたからである」。
本書は、3つの重要なことを私たちに気づかせてくれる。第1は、男女を問わず、また、自分がハンディキャップを抱えているか否かに拘わらず、人を愛してしまったら、その相手からも同じように愛されたいと激しく欲し、悩むということ。第2は、恋している人間は、相手の態度はもちろん、心の動きも敏感に察知するということ。だから、叶わぬ恋は辛いのだ。第3は、同情と愛情を取り違えることは、相手にとっても自分にとっても不幸を招くということ。愛情か同情か判断に迷ったときは、相手を心身共に受け容れられるケースは愛情、そうでないケースは同情という基準に照らしてみるというのはいかがだろうか。
人を愛すること、そして、人から愛されることは本当に難しいということを、本書によって再認識させられたのである。
本書の訳語にいささか穏当を欠く表現が散見されるが、41年前の出版であることを考慮に入れるならば、已むを得ないと考えている。