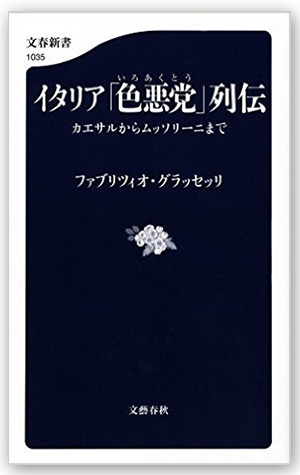ロドリゴ・ボルジアとジャコモ・カサノヴァが身近に甦ってきた
『イタリア「色悪党(いろあくとう)」列伝――カエサルからムッソリーニまで』(ファブリツィオ・グラッセッリ著、文春新書)を読み進めていくと、自分が歴史上の人物の身近にいるかのような錯覚を覚えてしまう。
英雄色を好むという言葉を実践したイタリア人――ユリウス・カエサル、ロドリゴ・ボルジア、レオナルド・ダ・ヴィンチ、カラヴァッジョ、ジャコモ・カサノヴァ、ジャコモ・プッチーニ、ベニート・ムッソリーニ――の生き方が、彼らの側近く仕えた人物の目を通して描かれる。この語り手たちは架空の人物であるが、歴史学の最新の研究成果が取り入れられているので、史実に限りなく近いと考えていいだろう。
取り上げられているいずれの人物も生き生きと浮かび上がってくるが、とりわけ私を魅了したのは、ロドリゴ・ボルジアとジャコモ・カサノヴァの二人である。
私の好きな人物、チェーザレ・ボルジアの父、ロドリゴ・ボルジアについて書かれたものは少ないので、舐めるように読んでしまった。
ロドリゴ・ボルジア、すなわち法王アレッサンドロ6世の章は、「ローマ法王の犯した禁忌の愛欲」という副題が添えられ、侍従長が語り手となっている。
「酒と女に溺れずにいられない事情が様々あることはお察しするが、侍従長という立場からすると、まことに手のかかる、困った方だと言わざるを得ない」。
「この時代、ローマ法王は、単なる聖職者ではなく、優秀な政治家でもなければならないことは、誰でもわかっていることだ。この点において、この方はまさに完璧な人物だった。まるでチェスの達人のように――今のヨーロッパは、彼にとってはまさしくチェス盤のようなものだった――彼はヨーロッパ政治に関わるあらゆる動きに神経を集中して、様々な政策の実行や人事、外交案件を見事にさばいていった。法王様の『チェス』の相手は、フランス王シャルル8世であり、ミラノ大公アスカニオ・スフォルツァであり、フィレンツェの君主である、ロレンツォ・デ・メディチだった――この男は、法王様にとっては幸運なことに、昨年死んだのだが――。そうしたときには、アレッサンドロ6世、すなわちロドリゴ・ボルジア様は、決して理性を失うことなく、常に冷静に振舞うことができた。ところが昨夜のような場面、エロスとの戦いにおいてはいつも、常軌を逸していると言いたくなるほどの乱れようを見せるのだった」。法王は、昨夜、全員の歳を全部足しても、自分の歳に届かないような若い女たちを、ベッドで3人まとめて相手にしていたのである。
「アレッサンドロ6世は、キリスト教徒の『魂の父』になる気など、もとから全くないお方だ。・・・そしてすべての優秀な為政者がそうであるように、法皇様も、その業務に忠実なお人だ、すなわち、その権力をより強化するとともに、その国土を――この場合は法王領、つまり『神の領土』を拡げることに全力を注いだ。正当なものも、悪辣なものも含めて、あらゆる手段をもってだ。そして、過去から現在に至るまで、ほぼすべての、王や王子、宰相がそうであったのと同じように、身の回りを美しいものや、美しい女たちで埋め尽くすことに熱心だった」。
「ただ一つ、今これを読んでいる人に知っておいてもらいたいことがある。それは、法王アレッサンドロ6世が、ローマ市民から愛されているということだ。法皇様はスペインの出身だ。そして、普通ローマ人はスペイン人を好まない。しかし、法皇様だけは別だった」。それはなぜか。この法王が、ローマと法王領に暮らす大衆が日々の食事に困らないことを保障するような政治を行ったからだ。
いよいよ、私の好きなチェーザレ・ボルジアが登場する。「25歳になられたチェーザレ様は、鮮やかな金色の髪をして、髭はきれいに手入れされており、上背は高く、体つきは一層たくましくなられた。そのいでたちも、いつもながらエレガントそのものだった」。チェーザレは、父親の代理として、軍事面で目覚ましい活躍をしていたのである。
チェーザレの美しい妹・ルクレツィアも登場する。「既に公式発表されたところによると、ルクレツィア様は、ヘェラーラ、モデナ、レッジョ・エミリアの領主である、北イタリアの有力者、アルフォンソ・デステ公爵と、21歳にして3度目の結婚をされることになっている。当然ながらこの結婚はこれまでと同じく、法皇様の政略のためのものだ。だが今回は、失敗に終わったこれまでの2回とは違って入念に計画されたものであり、今度こそはすべてがうまく行きそうだった。この方法なら、兄上のチェーザレ様が軍隊を率いて、かの地を征服するために出陣し、危険をおかす必要もない。この結婚はいわば、ベッドの上という『もうひとつの戦場』で行われる、エステ家との、血を流すことのない戦争なのだ」。女たちは、ベッドの上で実家のために頑張ったのである。
そして、遂に、私の好きな、もう一人の人物、ニッコロ・マキャベリが姿を現す。マキャベリが故国・フィレンツェの政府要人に書き送った内密の手紙が、スパイを使ってこれを盗み取った枢機卿によって法王の前で読み上げられる。その中で、マキャベリは、「アレッサンドロ6世の政治は、その息子である、ヴァレンティーノ公・チェーザレの軍事行動によって支えられている。そしてその作戦は我々の予想を超えて、大きな成果を挙げてきた。フィレンツェの君主は、今やイタリア半島が、大きな二つの部分に分割されつつあることを知るべきである」と、警鐘を鳴らしている。これに対し、法王は吐き捨てるようにこう言う。「私は、西ローマ帝国の滅亡以来、誰も果たし得なかった壮大な夢を、この手で実現させようとしているのだ! あのマキャベリとかいう、いけすかないフィレンツェ人は、まことに賢明なお方だな! 私の考えを全部ご存じのようだ! 今こそ、このイタリアを統一して、強力な国家を作らなければならないのだ。世俗の国家であり、同時に教会という霊的な権威のもとに治められる国家をだ! 私は何も、自分の権力欲だけでそんなことを考えているわけではないぞ! そうしなければ、イタリアの地は、周辺の強国に蹂躙されてしまうだろう」。マキャベリが『君主論』の中で、チェーザレを理想的な君主と評価していることは、よく知られているとおりだ。
ジャコモ・カサノヴァの章の副題は「華麗なる夜の外交官」となっており、彼の若き秘書が語り手を務めている。
「そこに待っていたのは、まだ20歳を少し過ぎたぐらいの、若い青年だった。前もって聞いていた話では、パドヴァ大学の法学部を卒業した秀才だということだったので、私は、黒い服を着て、分厚い本を抱え、眼鏡でもかけたような人物を想像していた。ところが、目の前に現れたのは、流行の最先端を行く服を優雅に着こなし、香水の香りを漂わせた、エレガントな若者だった。分厚い本を抱えているはずの手には、いかにも高価な、銀と象牙で出来た柄の付いた、杖を持っていた」。
「(カサノヴァの)特質は、決して下品なものでも、攻撃的なものでもなかった。むしろ、ジャコモ様の礼儀正しさや、人に対する優しさと寛大さ、深い教養といったものが、多くの女性を惹きつけているのだと思えた」。
カサノヴァが、秘書にこう言う。「いいかいマルコ、愛することの自由というのは、人間存在そのものの自由とつながっているんだ。男でも女でも、本当に自由で教養のある人間は、ばかばかしい世間のモラルなど乗り越えて行かねばならない。そして生きることの喜びを、自ら表現しなければならないんだ。これは肉体の問題ではない。その人間の、精神の在り方が問われているのだよ」。カサノヴァは、文字どおりの自由人だったのだ。
「彼の女性の好みには、年齢など関係なかった。少女からほとんど老婆と言って良い女性まで、そして大富豪や有名貴族の妻から農婦まで、あらゆる女を彼は愛した。彼は女というものを、自身の命と同じぐらい、いやそれ以上に愛していた」。
私は若い時からカサノヴァに興味を持ち、『カザノヴァ回想録』(ジャコモ・カザノヴァ著、窪田般弥訳、河出文庫、全12巻。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)などを繙いてきたので、彼の華やかな女性遍歴にはそれほど驚かないが、彼が一流の教養人だったという本書の指摘には、目から鱗が落ちた。
「世には、ジャコモ様のことをペテン師扱いする者もいたが、彼の高い教養と広範な知識は、どこへ出しても恥ずかしくない一級品だった」。「私にとって驚きだったのは、そうした恋愛沙汰の合間に、ジャコモ様がオペラの台本を書き上げたり、フランス中の文学者や文化人と会って、語り合う時間を作っていたことだった。彼は、当時百科事典の執筆をしていたアレンベルトという人物とも親しく付きあい、彼と一緒に世界の森羅万象、すべてを書き尽くしたいとも語っていた」。
もう一つ、魂消たことがある。カサノヴァは、当時の巨大な権力集団の代表者たるフランスの駐ヴェネツィア大使の愛人(しかも、この女はヴェネツィアの名門出身の修道女だった)と関係を持ったことを咎められて、獄に繋がれてしまう。1年後にカサノヴァは脱獄を果たすのだが、これが実は彼をスパイに仕立て上げるための政治的陰謀だったというのだから、驚くではないか。ヴェネツィア共和国政府の要職にあるマルコ・バルバロの言葉はこうだ、「何しろ彼は、ヨーロッパ中のどこの宮廷にも出入りが出来る。しかもそれぞれ国の重殖に就いている、多くの人間と友人関係を結んでいて・・・そしてもしかするとこれが一番重要な点なのかもしれないが、ヨーロッパのほとんどすべての国に、宮廷の事情通である貴婦人や、有力者の妻であるところの、愛人がいる。彼女たちとの寝物語に、どんな貴重な情報が出て来るかわからん」。「彼を単に釈放してしまったら、この仕事は任せられない。しかし彼が共和国政府を裏切って鉛の牢獄から脱獄したのであれば、誰も彼を、我々の手先だと疑いはしない。逆に、我が国の機密事項を彼から聞き出そうとするだろう。彼には偽りの国家機密をたくさん流してもらう。そうだ。鉛の牢獄から脱獄できた唯一の人間として、その冒険談を本にしてもらうと良いかもしれない。きっと評判になって、多くの宮廷人や有力者が、もっと詳しい話を聞かせてくれと申し出てくれるだろう。もはや彼が我々のスパイであると疑う者はいない」。
「(ロレンツォ・)ダ・ポンテは、1784年の冬にジャコモ様と出会い、話した後、オペラの台本を書くことを決意したと言った。それは何千という恋人を持ち、女性への愛のためにだけ生きた男の物語だった。若き作曲家、モーツァルトの作曲で1787年に初演されたそのオペラのタイトルは『ドン・ジョヴァンニ』だった」。この初演は、カサノヴァが62歳の時のことであった。