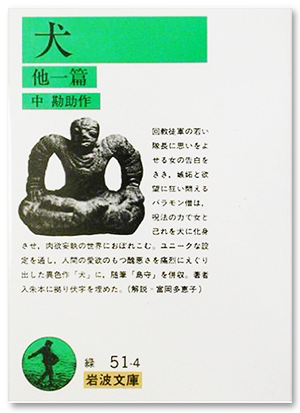『犬』を読まずして、中勘助を語ることなかれ
若い時分に『銀の匙』を読んだが、正直言って、儂にはどうにも好きになれんかった。猫も杓子も『銀の匙』は傑作だと持ち上げよるので、天邪鬼の儂は気に食わんかったのじゃ。この作品を絶讃したという漱石まで、危なく嫌いになりそうになったほどじゃった。
ところが、この年になって、『犬』(中勘助著、岩波文庫)を読んで、儂は長いこと中勘助という作家を誤解しておったことに気がついたんじゃ。儂はこれまで本だけはそれなりに読んできたつもりじゃったが、これほど「女の恋」と「男の性」を生々しいというか、毒々しいというか、おどろおどろしく描いた作品には出会ったことがない。
インドの変身譚という形をとったことが、この作品を成功させているんじゃなかろうか。それは1018年のことじゃったが、厳しい修行に励む年老いた苦行僧が、草庵の前を毎日通る若い百姓女に懸想してしまったのじゃ。その修行僧の汚いことと言ったら半端じゃないぞ。「どこもかしこも腫物と瘡蓋(かさぶた)と蚯蚓(みみず)腫れとひっつりだらけで、膿汁と血がだらだら流れている。自ら厳酷な苦行者であった湿婆(しば。ヒンドゥー教の神)はかような奇怪な肉体の苛責によってよろこばされると信じられてるのである」。
この百姓女は、不幸せな孤児で、遠い身寄りの者にこき使われる毎日を送っておった。「彼女は物心づいてからろくに人情のやさしみ温かみを味ったことがなかった。そうして眠る時のほかはほとんど休む暇もない労役に鍛えられつつ今度十七の春を迎えようとしてるのである。いったいが丈夫に生れついた身体は必要上めきめきと発達し、一方に境遇上の苦労や気づかいはその顔に明な早熟と孤独の表情を刻みつけて、彼女を実際の齢よりはよっぽどふけてみせた。ただおのずから流れいづることをとめられたあどけなさとあてのない深い憧憬とが乳房に乳のたまるように健な胸の底に熱く溜っていた」。
ところで、この娘は他人に言えぬ秘密を抱えておったのじゃ。アフガニスタンのイスラム王国の軍隊が、苦行僧や娘の住む町を通り過ぎた時、奪略、凌辱、殺戮の限りを尽くしていったのじゃが、娘はその軍隊の若き隊長に穢され、子を孕んでおったのじゃ。「彼女は一般に邪教徒のいかなるものであるかは知り過ぎていた。それは憎むべきもののなかでも憎むべく、恐るべきもののなかでも恐るべきものであった。彼女は彼らを憎み、恐れ、かつ咀っていた。それにもかかわらず彼女は己を抱愛した若い、美しい、優しい――と思った――男を憎むことができなかった。そればかりかどうしても忘れられない。彼は彼女を穢した。それが穢したのならば。とはいえ彼の抱愛はいかばかり熱烈なものであったか。それは彼女がいまだかつて夢想だもせずして、しかも我知らず肉と心の底の底から渇望していたところのものであった。彼女はその思い出すも恐しい、奇怪な、しかも濃(こまやか)に、甘く、烈しく狂酔させたところのそれを思うのであった。それは恐しく、奇怪であったがためにますます不思議な魅力のあるものとなった。彼女はまた自分の腹の子を考えるとき、男と自分との間に一種神秘な、神聖な鎖が結ばれたような気がしてならない。そうして彼がいつか再び戻ってきて自分とめぐりあうような気がしてならない。彼女は勝ちほこったような気持で覚えずほほ笑みながら胸のうちでこんなことをいってみる。『ご覧なさい。私はあなたのものです。私はあなたの子を授かりました。私は神かけてあなたのものです。私を抱いてください。口つけてください。一緒につれてってください』と」。
このことを知った苦行僧は、嫉妬に狂い、娘を自分のものにしようと躍起になったのじゃ。娘がどうしても言うことを聞かぬので、業を煮やした僧は娘の気を失わせ、その間に犯すという手段に出たのじゃ。「全身の血がどす黒く情慾に煮えた。彼は娘の覚醒するのを懼れてそうっと着物をほぐしはじめた。上体とよく釣合った下半身が露れた。それをまた先のとおり精査した。彼は女の匂を嗅いだ。髑髏の瓔珞をはずしてかたえにおいた。そして眼を血走らせて女の体に獅噛(しが)みついた。・・・娘はまだ喪神している。ただ前とは姿勢がちがっていた。彼ははじめて女の味を知った。彼は今弄んだばかりの女のだらしなく横わった体を意地汚くしげしげと眺めてその味を反芻した。そして今までとは際立ってちがった一種別の愛着、性慾的感覚にもとづくところの根深い愛着を覚えた。彼は嬉しかった。たまらなかった。・・・『わしはもうなにもいらぬ。わしはもう苦行なぞはすまい。なにもかも幻想じゃった。これほどの楽しみとは知らなんだ。罰(ばち)もあたれ。地獄へも堕ちよ。わしはもうこの娘をはなすことはできぬ』。『それにしてもわしは年よっている。そうして醜い。これからさきこの娘はわしと楽しんでくれるじゃろうか。いやいや、とてもかなわぬことじゃ。ああ、わしはあの男のように若う美しゅうなりたい。そうしたなら娘も喜んで身をまかせてくれるじゃろうに』」。
僧は長いこと思案した末に、娘も自分も畜生になって添い遂げることを思いつき、怪しい呪文を唱えて実現させてしまったのじゃ。狐色の牡犬と牝犬に変身した二人、いや二匹の交尾の様は、いかに儂でも赤面せずには語られんほど浅ましいもんじゃ。「彼女は暴力に対する動物的な恐怖に負けてしまった。彼女はきゃんきゃんと、悲鳴をあげた。口から泡をふいた。神意によって結ばれた夫婦の交りは邪教徒の凌辱よりも遥に醜悪、残酷、かつ狂暴であった。・・・僧犬はやっと背中からおりた。彼女はほっとした。が、その時彼女の尻は汚らしい肉鎖によって無慙に彼の尻と繋がれていた。彼女は自分の腹の中に僧犬の醜い肉の一部のあることを感じた。それは内臓に烙鉄をあてるように感じられた。彼女は吐きそうな気になった。いわばその胎から嫌悪がしみ出した。彼女は早くはなれたいと思って力一杯歩き出した。僧犬は後退りしてくっついてくる」。
それからも僧犬にとっては極楽の、彼女にとっては生きながらの地獄の日々が続いたのじゃが、女は心の中で、そして夢の中で、「あの人」を恋い慕っていたのじゃから、女というのは何とも不思議な生き物じゃのう。「僧犬は溜息をついた。彼は数多い呪法のなかに一途な女の恋を忘れさせる法のないのをくやんだ。しかも彼はなお懲りずまた執念(しゅうね)くかきくどいて夜となく昼となく彼女を悩ました」。
同じ男として、この僧の思いは理解できないこともないが、女というものは本当に分からんもんじゃな。
それにしても、この娘の恋は、女どもの恋というものを見事に暴いておるわ。愚かしいことに、相手の男の内容よりも外見に夢中になるということじゃが、世の常とは言いながら腹立たしい限りじゃ。隊長の心の内を娘に教えてやりたいぐらいじゃ。「彼はふとこのまえここに宿営した時に慰(もてあそ)んだ娘のことを思い出した。『可愛い奴だった。つかまえられて螇蚸(ばった)みたいに跳ねおった。だがおれはあとで可哀想になった。そうして帰してやる時ちょっと名残惜しいような気がしたのはへんだった。とにかく可愛い、いい奴だった。自惚かもしれぬが奴おれに惚れたような様子もみえた』」。
この物語の意外な結末は、敢えて語らないでおくほうがよさそうじゃな。