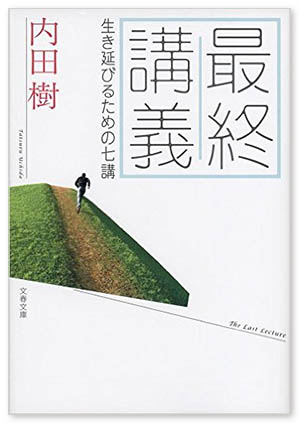内田樹の「『七人の侍』の組織論」に脱帽
内田樹の本は多数出版されているが、7つの講演録が収められている『最終講義――生き延びるための七講』(内田樹著、文春文庫)は、見逃すことのできない一冊と考える。その理由は、3つある。第1は、映画『七人の侍』を題材とした組織論が秀逸であること。第2は、人が何事かを成し遂げるときに感じる昂揚感がヴィヴィッドに描かれていること。第3は、日本の実態はアメリカの衛星国・属国であること、そして、その強化を推し進めている人物の正体が明らかにされていること。
「映画『七人の侍』に学ぶ組織のあり方」は、このように始まる。「どうやって共同体を形成するのか。どうやって他者と相互に助け合い、認め合い、許し合って共生するのか。それを教えることが学校教育のいちばんたいせつな目標の一つだと僕は思っています」と始まる。「組織論というのは、別の言葉で言えば、共生のための知恵ということになると思いますが、僕は『組織論』を語るときにしばしば黒澤明の『七人の侍』(1954年、東宝)という映画を引きます。ご存じの通り、これは7人の武士が農民たちに雇われて、彼らの村を襲う野武士と戦うという話ですが、『強い組織』『効率のいい組織』『求心力の強い組織』がどういうものかということについて実に含蓄の深い知見を含んだ映画だと思います」。
浪人・島田勘兵衛(志村喬)がリーダー、片山五郎兵衛(稲葉義男)がサブ・リーダー、七郎次(加東大介)がイエスマン、五郎兵衛が「まず腕は中の下。だが、愉快な男でな、話をしていると気持ちが晴れる。長い戦いのときには役に立つ男だ」と見抜いた林田平八(千秋実)は逆境時に役立つ人間、久蔵(宮口精二)が斬り込み隊長、菊千代(三船敏郎)がトリックスター――という、組織における6人の役割分担は、言われてみれば、なるほどそのとおりだなと納得できる。
内田の真骨頂は、残る1人の岡本勝四郎(木村功)の役割分析にある。「これはまだ少年といってもいいくらいの青侍ですから、腕はぜんぜんダメです。修羅場を踏んだ経験もない。戦闘力としては使い物にならないんですけれど、とにかく勘兵衛を尊敬している。この人を『メンター』にして侍としての成熟を果そうと願っている。でも、この若侍がいるせいで、他の6人の侍の戦闘力があきらかに向上する。というのは、あとの6人には『どんなことがあっても勝四郎を死なせてはならない』という暗黙の了解があるからです。勝四郎は若い。でも、彼には圧倒的なアドバンテージがある。それは若さです。彼にはあとの6人にないもの、『時間』がある。勝四郎が生き残ってくれたら、彼はかつて若者だったときに、自分がそれぞれに個性的な6人の侍たちとどんな英雄的な戦いをしたか、それを必ず語り継いでくれるに違いない」。
著者は、自分が同業者からどう言われているか、よく心得ている。「久しく日本の人文科学研究者は『輸入業者』だと言われてきました。もちろん、よい意味ではありません。海外の先端的な知見を、自分たちが持っている語学や知識を使って取り込み、日本人の読者にも理解できるようなかたちに『噛み砕く』。それだけしかしていない。オリジナルなものが何もない。知的な資源を原産地から市場まで運んで来るだけの、運搬業者にすぎない、と。僕もこの点では日本の伝統に忠実であり、それについては同業者からずいぶんきびしい批判を受けました。『内田くんはvulgarizationがうまいね』という言い方をされたことがあります。vulgarizationというのは『通俗化』ということです。難しい学術的な概念や仮設を、わかりやすい日常的な譬え話に落とし込んで説明することがたしかに僕は得意です。この方面では間違いなく才能があると思います。『これって、要するにあれのことだよね』という連想によって、似ても似つかぬものの間に思いがけないパターンの類似性を見出すのは僕の数少ない特技です。でも、それは学術的な能力としてはまったく評価されない」。この堂々たる開き直りは、小気味よい。
「危機的局面であるほど上機嫌であれ」という言葉には、共感を覚える。危機的な局面を切り抜けるには、自分の知的・身体的なパフォーマンスを最高レヴェルに維持する必要があるというのだ。上機嫌でいることが、判断力や理解力を最大化するからである。
「アカデミック・ハイの感覚」は、こう説明されている。「自分がこの後しかるべき資料に当たり、必要な論証を整えて、最終的に納得のいく結論に達して、(論文を)一本書き終わった時の達成感はすでに先取りされている。『この論文は完成する』ということがあらかじめ、僕のなかに確信される。そんな経験をしたことがこれまでに2、3回あります。実際に『アカデミック・ハイ』の状態で『書き終わった感じ』を先駆的に経験できた場合、論文も本も必ず完成する。自分のなかではかなりクオリティの高いものが書ける。あとで読み返したときに、どうして自分がこんなアイディアを思いついたのか、それがわからない不思議なものが書ける。こういうことは、経験したことのない人にはほんとうに伝えにくいのですけれど、この全能感、達成感というのは、僕たちがそもそも何のために学問をやっているのかという、根本のところにかかわりがあると僕は思います」。営利栄達でも、知的優越でもなく、自分の脳が高速度で回転しているという実感が人を駆り立てるというのだ。私もレヴェルはともかく、アカデミック・ハイを感じたときに、自分で納得できるものができ上がるという体験をしている。
日本の対米従属を強化している人物について、著者ははっきりと名指ししている。「『買弁』的政治家の代表が今の総理大臣です。まったく国益に背馳する政策を安倍首相は次々と打ち出しています。『集団的自衛権の行使』というのは要するに、アメリカの海外の軍事活動に追随していって、アメリカの青年の代わりに日本の青年が血を流し、アメリカが負担している軍費を日本国民の税金から支払うことです。アメリカからすれば自分たちのためにそうしたいと日本の方から申し出てきているのですから、断る筋の話じゃない。でも、その見返りに首相は何を要求したのか。『靖国神社参拝』です。・・・彼個人のプライヴェートな宗教的信条を満たすために、外交的な譲歩をしてみせたということです。個人の宗教的行事を果すために、国民の生命身体と国富を差し出した。・・・自国の首相が衛星国・従属国の指導者しか口にしないような常套句を口走っていることを『変だ』と思う国民がいない、野党も指摘しない、メディアも批判しない。それが日本が衛星国・従属国であることの何よりの証拠です」。「買弁」とは、「自国の資源を外国の支配者に売り渡して、その代償にいくばくかの自己利益を手に入れるもの」のことだと述べている。火を噴くような舌鋒が、核心を衝いている。