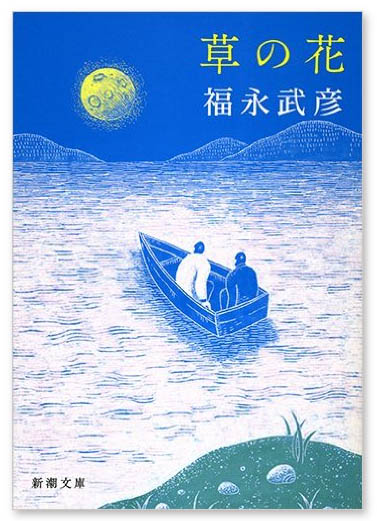恋愛の、そして人生の本質について、深く考えさせられる福永武彦の小説
若い時はともかく、最近は恋愛や人生について思いを馳せることがめっきり少なくなった私であるが、『草の花』(福永武彦著、新潮文庫)のおかげで、久しぶりに青春の息吹に触れることができた。
先ず、語り手が、太平洋戦争中に結核療養のためサナトリウムに入所していた時のこと、そこで知り合った個性的な患者たちの様子が語られる。
そのうちの一人、当時としては非常に危険性の高い肺摘の手術を自ら望んで受けた汐見茂思(しげし)という若い男から、自分が死んだら、読んでくれと、長い手紙を託される。「現在では、成形でも肺摘でも手術死ということは殆どないが、当時の肺摘には謂わば決死の覚悟が要った」。「『君、この僕の枕の下にね、ノオトが二冊入れてあるんだ』。『ノオト?』。『二冊だぜ。いつも僕の書いていたノオトさ。それを、もし僕が死んだら君にあげる』。『何だい、変なことを言うなよ』。『ゆうべはまだ決心がつかなかった。君になら、分ってもらえるかもしれない。つまらなかったら焼き捨ててくれたまえ。僕は生涯に友達らしい友達を持たなかった。それに格別、人に読ませようと思って書いたのでもない。しかし君には、・・・まあいいや。とにかく、君になら読んでもらってもいいような気がして来た。但し、僕が死んだら、だよ』」。
手紙は二通あり、その第一の手紙には、18歳の汐見が愛した弓術部の後輩男子・藤木忍からよい反応が得られず悩んだこと、藤木が思わぬ病気で急逝してしまった経緯が綴られていた。
もう一つの第二の手紙のほうには、24歳の汐見と藤木の妹・千枝子との恋愛の顛末が記されていた。互いに惹かれ合いながら、もう一歩のところまで行きながら、二人の愛は成就することなく終わる。平凡な幸せを望んだ娘と、自分の信念に忠実に生きることを選んだ男との間には、埋めることのできない溝が横たわっていたからである。戦時下のこととて、いつ何時、徴兵され戦地に送られるか分からないという重苦しい不安が汐見に覆い被さっていることが、彼の人生観に大きな影響を与えているのだ。
「藤木千枝子は決して際立って美しい少女ではなかった。僕は彼女の兄と親しくしていた頃、しばしば千枝ちゃんがもう少し藤木忍に似ていたらなあ、と考えたものだ。彼女は平凡な、そこらへんに幾らでもいそうな女学生だったが、ただその瞳はいつも澄んでいて、そこに知的な光を宿していた。しかし彼女の表情は感情に従ってしょっちゅう変り、殆ど停止した、定着された、ただ一種の情緒のみを示すということがなかった。性質が明るく、無邪気で、殆ど快活といってもいい位で、僕が知的な瞳などというのも、ひょっとしたら彼女が或る女子大学の数学科の学生だったからそう感じたのかもしれない。しかし人は愛するために、必ずしも美人を選ぶ必要はない。僕のようにいつも憂鬱にふさぎ込んでいて、交際もすくなく、家庭的にもめぐまれていない人間にとって、この健康でよく笑う少女は、当時の僕の夢をつくりあげていた。・・・真丸い顔とつぶらな瞳、やさしげな薄い脣とふくよかな頬、――恐らく藤木千枝子が僕に与えた印象は、僕がその頃抱いていた心象の中の(芸術的憧憬を具現化した)女性像と、微妙に交流していたのだろう」。
「――だってあなたの言う千枝ちゃんは、あなたの頭の中にだけ住んでいる人よ、このあたしのことじゃない。・・・――あたしは汐見さんの言うようにはなれないわ。――どうして? 僕は千枝ちゃんに何も註文なんか出してやしないぜ。千枝ちゃんは今のまんまで結構なんだ、僕はそういう君が好きなんだ。――あなたは夢を見ている人なのよ。ええそうよ。昔あなたは、兄ちゃんを好きだった頃にも夢を見ていらした。あたし兄ちゃんの言った言葉が忘れられないわ、汐見さんは夢を見てる、けれど僕には見られないって。あたしもそうなのよ。同胞(きょうだい)ってそういうものなのね。――そんなことは、千枝ちゃん、僕は何も夢を見てくれなんて頼みはしないよ、分らないかなあ? ――でもねえ、夢はいつか覚めるでしょう、あたしは惨めにはなりたくないの。千枝子は薄い脣をわななかせ、また暗い夜の方を向いた。僕はその横顔が、ふと、不思議なほど、藤木忍の横顔に似ていると感じた。そんなに僕は夢ばかり見ている人間だろうか、夢を見ることは悪いことだろうか」。
「千枝子は並んで、小柄なその身体を僕に摩りつけるようにした。僕等は薄暗い横通りを選んで歩き、こうして二人きりで、何処までも歩いて行けたらどんなにかいいだろうと僕は思った。しかし停車場はもうすぐそこだった」。
「そしてこういう時ほど、千枝子に会いたいという焦心が、僕の中に急激に高まって来ることはなかった。その明るい声を聞き、その暖かい手を取ってさえいれば、不安は容易に消え去って行くだろう。しかし僕は、空気のように僕の廻りに立ち覃めている不安、いつ来るか分らないこの未来の瞬間への不安と闘いながら、わざと、容易に千枝子に会いに行かない自分の意志を大事にした。それは決して僕の愛が小さかったからではない。会おうとさえ思えば、毎晩のようにでも出掛けることは出来たし、感情は常に僕を促してやまなかった。それなのに僕は自分の意志を靭く保つことに、奇妙な悦びを覚えていたのだ。それにぎりぎりまで感情を抑え、千枝子への愛をこの隔離された時間の間に確かめることほど、僕に愛というものの本質を教えるものはなかった。愛が持続であり、魂の状態であり、絶えざる現存であり、忘却への抗いである以上、会うとか、見るとか、話すとかいうことは、畢竟単なる現象にすぎないだろう。僕と千枝子とが愛し合っているならば、僕等の魂は、その奥深いところで二つの楽器のように共鳴し、微妙な顫音をひびかせ合っているだろう。――僕はそのように考えた。心から千枝子を愛していながら、恐らく僕は。一方であまりにも自分の孤独を大事にしていたのだろう。・・・僕は、愛すれば愛するほど孤独であり、孤独を感じれば感じるほど千枝子を愛しているこの心の矛盾を、自分にも千枝子にも解き明すことが出来なかった」。
「千枝子の眼が、きらきらと光って、すぐ僕の側に、やや俯いて、物思わしげに僕の脣方を見詰めていた。その塑像のように動かない顔が、ふと、僕の書いている小説の女主人公のように錯覚された。その瞬間、時間が止った。手に力を入れ、僕をその顔の方へ引き寄せたのは千枝子だった。冷たい脣が、無量の味わいを含んで、僕の脣の上を覆い、烈しく僕を忘却と陶酔の彼方へ押し流した。純潔な、しかしあらゆる情熱を潜在させた脣が、呼吸を止めたこの永遠の沈黙を天と地との間につくった。しかし、それは瞬間だった。千枝子はさっと顔を持ち上げると、くるっと机の方に向きを変え、両手で自分の顔を隠すようにした」。
「彼女の断髪の髪がさらさらと僕の頬に触れた。乳房が一層暖かく、僕の手の中に盛り上った。僕はその身体を折り曲げるようにして脣を探した。・・・湿っぽい草の匂と、少女のみずみずしい肌の匂とが、僕の意識を充し、熱い脣の感触がその中を火花のように貫いた。掌の五本の指が、まさぐるように彼女の髪を求め、それを僕の顔の方へ押しつけた。髪は乱れて顔を半ば隠していた。脣をゆるめると、千枝子は切ないような烈しい呼吸をした。そして僕等は絡み合ったまま倒れていた。僕は片手でその髪を草の茂みから支えるように抱き、空いた手を彼女の胸の上に置いた。呼吸の度にその胸はゆるやかに盛り上った。・・・千枝子は無抵抗に、僕に抱かれたまま眼を閉じていた。・・・しかし、何かが僕をためらわせた。何か、――それは何だったろう。僕はその時の僕の意識を正確に思い出し得ない」。
汐見と千枝子は別々の道を歩むことになり、その後、汐見は手術の失敗でこの世を去る。
最後に、汐見の最期を知らせ、彼から長い手紙を託されたことを伝えた語り手のもとに、千枝子から長い返書が送られてくる。そこに書かれていたのは・・・。汐見の第二の手紙と、この千枝子の手紙を併せ読むことによって、二人の恋愛の真の姿が立ち現れてくる。
私が、汐見の立場に置かれたら、どう行動しただろうか。恋愛について、人生について、その本質を改めて深く考えさせられる作品だ。福永武彦の実体験が強く反映しているのだろう。
本書を読んだことで、恋愛至上主義者を自任している私の確信が揺らいでしまった。と同時に、矛盾するようだが、福永武彦がますます好きになってしまった私。