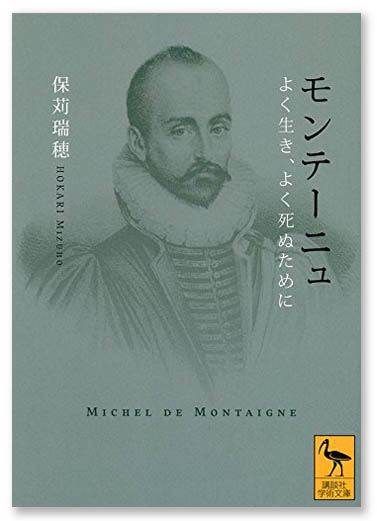『エセー』は、思索の深まりを反映して、長年に亘り書き加えられていた
『プルースト 読書の喜び――私の好きな名場面』(保苅瑞穂著、筑摩書房)で、保苅瑞穂のマルセル・プルースト理解の深さに目から鱗が落ちた経験があるので、その保苅がミシェル・ド・モンテーニュのことはどう捉えているのか知りたくて、『モンテーニュ――よく生き、よく死ぬために』
(保苅瑞穂著、講談社学術文庫)を手にした。
「ある本に巡り合ってそれを読んでいるうちに、どうかすると無性にその著者に会ってみたくなることがある。ただそうは思っても、そのときはほとんどもうこの世の人ではなくなっている。それでもこんな人間がこの世にいたのかと思うと、それがうれしさや共感になり、ときには生きることの励みになることもある。実際そんな本に出会ったときは、日が傾いて散歩に出ても木立の緑が息づいて見えて、家の近くを流れる野川に沿った小道を歩く足取りがいつになく軽くなっている。他愛がない話である。しかし事実はそうなのであって、ただ一篇の詩、あるいは何ページかの散文であっても、それが優れたものであれば、その力がこちらの命にじかに響いて来て、生き返ったような気持にさせられるものなのだ」。私も、しょっちゅう、同様の気持ちを味わっている。「なぜモンテーニュを語るのか」という著者の文章の一節であるが、この種の幸福感をこんなに巧みに表現できる人は滅多にいない。
老いを感じたモンテーニュは、どう考え、どう行動したのか、これが私の最大の関心事である。「カエサルやアレクサンドロスが生涯をかけてやった仕事、戦闘に勝つことも、国を統治することも、財を成すことも、付属的なことに過ぎないと言っている。老いが来て、生命の力が衰えて行くのを感じると、かれはそれまでの倍の力で生きていることを味わおうとした。かれがあれだけ本を読み、勉強したのも、それによって知識やなにかの肩書きを得るためではなく、よく生きて、よく死ぬためだった。そういう人間が400年前のフランスにいたのである。わたしはその人に本のなかで偶然巡り合った」。
本書で取り上げられている老年期のモンテーニュのロマンスが目を引く。「モンテーニュは、晩年になって思いがけない幸運に恵まれた。一人の若い娘が『エセー』に魅せられて、自分の方からモンテーニュを訪ねて来たのである」。
また、城館の最上階にある書斎で『エセー』の執筆に明け暮れるモンテーニュの日常の様子も興味深い。「かれは読書や夢想に飽きると、あるいは本の執筆に倦むと、今度は体をほぐすために戸外へ出て、家長の務めとして中庭や家畜小屋を見て廻ったかも知れない。あるいは城館を出て、ときには果樹園のなかを歩むことがあったかも知れない」。
『エセー』の最も重要なテーマの一つは「死」であるが、モンテーニュはどう考えていたのだろうか。「われわれはこの地上に生まれて、やがて老いて、死ぬ。これは人間だけでなく、生きものすべてを支配する掟として動かすことができない。・・・人間は生きながらに自分の死を意識することができるから、その不安から死について考えるのは人間の習性とも言える。モンテーニュもこの死というものに強い関心を示していて、『エセー』のなかでも重要な主題の一つはこの死である」。
モンテーニュが、『エセー』第1章第20章の「哲学することは死ぬことを学ぶこと」を記したのは、彼が39歳の時のことである。この文章は、『エセー』の中で最も早い時期に書かれているのである。
「『c』(=最も新しい、晩年の書き込み)という符号が示すように、この2行は、かれが最晩年になって加筆したものである。(加筆前と加筆後の)2つの文のあいだには、人間に対する認識の深まりが、なにか深淵のように口をあけている。『エセー』という本は、ときにはよほどゆっくりと読まなければ、こうした深淵を知らずに渡ってしまって、一見平和に見える文章のあいだに隠された、途方もない思想の落差を読み落とすことがある。いまのがその一例である。われわれが死ねば、いっさいの事物もまた死ぬ。この醒めた認識のまえでは、存在の連鎖も、魂の永生も、肉体の復活も、議論の余地を失うのである。しかし、この2行についてはまだ言うべきことが残っている。わたしはそこからいっそう厳粛な光景を想像せずにいられない。それはこの文が表立っては言っていないこと、いわば語られたことが指し示す彼方にある。世界のいっさいの事物は、われわれの死とともに死ぬとモンテーニュは言った。だが、そう考えるのは死んで行く人間にとってであって、あとに残る事物や他の人間にとってではない。われわれが眼を閉じたその瞬間に、すべての存在が消える。しかしわれわれの死後にも、世界は存続しているだろう。・・・死をこのように掴んだ人間に、魂の不滅、肉体の復活、万物の流転といった哲学や宗教の慰めが入り込む余地があったとは思えない。人間の生死とは没交渉に、世界は生成し、存続している。これが現実であって、ただそう考えないのがわれわれ人間の性(さが)であることをモンテーニュは見抜いている」。
「モンテーニュが、死を単なる一瞬の出来事と見なすようになったのは晩年のことである。そうした境地に到達するには、かれなりに長い道のりが必要だったのである。実際、死というものをどう考えたらいいのか、それに対するかれの態度にはかなりの曲折があって、その折々のこころの動きを記録した『エセー』が語るとおり、若いころと中年過ぎとでは、死の考え方が大きく変わって行くのである。そしてその変化は、かれの思索の深まりを示すものでもあったから、死を語るかれの晩年の言葉にはそれだけの読み応えが感じられる。・・・われわれの生命を最後に消すのは死であって、死は非業の死であれ、自然な死であれ、必ずわれわれを襲うものであれば、生きていることを自覚する人間がやがて来る自分の死を思い、死を恐れるのは自然なことかも知れない。・・・はじめのうちモンテーニュは、死が人生の最終の目標だと考えた。そして、ストア派の賢者のように、死ぬときの心の準備をして、死の恐怖に打ち克とうとした」。
モンテーニュの死に関する思索はより深まっていく。「死は、短いあいだの出来事であるから、苦痛でも不快でもなく、それが死の『本当の自然な顔』だというのである。・・・こうして、モンテーニュは落馬事故から死に関する教訓を得たのである。・・・死を人生の最終の目標と見る見方はきっぱりと捨てられている。生きている間は生きることに打ち込むしかないのが人間であり、そういう存在である人間にとって、この心の変化は限りなく大きい。また死に不断に備えることで死の恐怖に打ち克つというストア派の賢者のような態度も捨てられる。といって、それに代わる明案があったわけではない」。
晩年のある日、モンテーニュは自分の一生を振り返って、こう書き加えている。「私はそれ(人生)が芽を吹いて、花を付け、実を結ぶのを見た。そして今、それが枯れるのを見ている。幸せなことだ。なぜならそれが自然だからである。いま罹かっている病気も来るべきときに来たのだし、過ぎ去った人生の長かった幸福なときを、病気はいっそう懐かしく思い出させてくれるのだから、それだけ静かに、私は病気に堪えている」。著者は、こう結論づけている。「楽しかった人生の盛りの頃を思いながら静かに病気に堪えている。そうしているうちに、歯が抜けるといった小さな死が訪れるようになる。そして、その先に来る本当の死をもう恐れることもなく、それを生の最後の一瞬として迎えるだろう。・・・死は恐るべき宿敵でなくて体のなかに住みついたかれの一部になっている」。死を親しい友のように迎えたモンテーニュは、彼の住み慣れた城館の一室で穏やかに息を引き取ったという。59歳と6カ月の生涯であった。
本書によって、私にも「死」を迎える心構えができたような気がする。