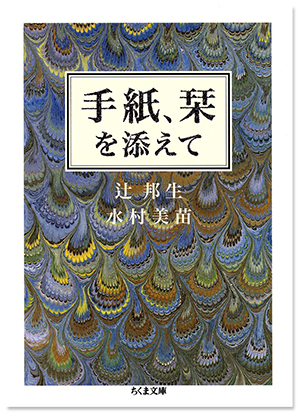
辻邦生と水村美苗の往復書簡が紡ぎ出す豊饒な文学世界
大分以前に朝日新聞の読書欄に連載された辻邦生と水村美苗の往復書簡『手紙、栞を添えて』を、当時、興味を持って読み始めたのだが、私の好きなモーパッサンに二人が「第一級とは認めがたい作家」と低い評価しか与えていない件(くだり)で気分を害し、それから先を読むのを止めてしまったことがある。ところが、定期的に読書情報を交換している読書仲間の只野健から、文庫版の『手紙、栞を添えて』
(辻邦生・水村美苗著、ちくま文庫)から大いに刺激を受けたという書評が送られてきたのに触発され、今回、改めて本書を手にした次第である。
会ったことのない二人が往復書簡形式で文学論を語り合うという趣向が成功し、そこには豊饒な文学世界が広がっている。
水村が、シャーロット・ブロンテの『ジェイン・エア』のヒロイン、ジェーン・エアの高らかな自由への意志を情熱的に論じる。ロチェスターの前に現れたのは、「質素な身なりの18歳の娘です。青白い顔は少しも美人でない。小柄な体には女らしい豊かさもない。しかも、しかるべき家の御令嬢などではなく、館に雇われた家庭教師でしかない」。「ジェーンは家庭教師という当時女に開かれた唯一の自活の道を盾に、どこまでも『人間』であろうとする。どこまでも『人間』であろうとすることによって、あのシンデレラより、強く、深く、狂おしく、(ロチェスターから)愛されるのです。われら女にとってこれほど真に教訓的で、かつ夢を与えてくれる話はないではないか!」。
これに対し、辻は、「以前は、『ジェーン・エア』より妹のエミリー(・ブロンテ)の『嵐が丘』のほうが遥かに偉大だと思っていました。今では『嵐が丘』の宇宙論的な黙示も偉大だけれど、シャーロットのひたむきな生き方にも深く共感します」と返信する。そして、私の好きなバルザックに筆が及ぶのである。「私は『ジェーン・エア』のことと同時に、実はバルザックのことも考えているのです。というのは、個人が家庭・社会と戦い、『人間の証である自由』を得るドラマを組織的に書いたのはバルザックだったからです。彼の描くのは、多くは制御しがたい力との葛藤から生まれる悲劇です。しかし社会の前に立ちはだかる人間は屈服しません。全社会を視野の中に入れ、まず社会をパノラマ的に見ることで乗りこえようとします」。
辻は『嵐が丘』を、「『この世を超えるもの』を熱烈な存在感で実現し、世界文学にも稀な、ヒースクリーフとキャサリンの恋の真実を描いたエミリーは、西洋文明の生み出した典型的存在にほかなりません」、「エミリー・ブロンテのように完全な孤独の中で書くことは、読者がいないという絶望的状況でもありますが、同時に、自分にとって最も大切なことを、自分に向かって書くという根源的な意味を開示してくれます」と、高く評価している。
水村が、私の好きなプルーストの『失われた時を求めて』を論じているが、この作品の本質を鋭く衝いている。「回想形式のこの長編が、文字どおり、円環構造をしていることは有名です。しかもプルーストは、『死』の視点から、『生』を描いただけではない。『死』の視点から『生』を描くという、作家の行為そのものの意味を描いたのです。・・・プルーストはさらに教えてくれるのです。『死』の視点から『生』を描くというその作家の行為自体、人間にとって有限な『時』との競争でしかないことを。それにしても『時』というものの根源的な残酷。それは人が年をとるという残酷ではなく、人が年をとるということを、永遠に自分のこととしては、認識できない残酷ではないでしょうか。サナトリウムから帰還したプルーストの主人公は、久々にゲルマント家に顔を出す。すると昔知っていた人たちが、皆、『髪粉』をふったり、『白いあごひげ』をはやしたり、『小さくちぢこまって』しまったりして、なぜか滑稽な老け役に変装している。そのとき主人公は『時』がたってしまったのを知るのです。主人公は啓示を受ける。彼らの上に流れた『時』は自分に上にも流れたであろう。ところが、その啓示は本当の認識にはつながらないのです。本当の認識は、主人公が他人から、当然のように、そしてくりかえし、もう若くはない人として扱われることによってしか得られない。そしてその認識はそのたびごとに、驚きでもあれば痛みでもあるのです。悲しい。悲しい」。この的確な指摘は、私が『失われた時を求めて』全巻を読み終えた時に感じたことそのものである。この長大な作品は、途中で止めずに最後の巻まで読み通した者だけに、その核心部分を開示してくれるのである。
辻が、私の好きなギッシングの『ヘンリ・ライクロフトの私記』に言及している。「お便りを読みながら、突然、私がギッシングの『ヘンリ・ライクロフトの私記』を思い出したのは、季節の移りゆきを、愛着のまなざしで眺めるライクロフトという人物に、どこか日本の隠者風の面影を感じたからでした。・・・ギッシングは、貧しかったので、そう自由に本を買うことはできなかったのですが、ライクロフトには、本を持つという幸福を心ゆくまで味わわせます。現在のように本が安く自由に買える時代には想像がつきませんが、昔は(ギッシングはちょうど100年ほど前の人です)、本を買うことは、かなりの散財を意味しました」。
水村が、ジェーン・オースティンの『高慢と偏見』への思いを熱く語る。「『高慢と偏見』。この本がどんなに私たち女の間で人気があるか、男の人たちは知らないでしょう。女たちは遠慮して語らないのです。いったいどうしてこんなにも女の読者に人気があるのか――ハッハ、その答えを、モロに言います。頭のいい女が男に圧勝する物語だからです」。
二人の文学的交歓によって、次から次へと連環的に文学論が紡ぎ出され、広がっていく。最初から最後まで、文学を読む幸福が臨場感豊かに伝わってくる素晴らしい一冊だ。
読み終わって、この読み応えのある本を手にする契機を与えてくれた読書仲間に心より感謝している。



