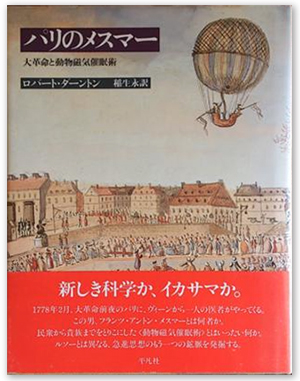
フランス革命前夜にフランス人は何に熱狂していたのか?それは革命のトリガーとなったのか?
危機的な安倍政権のもとで、政治の劣化が激しいが、社会が大きく動く気配は全くない。それでも、毎日が行動日の私に本を読む時間がない。とわいえ、本読み人の本性を棄てるわけにはいかないので、がんばるわけだが、フランス革命前夜の民衆の心性を探った本を読んでみた。
70年代、80年代特にフランス史関係者から「心性」と言うキーワードが良く聞かれ、それがテーマの書物がたくさん書かれた。いわゆるアナール派と言われた歴史学派のコンセプトなのだが、現在、歴史学界の動向を追いかける余裕がないので、その後がどうなっているのかよく知らない。しかし、当時の書物がもったインパクトは忘れ難い。ロバート・ダーントンはその先駆者であるが、超有名なのが『猫の大虐殺』という本であった。これはフランス革命の引き金になったのが、知識階級の理念とか、政治結社の政治運動とかとは別に、民衆の革命に向かう爆発する心性は実は日常のささいな事件が、その中にある社会的な矛盾にきがつかせて、大革命へと繋がったことを書いた本であった。
つまり、人間並みに扱われていない印刷職人が、自分より良い食事を与えられている親方の25匹もいる猫を密かに殺してしまうという事件から、平等とは何かという壮大な革命への疾走がはじまった過程をえがいた「猫の大虐殺」である。その同じ著者が、「動物磁気催眠術」というものが、革命前夜のフランスに大流行した様子と、そこからどのように革命の過激思想が生まれたかを詳細に描いたのが本書である。本書は、「猫の大虐殺」とは違い、フランス知識人たちの精神構造と、彼らが思い描いた世界が如何なるものであったか、それが民衆の観念と堂すれ違ったかが中心に描かれている。
ダーントンが取りだしたのは、動物磁気催眠治療術(メスメリスム)という科学(当時はそう考えられていた)である。現代人からすれば、インチキ臭い擬似科学だとしか思えないこのメスマーという人物の動きなのだが、1780年代のフランス人はメスメリスムが自然とその不可思議で不可視の諸力について、さらには社会と政治を支配する力について、解明できる科学だと心酔していったのである。メスメリズムに心の底から没頭した結果、彼らはそれを息子や孫に対し、精神的遺産のひとつとしてのこし、そこから、今日我々がロマン主義とよぶものを形成したのである。
この遺産に占めたメスメリズムの位置は、これまでけっして認められることはなかった。なぜなら、後の世代は、みずからの世界観の、不純で擬似科学的な源泉に関して、おそらくいっそう神経質であったため、旧体制(アンシャン・レジーム)末期の数年間にメスマーが占めていた指導的地位をすっかり忘れてしまったからである。ダートンのねらいは、この怪しげにしか印象が残っていないメスマーを正当な地位、つまり、この時代にもっとも話題をよんだ人物として復帰させることで、そうすることによって、啓蒙主義の諸原則がいかにして革命の宣伝要素として鋳なおされ、後に、19世紀の信条に変容していったかを示すことができるかもしれない、という意図である。
この時代のもっとも偉大な政治論考ともいえる『社会契約論』が多くのフランス知識人の関心を惹くにいたらなかったのだそうである。その代わりに、いったいいかなる形態の急進思想が彼らの嗜好に合致したのであろうか。そのひとつは、動物磁気説(マニエチスム)あるいはメスメリスム(メスマーの動物磁気催眠治療術)という不思議な姿をとってあらわれた。メスメリスムは、フランス大革命に先立つ十年間に、測りしれぬほどの関心を集めたのである。
メスメリスムは本来政治とはまったく無関係のものであったが、ニコラ・ベルガス(弁護士・政治家。1750-1832年。メスマー支援のため1781年、『普遍的調和協会』を設立)とかジャック=ピエール・ブリソー(ド・ワルヴィル ジャーナリスト・政治家。1754-93年)といった急進的なメスマー主義者たちによって、ルソーの著作に酷似した政治理論を偽装するものになっていった。メスマー主義者たちの運動は、したがって、大衆の段階で政治を一時的なブームに結びつけ、急進的な著述家たちが検閲官の注意を惹くことなく読者の関心を捉えつづけることができるような大義名分を与える方策の一例とみなすことができる。
メスマーは1734年、コンスタンツ(現在西ドイツ西南部)に生まれ、ヴイーンで医学を学び、医師として活動した。1766年、天文学とニュートンの学説を混淆した『惑星の影響論』と題する博士論文をヴイーン大学医学部に提出した。磁波を操って病気を治療することができることを発見し「動物的(アニマル)」と名付けた磁気説の実践を行なったが、ヴイーン大学医学部の反感を買い、パリへ出た。1778年2月、フランツ・アントン・メスマーはパリに到着し、身体を貫通し、その周りを取り囲む超微細な流体を発見したと宣言した。メスマーは、宇宙全体をこの原初の「自然力(アジャン・ド・ナチュール)で満たす一方、パリ市民に熱と光と電気ならびに磁気を与えるため、この「自然力」を地上にもたらしたというのである。
そして、彼は、何よりもまず「自然力」を医学に応用することを推奨した。かれの主張によれば、病というものは、磁石に似た身体を貫通する流体の流れが「阻がい」されることに起因する。したがって、個々の人間は、自分の身体の磁極を摩擦したり、それらの磁極を「メスマー化」すなわち動物磁気化することによって、この流体の活動を抑制したり強化することができるうえ、それによって障がいを克服したり、しばしば痙攣のかたちであらわれる「発作(クリーズ)」を誘発させたり、健康、あるいは人間と自然との間の「調和」を回復させたりすることが可能になるのである。このような理論と実演が主とした、治療を主眼としたものであった。それが1780年代のフランス知識人の関心事と完璧に対応するものであった。科学は、メスマーの同時代人たちが眼にみえない不可思議な力に取り囲まれていることを明らかにすることによって、彼らを虜にしてしまった。ニュートンの万有引力説はヴォルテールによって理解しうるものとなり、フランクリンの避雷針の流行やパリの社交界での講演会や博物協会(ムセイオン)での実演によって普及した。そしてシャルル気球とかモンゴルフィエ気球といった驚異的な熱気球は、1783年に初めて人間を空中にもちあげてみせて、ヨーロッパじゅうを驚嘆させた。
18世紀最大の科学者ニュートンはでさえ、「神秘的な力と特性」について異常なほどに思索をめぐらせていた。のみならず、ニュートンはボリーなる隠秘主義者の医師に多大の関心を寄せていた(「私はこの人物がいつも緑色の服をきていると思う」とニュートンは書簡の中で記している)。ことによると、この人物がメスマーの初期の化身であったということもありうるのだそうだ。科学は中世のイデオロギーと決別していたわけではないと言うことである。魔術との密接な関係が貼りついたままであった。
フランス大革命前夜を支配していたのは、どうやら驚異というものへの好奇心であったようだ。それが科学と言う衣をまとって現れた時、知の先端にふれる喜びのように流行に雪崩をうってなびいたらしい。しかしその科学は擬似科学でありオカルティズムとの境は明快ではない。むしろその境界こそがスリリングであったようである。
ダーントンがメスメリスムに注目したのは、大革命前夜フランスで大量に出版された小冊子には政治思想に類するものは非常に少ないと言う事に注目したからであるが、庶民には『社会契約論』などは浸透していなかったというわけである。メスマーの公開治療は不思議大好きのパリに大いに受けた。版画には桶のようなものに入って、磁気を流してもらい麻痺をおこして、失神することで治療を受ける多くの人。ただしこれらは金のある上流階級で、庶民はそれを見て娯楽としたようである。
この大流行は同時代の人びとに大きな影響を与えた。一つは権威(科学アカデミー)に対する挑戦やさらには政府に対する挑戦さえ思い起こさせることになり、政府に危惧の念を抱かせ始めた。メスマー自身が自らの思想にコントロールがきかなくなり、病人の治療よりは魔術的な数秘術やイシス信仰に傾き霊と交流したりする方向へ傾斜し、フランスを離れ、1815年没している。しかし、メスメリスムが消滅することはなかった。
メスマーの理論と財産とをまもるために『普遍的調和協会』なる組織が作られた。初めは貴族、卓越した市民(ブルジョワ)が占めていたが、この上流階級の組織から分裂し、メスマーの行為が金儲けのための発明であり、人類の福祉のために秘密を公開する義務を怠ったとして非難し、いわば左へ旋回させたのがベルガス成り人物であった。彼と分裂した「普遍的調和協会」グループについては詳細な記録はないそうであるが、1787年から89年にかけて、彼らは政治的危機に全面的に献身するために、ジロンド党員を迎え入れて、大革命への道をつけている。
ベルガスは、経済力の伸長に応じた政治的役割を行使するための手段として三部会の協定をうけいれた、商業ブルジョワの典型であった。彼はこの考えを、1789年の三部会構成に関するいくつかのもっとも重要な諷刺小冊子の中で展開している。協会、軍隊、法曹界ならびに各種アカデミーにおける貴族階級の支配を告発した彼は、生まれに基づく諸特権の不条理性、「封建的な政府の悲しむべき混沌」にみられる貴族の血統、ならびにこのように彼らのために不当に確保された地位で仕言をうまくやりとげる能力の欠如などを嘲笑するのであった。すなわち、地下に潜んだ急進思想の底流が、メスマー主義の運動を通して流れ、ときおり過激な政治的小冊子の中に噴出することになった。メスマー的思想がまとまった哲学的諸相に寄与することはなかったとはいえ、いく人かの革命思想家の形成につながる、科学的過激諸相と政治的過激思想との奇妙な結合の実態が証明されるのだそうである。
フランス革命後のメスマー主義者たちはどくじの解釈を推し進めたが、概して心霊主義の性質を帯びた。未来のユートピア的状態をイメージさせる原理となった。フーリエ、サン・シモン主義者に結びついた。そして、さらには19世紀前半の文学者や政治学者たちにも影響をおよぼした。メスマーは、ライン河を渡った最初のドイツのロマン主義者であるともいなされた。デュマや多くの作家に、素材を提供したのである。バルザックは、『人間喜劇』の序文で次のように書いている。
「動物磁気説、その生み出す奇蹟に、私は1820年以来慣れ親しんできた。ラヴァターの後継者であるガル(フランツ・ヨーゼフ。ドイツの医学者。Ⅰ758-1828年。ヴィーン大学、ついでパリ大学教授。骨相学の創始者)の見事な研究および、動物磁気とほとんど同じものといえる光線について光学者たちが研究してきたように、動物磁気について50年来研究を行なってきたすべての人びとは、この思想が、使徒聖ヨハネの弟子である神秘主義者の考えであると同時に、精神界を確立してきた大思想家の考えであることを確認しているのである」
メスメリスムとはなんであったのか。それは革命のムードを生成したということだと、ダーントンは結論付けている。1780年代末のフランス人は、18世紀中葉の冷静な合理主義を棄てて、異国的な知的な餌に飛び付いた。彼らは超自然的なものと科学的神秘に憧れを抱いた。つまり、ヴォルテールには振り向きもせずに、メスマーの廻りに群がったのであった。
この革命前夜の実態を知った時、驚異とか好奇心とかに庶民がなだれをうつ。その中から、本質に目覚めた人びとが、人間にとって在るべき存在を目指して立ち上がる、それが革命の下支えとなるという事があるという歴史の事実。そんなことを考えながら、今と言う時代を見返す時、大切なことは、日替わりで、ニュースとなるあれやこれやに好奇心ばかりで見ることの危険をしることだろうか?革命は庶民が苦しさに耐えかねて親方の猫を殺してしまった所からも生まれるし、怪しげな物の裏側を見据えることからも生まれる。
本書は1987年の刊行本なんだけれど、今裏表紙の外の書物の案内を見たら、あの当時、なんて素敵な歴史書がたくさん出ていたのかあらためて、思い返した。『路地裏の大英帝国』、『洒落者たちのイギリス史』、『パリの聖月曜日』(これ私の師匠の本)、『中世イタリア商人の世界』、『マルタン・ゲールの帰還』、『ハーメルンの笛吹き男』、『中世を旅する人びと』、『放浪学生プラッターの手記』、『青きドナウの乱痴気』、『巡礼の道 星の道』など。
魔女:加藤恵子



