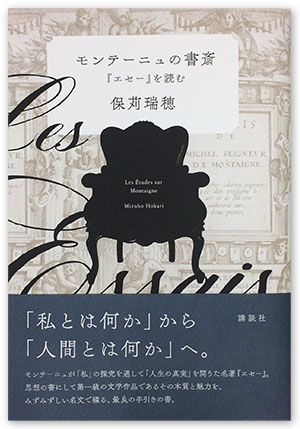
モンテーニュの書斎で、晩年の想い人、デカルト、ツヴァイクに出会う喜び
『モンテーニュの書斎――<エセー>を読む』(保苅瑞穂著、講談社)は、著者がミシェル・ド・モンテーニュに寄り添い、モンテーニュと共に思索を深めようという探究の書である。
14の角度からモンテーニュに迫っているが、私にとって、とりわけ興味深いのは、モンテーニュ晩年の想い人・グルネー嬢、ルネ・デカルト、シュテファン・ツヴァイク、読書、そして死――に関する各章である。
著者は、モンテーニュの意外な面に触れている。「『エセー』の謹厳な読者は眉をひそめるかもしれないが、わたしが見るところ彼は色好みである。それも男女の交情の機微にも通じた、なかなかの色好みだったように思う」。こう聞いて、親しみを感じるのは私だけだろうか。
「女性の読者といえば、グルネー嬢のことを忘れるわけにはいかない。1588年、モンテーニュがパリへ上京したときのことである。グルネー嬢は18か19のときに手に入れた『エセー』に夢中になって以来、著者を深く敬愛するようになったが、彼の上京を知ると、さっそく自分のほうから彼に会いに出向いて行った。このときグルネー嬢は弱冠22歳、モンテーニュは55歳だったが、会って話をするうちに、彼は若い娘のなかに誠実な人柄に加えて知性と教養を見出して、彼女がただの小娘でないことに気がついた。かくしてモンテーニュはグルネー嬢を縁によって結ばれた『義理の娘』として実の娘のように可愛がり、またおそらくは一人の女性としても愛するようになったと思われる」。
「彼は『エセー』が取りもつ縁で彼女と出会ったことについて、最晩年の(『エセー』への)加筆のなかで次のように書いていた。『運命が、この本が仲立ちになって私に贈ってくださったのかもしれない情け深いこれほどのお恵みも、それが若い頃だったら、もっとふさわしい季節に巡りあえていたことだろう』。『もっとふさわしい季節』といっているのは、いまより若くてグルネー嬢と甘美な交わりを愉しむのに適した季節ということではなかっただろうか。彼はこう書いて、二人が出会ったのが遅すぎて運命のせっかくの恵みをこころゆくまで愉しめなかったことを暗に嘆いていたのである」。このモンテーニュの、もう少し早く出会えていればという無念の気持ちは、私にもよく理解できる。そうは言っても、彼を慕うこの若い女性の存在は、死を覚悟したモンテーニュの隠棲の日々を優しく慰めるものだったのである。
デカルトはモンテーニュの思想的後継者と言えるだろう。「(モンテーニュは)哲学を、中世以来のスコラ哲学の衒学的な詮索や、宗教的権威との癒着から解放して、わたしたちが幸福になるための道徳哲学、すなわち人間的叡智という姿に戻したのである。この叡智としての哲学を受け継いだのがデカルトであった」。
ツヴァイクは、晩年の亡命時代に『モンテーニュ』という作品を著している。「かつての世界的な名声をよそに、遠い異国の地で失意の生活を送るそんなツヴァイクの最後の日々を慰め、傷ついた魂に勇気と救いをもたらしたのがほかならぬこの本(『エセー』)だった。それゆえこれは、ナチス・ドイツの暴政のなかで、精神の自由を求めて異郷の国々をさ迷って来た魂にとってその砦ともなったのである」。
「『ほんとうのことをいうと、なにをおいても私の魂は、武力にも暴力にも屈することは決してあり得なかったと信じている』(『エセー』)。ところで、問題はツヴァイクである。彼はまちがいなくこの文章を読んでいたであろう。またモンテーニュの精神の自由を貫く姿勢を示した数々の文章も読んでいたであろう。そしてそれらの文章が、ユダヤ民族を虐げるナチス・ドイツの暴力を逃れて異郷の地に亡命した彼の魂に深く響かないはずはなかったのである」。ツヴァイクは、自分とモンテーニュの運命の類似を意識しており、この痛ましい一体感がツヴァイクを『エセー』の著者に強く結びつけることになったのである。
「そんなツヴァイクを支えたのが『エセー』の次の文だった。『この世でいちばん大切なことは、だれにも左右されずに自由でいられることを心得ることである』。・・・終焉の地となるべきその土地で、ツヴァイクは、自分の運命をモンテーニュの運命に重ね合わせながら、モンテーニュが時代の狂気と暴力のなかで魂の自由を守るためにはらった努力について、こう自問自答するのである。『・・・モンテーニュはこの問いに、この問いにだけ彼の生命と力を捧げたのである。この自由を愛するがゆえに、彼は、自分の体が動くたびに、感覚が働くたびに、自分自身を観察し、監視し、試し、そして叱責した。世界中がイデオロギーと党派の前で卑屈な奴隷と化しているとき、彼はおのれの魂を救うために、おのれの自由を救うために、かかる探求を企てたのであった。そしてその探求ゆえに、今日彼は、われわれにとって、はかのあらゆる芸術家よりいっそう兄弟のようにちかしい存在になったのである』。モンテーニュを語る言葉のなかにツヴァイクの魂の叫びが聞えるようである」。
「わたしはこれほど真情をこめて『エセー』を語った人にこれまで一人も出会ったことがない。また『エセー』のほかに、これほど深く人に慰めと勇気を与えることのできる本にもまだほとんど出会ったことがない」。
読書について。「本は放っておいても人間のように嫌な顔ひとつせず、読みたくなって本を開けばいつもおなじ顔で迎えてくれる。だから本との付き合いは気兼ねなく一生続けられる。それに本は、書斎を離れて、いつでも、どこへでも読み手に付き添って行って旅のつれづれを慰めてくれる。そうした数々の利点がモンテーニュにとってなによりも本のありがた味なのである」。
続いて、「有能な読者」という言葉が現れる。「『有能な読者は、しばしば他人の書いたもののなかに、著者が書き込んだ、自分で気づいている完璧さとは別の完璧さを発見するものだ。そしてそこにいっそう豊かな意味と顔つきを与えるものである』。これこそは有能な読者に許された読む醍醐味である」。
ここで、著者が敬愛して已まないマルセル・プルーストが登場する。「(モンテーニュとプルーストの)二人はたしかにすぐれた読書家だった。しかし同時に、書こうと意欲する創作者としての意識は、読書家としてのそれをはるかにうわまわるものがあった。それゆえあれほど愛した読書を、彼らはそれぞれの作品のために精神の活動の場から遠ざけたのである」。私のように読むことだけに専念できる者は、二人のように読書を制限する必要がないので、存分に読書を楽しむことができるのだ。
モンテーニュは生涯に亘り、常に死の問題を意識していたと、著者が指摘している。「(最晩年のモンテーニュは)死がやって来てももはや尻込みすることはないだろう。そしてそのときが来るまではひたすら生きることに打ち込むだろう。彼のなかで生と死の比重は生のほうへ大きく傾いている。死は生のなかに最後の一瞬として組み込まれ、それまでどう生きて来たかによって判断される。『あらゆる死はその死が終わらせる生に一致したものでなければならない。われわれは死ぬからといってそれまでと別の人間になりはしない。私はつねに死を生によって解釈している』。だから愉しい充実した人生を送ったものは死んでゆくことにもはや不満など感じはしない。むしろ生を完成させるものとして死を待つ気持ちにさえなるかもしれない。いや、死は待ち望むまでもなくだれにでも必ずやって来る。だからそれまでは未練を残さずに死ねるように、いまはただ生きていることを精一杯愉しめばいいのだ」。
モンテーニュというのは、付き合えば付き合うほど、味わいが増してくる魅力的かつ奥深い人物であることを、本書が再認識させてくれた。
最終ページを捲りながら、モンテーニュの書斎で、私の敬愛するモンテーニュ、デカルト、ツヴァイク、そしてプルーストに出会えた幸せを噛み締めている。



