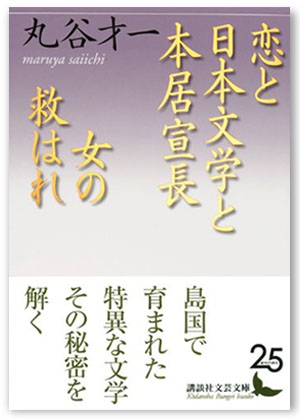
本居宣長は熱烈な恋愛至上主義者だった
本居宣長は堅苦しい国学者と思い込んでいたが、『恋と日本文学と本居宣長・女の救はれ』(丸谷才一著、講談社文芸文庫)所収の『恋と日本文学と本居宣長』に宣長が熱烈な恋愛至上主義者であったことを教えられ、俄然、親近感を覚えた。私も恋愛至上主義を信奉しているからである。
宣長は、25歳の時、学友の14歳の妹・草深民に出会い、一目惚れする。しかし、意思表示しないうちに、民は他家に嫁入りしてしまう。3年後、宣長は周囲の勧めを断り切れず、村田みかと結納を交わす。その僅か16日後に、民の夫が死亡したことを風の便りで知るが、宣長はみかと結婚する。「しかしこの結婚はうまくゆかなかつた。おそらく宣長の未練のせいでせうね。民さんのことが思ひ切れなかつた。十二月に離婚になりました。そして翌年十一年の七月、宣長は草深民さんに結婚申入れ。十一月に結納をとりかはし、翌十二年一月十七日に結婚となります。本当によかつた」。
大野晋の説が引用されている。「それまでの経過を通じて宣長は、恋を失うことがいかに悲しく、行方も知れずわびしいかを知ったでしょう。また、人妻となった女を思い切れず、はらい除け切れない男のさまを、みずから見たでしょう。その上、夢にまで描いた女に現実に接するよろこびが、いかに男の生存の根源にかかわる事実であるかを宣長は理解したにちがいない。また、恋のためには、相手以外の女の生涯は壊し捨てても、なお男は機会に恵まれれば自分の恋を遂げようとするものだということを自分自身によって宣長は知ったに相違ありません。この経験が宣長に『源氏物語』を読み取る目を与えた。・・・恋とは文字の上だけのそらごとでなく、実際の人間の生存そのものを左右する大事であり、それが『源氏物語』に詳しく書いてある。そう読むべきだと宣長は主張したかったに相違ないと、私は思ったのです」。
大野と同じように、丸谷才一も、宣長はこういう経験をしていたから、『源氏物語』や『新古今和歌集』の根底に「もののあはれ」があると見抜くことができたと考えているのだ。
さらに、丸谷は、宣長の孤立無援の闘い――恋愛を無視・排除する中国文学の強大な影響下にありながら、日本文学が恋愛を描き続けたのはなぜかを究めること――について考察している。
「彼(光源氏)が恋愛しかしないこともまた事実である。つまり光源氏は恋愛の名人だつた。われわれの文学の代表者は恋が専門でした」。
「日本文学のかういふ恋愛肯定はなぜ生じ、なぜつづいたか。これは大問題なのですが、いままで考へた人はゐなかつた。なぜ誰も考へなかつたかといふと、西洋のせいでせうね。明治維新以後、西洋の文学がはいつて来ると、この新しい文学では恋愛を取上げるのが当り前のことだつた。シェイクスピアもトルストイも恋を描いてゐる。とすれば、なぜ日本文学は恋に熱心なのかなんてことを問題にするのは馬鹿ばかしい話になつた。そんなこと論じたのでは偉い評論家に見えない。損である。だから別のことを書いたのでせう。仕方がないから、自分で一つやつてみます」。
「中国は日本にとつて圧倒的な先進国だつた。これは『古事記』の八百年も前に『史記』が成立してゐたことを見てもわかる。貨幣も、暦も、律令も、戸籍も、すべて中国に学んだ。文字は中国のものを借り、さらにはそれを元にして仮名を作つた。土木も、建築も、衣服も、医薬も、みなこの先輩について習つた。その師事ないし兄事の度合は明治維新以後の西洋に対すよりもはなはだしかつたはずで、まるで頭があがらない思ひだつたらう。ところがその先進国の文学と自国の文学とのあひだに、恋愛のあつかひにかけて大きな相違がある。性格の極端な対立がある」。このことを誰も気にしない中で、「日中両国の文学の対立を重大問題としてとらへた人が、わたしの知る限りたつた一人ゐた。彼は恋といふこの一点にこだはることによつて日本文学の宣揚に成功した。本居宣長です」。
丸谷は率直な人である。宣長にも変な遠慮はしない。「宣長には悪いけれど、ごたごたした論旨なので、すこし整理してみます。●A=中国人は道徳論が好きで、好色を咎める。詩も武勇を歌ひ、恋を詠まず。これは嘘をついてゐるのだが、日本人はこの嘘に気づかず、事実だと取る。●B=日本人は道徳を言ひ立てないたちで、『もののあはれ』を重んじ、小説に恋愛感情を率直に書く。●C=日中とも歴史を読めば違ひがない。詩歌でくらべるから話がをかしくなる。●D=一体に中国には悪人が多い。悪い国なのである。日本には悪人がすくない。神国だからである」。丸谷はDについては異議を唱えているが、「要するに、儒教的なものが欠落してゐるせいで日本では恋愛小説がよく書かれた。それだけの話である」。
たったこれだけのことを言うために、宣長がどんなに苦労したか。「西洋の恋愛文化がまつたくない状態で、その助けをちつとも借りずに、宣長は、恋愛が大切だといふ『源氏物語』と『新古今』の文学的主張を擁護しなければならなかつたのです。・・・西洋文学といふ権威を持出して闘ふ手は、宣長にはなかつた。彼はまつたく一人きりで、自分の頭だけで、中国文学といふ唯一の先進国の文学趣味と対立しなければならなかつた。そして彼の生きてゐる十八世紀後半の日本では、中国文学の趣味が支配的だつたのです。・・・宣長はさういふ状況のなかで、どう考へて、自分で納得が行つたか。中国人が倫理的に高級だから恋をしないのではない、恋をしても書かないのだ、彼らは嘘をついてゐるのだ、偽善的なのだ、と考へた。宣長にとつては必死の思ひの思索だつたでせうし、日本思想史に一時代を画する発想だつたのぢやないか。そしてこの、中国人の偽善好きといふ主題は、宣長終生の主題になります。例の『玉かつま』といふ随筆集を思ひ出して下さい。一本の赤い糸のやうに貫くものは『からごころ』排斥なんです。『からごころ』とは中国精神といふくらゐか。『やまとごころ』ないし『やまとだましひ』の対ですね」。
「宣長のこの『もののあはれ』によつて、中国文学の方法とは違ふ日本文学の方法、人間の感情の直截でしかも美的な表現を宣揚しようとしたのである。文学的先進国の理念と真向から対立する文学的後進国のこの主張は、日本文学の独立の宣言であつた。すごい事業でした」。
本書のおかげで宣長が身近に感じられるようになっただけでなく、丸谷のこともますます好きになってしまった。



