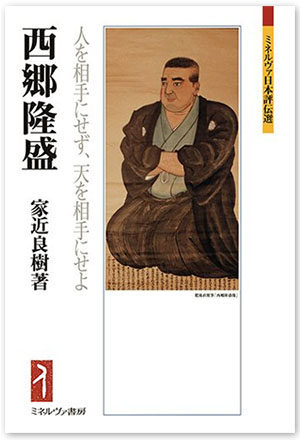
一次史料で明らかになった西郷隆盛の性格、大久保利通との仲
『西郷隆盛――人を相手にせず、天を相手にせよ』(家近良樹著、ミネルヴァ日本評伝選)には、西郷隆盛の真の姿を究明したいという著者の執念が籠もっている。その思いが580ページという本書の厚さに繋がったのだが、その願いは十分に達せられている。歴史の真実に迫ろうとするとき、一次史料が鍵を握ることが多いのだが、著者の一次史料に対する丹念な取り組みは敬服に値する。管見だが、西郷に関する通説を根底から覆す、類書の追随を許さぬ最高の研究書と考えている。
一次史料から明らかになったことはいろいろあるが、とりわけ私の目が吸い付けられたのは、●西郷の性格、●盟友とされる西郷と大久保利通との仲、●西郷の西南戦争に対する考え方――の3つである。
西郷の性格について。「映像や文学作品に登場する西郷は、肥大な体格のイメージが強すぎるためか、細事に囚われない、豪放磊落で、茫洋とした、いかにも大人物風である。だが、西郷と日常的に接した関係者の多くが指摘する彼の実像は、何事においても論理的に物事を考えようとする理詰めの人間であった。また、謹厳・実直・生真面目で、融通がきかない『堅物』であった。このことを伝えるエピソードが残されている」。
「西郷は、物欲が強く、人間性の卑しい人物をひどく嫌悪する、人の好き嫌いが大変激しい人物であった。また一度でも自分を裏切った人間は生涯にわたって許さない(容れない)人物であった。当然、『清濁併せ呑む』といったタイプではなかった。いや、むしろ対人関係においては極度の潔癖症といってもよい性分の持ち主だった。したがって、敵と味方を厳しく峻別し、敵と見なした者を激しく憎むことになった。そういう点では、彼は度量が大きい人物では到底なかった。そして、西郷はこうした性分もあって、相手とうまく妥協することができなかった。つまり、ギブアンドテイクをなしえない不器用な人物であった。そのため、島津久光らとの対立を深め、それが結局、彼の歩もうとした人生のコースを大きく歪めていくことになる」。尤も、半面、こうした西郷のあり方が、逆に「えも言われぬ」彼の魅力に繋がったと言える、と付記されている。
一次史料によって明らかにされた西郷の性格は、俄かには信じられないほど意外なものであった。
西郷と大久保の仲について。「薩摩藩内の両雄と称されたこの両人については、従来の通説的見解では、『竹馬の友』『肝胆あい照らす仲』『兄弟のような関係』『若い頃から苦労を共にしてきた無二の親友で同志』といった式の評価が支配的である。・・・ついで、やはり通説的な見解では、このような両人の関係が明治6年に発生した政変で終わりを告げたといった理解の仕方がなされてきた。本書では、こうした通説的見解に飽き足りない立場から、3歳の年齢差によって、先輩・後輩の関係にあった両人の関係が、幕末期のかなり早い段階から、盟友であるとともに、藩内では一種のライバル関係に入ったとの認識の下、それが薩摩藩のみならず、日本近代史の在り方にも少なからず影響を及ぼしたと見て」いる。
「西郷と大久保の両人はその性格も置かれた立場も大きく異なった。・・・西郷と大久保の両人を大きく分けたのは、執着度と器用度の違いであった。大久保には、自分たちの考えを藩政に反映させるために、非常な粘着力でもって島津久光への接近を試み、それを実現させるといった面があった。ところが、西郷にはそのような面がほとんど見られなかった。そして、こうしたことが両人のその後の歩み方を大きく分けることになった。大久保が、『文久2(1862)年に頭角を現して以来、一度として左遷・免職の経験がな』かったのに対し、西郷は『島津久光の勘気による沖永良部遠島、征韓論政変による参議辞職』と、重要な局面でしばしば敗者となった。そして最後は城山で文字通り敗者そのものとして人生を終える」。
西郷と大久保の関係は、世上言われてきたように単純なものではなかったのである。
西南戦争について。「西郷は、(西郷)暗殺問題の登場によって大久保政権との対決を決意したと考えられる。そして、これには、どうやら西郷が大久保らによるとされた自身の暗殺計画を真実だと受け止めたらしいことが大いに関係したと思われる。・・・西郷が大久保らによる自身の暗殺計画を真実だと判断したらしい背景には、西郷にしか理解しえない大久保の在り方(本質)への認識が関係したものと思われる。幕末時以来、西郷が盟友(ただし、あくまでも後輩)として身近で眺めてきた大久保の姿は、目的のためには手段を選ばない『非情』な男のそれであった。客観的に眺めれば、とうてい『理』があるとは周りにはみえない中、政権を返上した徳川慶喜に難癖をつけ、結果的に敗者(日本一の悪役<ヒール>)の立場に追いやった座元は大久保であった。また、明治期に入り、自分(=西郷)が熱望した朝鮮使節就任を、閣議決定がなされたにもかかわらず、不法な手段で覆したのは大久保だった。こうした男なら、欧米流の近代国家を創設していくためには、理念レベルで異を唱え、真に鬱陶しく邪魔な存在そのものとなっていた自分(=西郷)を始末する決心を抱いたと、西郷が解釈しても、いっこうにおかしくはなかった。・・・いずれにせよ、西郷らは暗殺計画を口実(理由)として決起することになった。すなわち、この件で大久保と川路(利良)に『尋問』するために東京に向かうと宣言した」。
「(西南戦争の)軍略に関しては、桐野利秋らに任せて自分はもっぱら担がれる役に徹した。しかし、これも見方を変えれば、西郷の自惚れの結果であったと言えるかもしれない。すなわち、大変な人気者で日本全国にまたがる人望のある(また支持してくれる有志が各地に存在する)自分が東上をひとたび開始すれば、風がなびくように追随者が各地で生まれ、それがやがて巨大な渦となって敵方をやっつけ、自分たちの進軍を援護してくれるだろうとの目論見であった。・・・彼が十分に勝利を収めうるとの見通しの下に立ち上がったであろうことはほぼ間違いなかろう。ただ、その見通しはきわめて甘かったと評さざるをえない。・・・とにもかくにも、この自分にとって真に都合の良い希望的観測に基づく、ごく甘の戦略論が、実際に西郷の口から発せられたとすれば、鹿児島を出発する直前段階の西郷が、勝利を収める気分でいたことは明らかであろう。・・・西郷らが自分たちが決起した理由を川路ー大久保ラインによる暗殺計画への『尋問』にのみ絞ったために、結果として大敗北を招いた。このような個人的な恨みつらみのレベルに止まる進軍理由では、とうてい広い層の支持を得られるものではなかった。すなわち、これによって、西郷らの決起は薩摩藩内の大物同士(西郷と大久保)の私的な怨み・憤りを晴らすための、取るに足りない些々たる喧嘩レベルのものだと受けとめられてしまった。・・・もし西郷らが『私怨』『私憤』レベルではなく、当時世間一般の人々が広く問題にしていた大久保政権の在り方を問う形で決起しておれば、その後の事態が大きく変わった可能性を示唆している。大久保政権は、当時、天皇の考え(『聖旨』)や知識人・民衆の意見(『公議』)を抑圧して、数人の政府高官による臆断と専決によって政治を行っているとの批判を浴びていた。そして現に、各地でそれに反発する民衆の蜂起が発生していた。そうした中、暗殺問題だけを取り上げて進軍を開始したことは、挙兵の『名義』としては、いかにも貧弱だったと評価せざるをえない。専制的・独裁的だとされた大久保政権の在り方そのものを問うて(批判して)やはり立ち上がるべきであったろう。また、実際のところ、そうしなければ、とうてい勝ち目はなかった」。
「西郷の城山での最後の日々だったが、注目されるのは、彼が敗北が決定的となったにもかかわらず、別段死に急ぐような姿勢を示さなかったことである。すなわち西郷は、鹿児島への帰還後、死に急ぐ素振りを、いっこうに見せなかった。いや、それどころか、鹿児島への帰還後も彼の戦闘意欲はいまだ強かった」。
本書によって、西郷が鹿児島の私学校生徒たちから担がれて已むを得ず西南戦争に立ち上がったという通説、最初から負けを覚悟して戦っていたという通説は覆されたのである。しかも、西郷は、根源的なレベルでの戦略ミスを犯してしまったという著者の指摘は、注目に値する。
西郷が、決して聖人君子ではなく、ある意味、普通の人間であることを知って、親しみを感じてしまった私なのだ。



