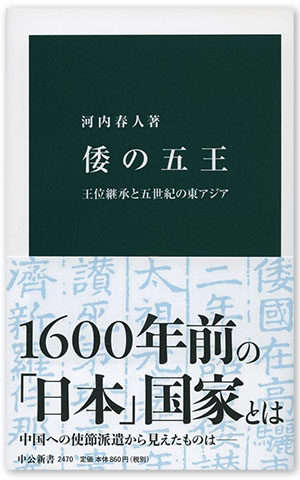
倭の五王が宋に外交使節を送らざるを得なかったのは、なぜか
私は、「倭の五王」がどの天皇たちを指しているのかに多大な関心を寄せてきたが、そういう姿勢では重要なことを見逃してしまうと主張する書が出現した。『倭の五王――王位継承と五世紀の東アジア』(河内春人著、中公新書)がそれである。
「倭国がまだ自国の記録を文字として残さない時代における中国史料として耳目を集め続けているのが、一つは3世紀の『三国志』魏書・烏丸鮮卑東夷伝倭人条いわゆる『魏志』倭人伝であり、もう一つが5世紀の『宋書』夷蛮伝倭国条(以下、『宋書』倭国伝)である。『宋書』倭国伝では5世紀の列島の歴史について、5人の王が中国に外交使節を派遣してきたとする。いわゆる倭の五王――讃・珍・済・興・武である。これまでの代表的な説を挙げれば、讃を第16代仁徳天皇、珍を第18代反正天皇、済を第19代允恭天皇、興を第20代安康天皇、武を第21代雄略天皇とする。讃・珍については他にも説があるが、済・興・武についてはほぼ確定的に考えられている。だが史料が少ないこともあり、その理解が深まっているとはいいがたい」。なお、讃については、仁徳天皇説、応神天皇説、履中天皇説がある。
著者の問題意識は、讃が、421年にそれまでの長期の断絶を超えて中国との外交に乗り出したのはなぜか、そして、それが列島支配にどのような影響を与えたのか――ということからスタートしている。
「朝鮮半島の鉄資源を不可欠とする倭国にとって朝鮮半島諸国の高句麗や百済の動向は常に注視するところであり、両国が東晋から官爵を授かり、さらに宋建国の際にもその地位を着実に上昇させたことに対して傍観していられなかったのである。高句麗・百済が宋とのつながりを深めるなかで、讃は宋王朝開基という新たな国際情勢に出遅れたことを痛感していた」。百済との軍事同盟によって東アジアに関わってきた倭国は、宋王朝の建国と宋からの高句麗・百済への働きかけを目の当たりにし、およそ150年ぶりとなる対中国外交に踏み切ったというのである。
「五王は讃から武まで一貫して宋の外臣であることを意識し続けた。それは必ずしも独立意識が低かったということを意味しない。五王たちは、いかにして宋の外臣という立場を利用して、東アジアのなかで有利な立場を築き上げるのか、という課題と向き合っていたのである」。
「宋による讃の安東将軍・倭国王への冊封は、倭国が東アジアという国際舞台で高句麗・百済とようやく同じ土俵に上がったことを意味する。それは緊張が増していた東アジアの国際関係を熾烈化させるものであった」。
「438年4月、讃の弟の珍が宋に到来し、讃が死んだことを伝えてきた」。
「(5世紀の古市古墳群と百舌鳥古墳群の並行的な存在は)大王となり得る王族集団が2つあったということである。当時の倭国において大王を輩出する一族は倭姓を名乗る集団として勢力を保ったが、その内部には有力なグループが複数存在していた。5世紀前半には讃と珍がリーダーとして立っていた讃系王族集団があったが、それとは別に讃系に匹敵する王族集団が存在し、そのリーダーとして倭隋がいたのである」。
「倭国は443年に宋に遣使してきた。ところが、使節を派遣してきたのは珍ではなく倭済という名の王であった。この時点で珍は死去して国王が交代したことになる。・・・しかし、珍から済への王位継承には大きな問題が横たわっている。それは、少なくともこの2人の間に近親関係は見出しがたいことである。『宋書』倭国伝には、讃と珍が兄弟であることは明記されているが、珍と済の続柄は記されていない。済は倭姓を名乗っていることからすれば、それまでの倭国王と同族だったことは間違いない。だが、宋に対して珍との続柄を名乗らなかったことから、珍との血縁関係はそれほど近いものではなかったことが推測できる。それは、讃・珍の兄弟で継承した倭国王位がその近親には引き継がれなかった可能性を示唆している」。『日本書紀』の記事から、5世紀には王位継承を巡る王族同士の抗争が繰り広げられていたと、強く推測されるというのだ。
「済にとって、朝鮮半島南部の軍権について宋の承認を得たことは外交的成果と受け止められただろう。しかし、現実の東アジアの情勢は混沌として緊迫の度合いを増していく。450年の北魏による南征によって、中国における北魏の優位は確立したといってよい。しかし、すぐに宋を滅ぼすことにはならなかった」。
倭や朝鮮半島諸国が頼りにしてきた親分格の宋自体が、ここに来て、大きく揺らいできたのである。
「(宋の弱体化に拍車がかかる中)462年に倭国の使者が宋にやってきた。済の『世子』と称する興が、済の死去を伝えたのである。済は20年弱にわたって倭国に君臨していたことになる」。「興が世子を名乗って使節を派遣したことは、興は国内で即位が容易に認められない政治的事情を抱えこんでおり、そのような状況を打破するために宋に遣使したことを示唆している」。
「興の次に宋に使節を派遣した武について、『宋書』倭国伝は興の弟と記している。また武の上表文には、武が済を『亡考』(亡父)と記すことから、興が済の子であったことは間違いない」。「478年の武の遣使の目的はそれまでと同じように、冊封を受けて官爵を授かることであった」。「武は遣使にあたって長い上表文を宋の皇帝宛に送っている。『宋書』倭国伝によって伝えられているが、それは5世紀後半の国際情勢を考えるうえで見過ごせない重要な史料である」。「上表文は高句麗との対決を大きな主題としている。それは武だけの問題ではなく、五王歴代の外交的課題であったことを強調している」。「武の上表文は事実をそのまま記したものではなく、目的に即して改変した。また、その文章表現は古典の文言を駆使したものであった」。
「468年以降の高句麗と新羅・百済の抗争は、百済と結びつく倭国にも強い危機感をもたらした。高句麗の南下によって、鉄をめぐる倭国の権益が侵犯されることが予想されるからである」。
「高句麗南下の阻止は、倭国の朝鮮半島における利権を守るためにも差し迫った外交課題である。高句麗と正面から対決してきた百済は弱体化しており、それまでと同じような役割は期待できない。それゆえ高句麗との対決は、倭国が盟主となって実行することが現実的な情勢であった。478年の武の官爵要請はこれらの国際背景のもとに行われた。そのためには高句麗に匹敵・凌駕する官爵を獲得する必要があった。また配下の王族・豪族にも将軍号を授与することによって、王としての地位を確固たるものとし、さらに高句麗征討に対する支持を取り付けようとした。上表文は当時の外交課題と国内の権力構造を端的に示している。それは讃以来、変わるものではなかった」。
「名前あるいは系譜から倭の五王の実体について迫ることはきわめて難しいことを説明してきた。そもそも『宋書』倭国伝と(古事)記・(日本書)紀をすり合わせること自体、あまり生産的な作業とは思えない。5世紀の倭王権の実態を考えるためには、異なる視角からアプローチすべきである」。「天皇系譜は5世紀以来、政治的変動や歴史書の編纂のなかで追加や削除が繰り返されてきたものである。それをふまえずに誰に当てはめるかを議論しても、それは実りある結論を生み出すことはない。倭の五王は、記・紀に拘泥せずにひとまずそれを切り離して5世紀の歴史を組み立ててみる作業が必要なのであり、本書はそのための露払いである」。本書は、この役割を十分に果たしている。
「宋との外交の目的は官爵の授与にある。授与された官爵は、国内的には将軍号の再分配や府官制という仕組みとして倭王権の権力強化に利用され、対外的には百済や高句麗との競合の際の地位として意味を持っていた。逆にいえば、外交をやめることは、中国官爵を授からなくなるということであり、倭国王として列島に君臨し、東アジアに臨むための手段を放棄することであった。それは倭の五王が一貫して構築してきた権力のあり方に変更を迫るものであった」。
倭の五王が宋との外交を重視したのは、宋皇帝と君臣関係を結ぶことによって、国内の王族・豪族に対して倭国王としての優越的な地位・権力を保証しようとしたためであった。同時に、宋を後ろ盾として、貴重な鉄の供給先である朝鮮半島での権益を守ろうとしたのである。すなわち、五王の外交使節派遣は、国内対策と国際対策の両面からなされたというのが、著者の結論である。この結論は、強い説得力を有している。



