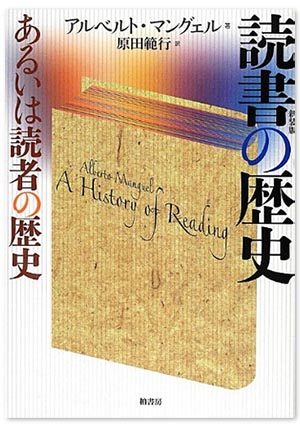
カフカが寓話的な小説を、紫式部が『源氏物語』を書いた真の理由
敬愛する松岡正剛が『千夜千冊エディション 本から本へ』(松岡正剛著、角川ソフィア文庫)の中で、『読書の歴史――あるいは読者の歴史』
(アルベルト・マングェル著、原田範行訳、柏書房)を「これはものすごい本である。どのくらいすごいかを説明するのが息苦しいほど、この手の本ではダントツだ。類書はとうてい及ばない。いや、類がない」と破格に評価しているからには、読まないではいられない。
分厚い本書の中で、私は、松岡が指摘した●「カフカの読書法こそがカフカ文学の謎をとく鍵だというベンヤミンの見方のどこに限界があるかということ」を論じた箇所、●「紫式部に注目して、これを『壁に囲まれた読書』というふうに仕立てた章」、加えて、●アメリカ南部で文字を学ぶことを禁じられた黒人奴隷が密かに努めたエピソード――の3つに注目した。
「ヴァルター・ベンヤミンは、その優れた論文において、カフカの世界観を理解するためには、『カフカの読書法というものを念頭に置かなければならない』と示唆している。彼は、カフカの読書法を、ドストエフスキーのアレゴリカルな小説『カラマーゾフの兄弟』に登場する大審問官のそれに準えている」。
「カフカは、まさに字義通りにも、アレゴリカルにも、政治的文脈においても、心理学的側面からも読まれ続けているのである。解釈はそれを生みだすテクストの数をはるかに上回るとよく言われるが、しかしやはり、全く同じページを読んでも、ある読者は意気消沈し、別の読者はこれを笑い飛ばせるという事実は、読書という行為が持つ創造的な性格を如実に示しているのではあるまいか」。
「彼のさまざまな読書経験を養分とするカフカの作品が、読者に対して作品を理解できたという錯覚を与えつつ、同時にこれを奪い去るものであることは確かである」。このマングェルの指摘は、非常に重要である。私自身も、カフカのアレゴリカル(寓話的)な諸作品は、読者にカフカの言いたいことは何なのか、寓話的に何を意味しているのかをあれこれ考えさせるだけ考えさせて、その答えは最後まで明らかにしないことを目論んでいたと睨んでいるからだ。
マングェルや私の考えが的を外していないことは、マングェルが引用したカフカの告白からも明らかである。「1904年、友人オスカー・ポラックに宛てた書簡の中で、カフカは次のように語っている。『要するに私は、読者である我々を大いに刺激するような書物だけを読むべきだと思うのだ。我々の読んでいる本が、頭をぶん殴られた時のように我々を揺り動かし目覚めさせるものでないとしたら、一体全体、何でそんなものをわざわざ読む必要があるというのか? 君が言うように、我々を幸福にしてくれるからというのか? おい君、本などなくても我々は同じように幸福なのさ。我々を幸福にしてくれる本なんて、困った時に自分たちで書けばよい。本当に必要なのは、ものすごく大変な痛々しいまでの不幸、自分以上に愛している人物の死のように我々を打ちのめす本、人間の住んでいる場所から遠く離れた森へ追放されて自殺する時のようなそんな気持ちを抱かせる本なのだ。書物とは、我々の内にある凍った海原を突き刺す斧でなければならないのだ、そう僕は信じている』」。
「ある特定の読者自らの手によって、いわば隔離された読者のための読み物が入念に創造されることもある。11世紀、日本の宮廷女性の間で生まれた文学作品がまさにそれだ。・・・宮廷の女性たちは、もちろん、より低い階層の女性たちに比べれば多くの特権を与えられてはいたが、それでもなお、多くの規則や制限に甘んじなければならなかった。彼女らは、外界から閉ざされ、決まりきった単調な生活を送らなければならなかったし、使う言葉も限られていた。だから宮廷女性たちは、さまざまな規制の網をかいくぐって、自分たちの生活している世界とその障子の外の世界とを探索し読み取るための巧みな方法を、自ら編み出していかなければならなかったのである。・・・彼女たちが当時最大級の文学作品を創作したこと、そしてその過程で、それこそ新しい文学ジャンル自体が生みだされたことは、まことに驚くべきことである。・・・自分たちの読み物を増やすため、そして本当に夢中になって自分たちが読めるような読み物を自由に得られるようにするため、女性自ら文学作品を創造していったのである」。
「かつてヴァルター・ベンヤミンは、『書物を獲得するあらゆる手段の中で、書物を実際に執筆することが、もっとも賞賛すべき方法である』と述べたことがある。平安時代の女性のような場合は、それが唯一の方法なのであった。自ら考案した新しい言語を用い、彼女たちは日本文学史上、不朽の名作のいくつかを残したのである。とりわけ最も有名なのは、紫式部による記念碑的作品『源氏物語』と清少納言の『枕草子』であろう」。
自分たちが読んで楽しむべき書物が存在しなかったから、紫式部や清少納言は男性が使わない仮名を用いて、自ら文学作品を書いたのだという指摘は、説得力がある。
「文字を読むことについて、アフリカ系アメリカ黒人たちは、何世紀もの間、ほとんど不可能と思われる状況にもかかわらず、なんとかこれを修得しようとしてきた。さまざまな困難から、自分の生活を危険に晒すこともあった。だが彼らの文字学習に関する逸話は少なくなく、また英雄的でもある。1930年代、かつて奴隷であった人々の個人的回想などを記録しておく目的で、連邦書記計画が推進されたが、このインタヴューに答えて、90歳になるベル・マイヤーズ・カラザスは、かつて彼女が、農園の所有者の赤ん坊の世話をしながら文字を覚えたことを打ちあけている。この赤ん坊はアルファベットの書かれた積み木で遊んでいた。だがこの所有者は、カラザスもまたこの積み木で文字を覚えているところを目撃すると、即座に彼女を足蹴にしたという。結局自分は、子供が書く文字から、見つけだした綴り字教本の中のいくつかの言葉から、密かに文字を学んでいかなければならなかったと、彼女は繰り返し語っている。・・・アメリカ南部では、仲間に綴りを教えようとした奴隷が、農園の所有者によって縛り首にされることさえ一般的であったという」。自由に文字を学ぶことができ、自由に本を読むことができ、自由に読む本を選択できる私たちは、いかに恵まれているかに思いを致そうではないか。



