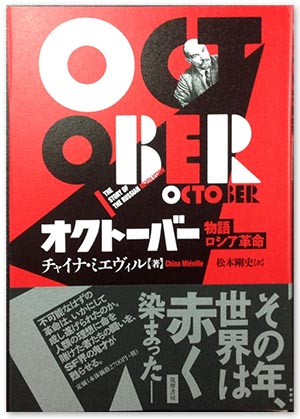
ロシア革命から100年を超えて、世界はその後革命の理念を食いつぶしての現在なのか、それとも革命は欺瞞だったのか?そんなことをかんがえる日々である。読んでみた、ロシア革命の物語。
『オクトーバー:物語ロシア革命』チャイナ・ミエヴィル著、松本剛史訳を読む。
昨年がロシア革命100年で、それに関する本が出るかと思っていたのだが、数冊研究書の類が出版されて、購入してみたがはっきり言って面白くなくて、途中で放棄してしまった。この本は副題の通り物語として書かれているのだが、筆者があとがきで書いている通り、いわゆるフィクションとして存在しなかったことは書いていないという。それならノンフィクションなのかと云えば、それとも違う。そもそも歴史Historyの後ろ半分はStoryだということは、後の世にに物語ることが歴史であるし、事実と事実をつなげることが物語でもあることは今や常識である。本書はその意味で歴史書としても十分に読めるのだが、主な登場人物55人、その他名前の確認できない者多数。その上、それぞれの集団の名前が飛び交い、もう混乱の極みであるが、その中から浮かび上がるロシア革命の実体はまさにこんなな中から瞬間に浮かび上がった夢の実現であったことに胸が熱くなるのである。
本書の中心は1917年の1年間であるが、そこに至る前史も確かに書かれてはいるが、あくまでも前史に過ぎないのは、1917年に登場する主要人物たちの多くは亡命中であったり、流刑されていたりする。彼らが何も役割を果たさなかったとは言えないが、現在のように電信電話が発達している当時ではないから、レーニンはスイスに、トロツキーはアメリカにいるというわけで、彼らの指導力がロシア国内に影響を与えたと言うのは後世に創りだされた物語にすぎない。それほど国内は自主自立、それぞれがわらわらと動きだして、10月に至る過程が良く分かるのである。
レーニン、トロツキー級の知識人、革命家はしかしながら、政治情勢を理論的に理解し、そこから革命への道を作り出そうとするのであるが、結論から言うと、多くの場合は理論は民衆の力によって乗り越えられて行くのである。1年間の対決軸はケレンスキーの臨時政府との駆け引きなのであるが、ケレンスキーという人物はともかく権力を掌握するために常に右左の中間に軸足を置いている、身振りだけは大仰な人物だったようだ。
しかし、レーニン、トロツキーにしても当時、革命はマルクス理論の2段階革命理論であり、ブルジョワ革命がまずなされたさきに共産主義革命があるというドグマから抜け出していない。かといってアナキストすら、ドイツとの戦争への対応は国内防衛を求めると言う点で、敗北的であれ終戦を求める姿勢は取れなかった。この2つの要素のからみあいから最右翼ブルジョワから左へ向かって、メンシュビキ、メンシュビキ左派、ボルシュビキ、ボルシュビキ急進派、エスエル、などがソヴィエトを臨時政府に対置させて、権力を掌握するために動きまわっているというのだが、7月の時点でレーニンらはケレンスキーに破れている。その責任はレーニンらが二段階革命論から抜け出せず、左からの力、たとえばクロンシュタット水兵らの圧力や農民たちの生の叛乱の力を抑え込む行動に出ていたことや、当時レーニンはドイツのスパイだと言う反革命派のプロパガンダに屈したと言うことが挙げられるようだ。この時点ではトロツキーも又レーニンよりもさらに右寄りであった。破れたレーニンの逃亡は10月まで続いて、つまり決定的な局面でレーニンの果たした役割は本当にあったのか?と疑問に感じてしまうほどである。
こんな流れの中で、女性たちの動きは理論とは別次元で一層さわやかで動かし難い要求を突き付けている。たとえばスモレスク地方のロスラヴリの街頭でストを打った婦人帽子作りの職人は大半がユダヤ女性で、1905年以来戦闘的であった。彼女らの要求は1日8時間労働、賃金の50%増額、週休2日制、有給休暇を要求している。またケレンスキー政権下の大会の4分の1は女性であった。またムスリム女性も中にはいた。エピソードとして書かれていて笑える話もある。
レーニンが逃げた時の変装であるが、はげ頭をかつらで隠し、顔中包帯を巻いて傷兵をかたったそうで、当時前線の兵士の逃亡で戦線維持がほとんど不能になっていた事と共に、兵士が逃げることは止めようのない事態になっていてその兵士の増大がソヴィエトの判断を左へ引きずっていたともいえるから、ケレンスキーの守備隊すら兵士には手出しが出来なかったということなのかもしれない。
なぜこんなことが事実として残っているかと云うと、かつら屋のおやじが、だいたいかつらを買う人物は若く見せるために買うのに、この人物だけが老人にみせるためのかつらを買ったと言うことを書き残しているからだそうだ。そんことはまーどうでもいいのだが、本書で印象的なことはレーニンは文書主義で彼がいわゆる重要な文書を書いているのだが、多くは実は時勢に遅れていて、賛成を得られないことが多々あった。
たとえば「すべての権力をソヴィエトへ」というスローガンは過激化する民衆に乗り越えられてしまうのだが、そのソヴィエト自体が民衆の力を受け入れない状況下で、このスローガンの優柔不断ぶりに気付いていたのはレーニンではなくて民衆の方であったということのようだ。
レーニンは7月の蜂起の失敗後このスローガンはこうあるべきだったと語っている。
「すべての権力を、革命を担う党、すなわちボリシュビキが率いるプロレタリアートに」。
もうひとつ印象的であったのは、いろいろの時点での決定が参加者の投票で行なわれていたと言うことである。その数は多いときは500人を超えるし、最低では5人という場合もある。そのことが穏健派、中間派の数によって決定的なことが決まらなかったということはあるが、それでもしだいに急進派が力を得たことは間違いなく、その間、結局は民衆の力量が急進かしていったし、それを反映する人物たちが乗り越えられて言っていることを認識した結果の10月革命であったといえるだろう。
それにつけてもトロツキーはここぞと言う時にはアジ演説がさえている。それも少し前にはかなりあいまいであったスタンスを大衆を前にして演説がうまかったことは事実のようだ。それに対してレーニンは多くの国民の期待を背負っていて、ほとんどが勝負がついてしまった時に出て来ると言うなんかやたらにいい役どころなのだ。レーニンは10月最終段階で次のような声明を出した。
「ロシア市民に告ぐ。臨時政府は打倒された。国家権力はペトログラード労兵代表ソヴィエト、軍事革命委員会の手に委譲される。後者はペトログラードのプロレタリアートと守備隊の上に位置する機関である。
人民が拠りどころとして闘ってきた大義――民主的平和の即時提案、私的所有地の没収、労働者による工場管理、ソヴィエト政府の創設――その大義が勝利によって保証された。
労働者の、兵士の革命に万歳」この声明はキリル文字で印刷され、ポスターとして張り出された。しかし、実際はこの内容は実現されたものではなかった。願望だった。革命はなったのであろうか。10月以降、ロシアが直面した多くの問題に後退を余儀なくされた。そしてレーニンの死とスターリンの登場によって革命は一党独裁のおそるべき堕落へと雪崩を打って落ちて行く。巻末に挙げられている主な人物の多くがスターリンによって粛清と云う文字に戦慄する。
本書の作者はこう書いている。
「1917年のロシアで起こったことは、すべて明瞭なかつ重要だ。10月をただのレンズとみなし、それを通して今日の苦闘をながめるのは、不合理で滑稽な近視眼だろう。しかしあれから長い1世紀が、恨みと残虐の長い薄暮が、異常な生成物と本質から成る時間があった。薄明は、たとえ記憶のなかにある薄明でも、光がまったくないよりはましだ。あの革命から学べるものは何もない、というのもやはり不合理だろう」
「たとえば10月は、新しい種類の力をもたらす。労働者による生産の掌握へ、土地に対する農民の権利へと向かう変化。労働や結婚における男女平等の権利、離婚や子育て支援の権利。100年前にあった同性愛への差別撤廃。民族自決への動き。自由な普通教育、識字の普及。識字とともに生じる文化的な爆発、学習欲。大学や連続講座や成人対象の学校の急激な発展。・・・・工場での変化に劣らぬほど大きな魂の変化・・・」
革命によって表現された世界観は、今の私たちの社会で再び革命を起こすべき主題になっていることを感じないであろうか?夢ではなかった革命の一歩を今こそもう一度、後退してしまった地点から歩み出そう。夢を見ないで闘いは出来ないから。
魔女:加藤恵子



