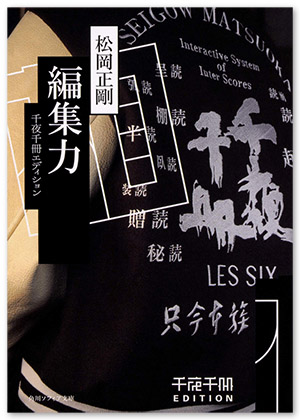
松岡正剛の「曼荼羅的好奇心」と「数寄三昧的編集力」の妖しく底知れぬ世界
『千夜千冊エディション 編集力』(松岡正剛著、角川ソフィア文庫)を読んで、松岡正剛の幅広く、かつ奥深い「曼荼羅的好奇心」と「数寄三昧的編集力」を再認識させられた。
本書は、「意味と情報は感染する」、「類似を求めて」、「連想、推理、アブダクション」、「ハイパーテキストと編集工学」の4章で構成されている。いずれも読み応えのある書評ばかりだが、私の「曼荼羅的好奇心」と「数寄三昧的編集力」を好き勝手に行使して、敢えて、それぞれの章から一冊だけを選び出すという暴挙を試みた。
「意味と情報は感染する」の章で注目したのは、「『数寄のパサージュ』という方法 文化の敷居をまたいで『アウラ』を感じる」ヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』である。
「ベンヤミンはパリのパサージュ(回廊型のアーケード)に世界モデルを見いだし、そこに込められ、そこから導きだしうる言説と思想を厖大に並べ、組み立て、編集してみせたのである。・・・パサージュはたんなるアーケードなのではない。たんなる空間でもなく、たんなる店の並びでもない。ベンヤミンにとってのパサージュとは移行者であって街路者であり通過者なのである。境界をまたぐ者になることである」。
「ベンヤミンにとっては情報の『配列』と『布置』こそがすべてであって、そこから何が抽出され、そこに何が引用されたのか、それを編集できるかどうかが最大の問題なのである。個人とはその抽出と引用の代名詞であったのだ。このことが示唆する意味は、ベンヤミンが若いころから書物を偏愛し、それ以上に装幀に稠密な好奇心をもっていたことにあらわれている。ベンヤミンにとって書物とは、それが見えているときと、それが手にとられるときだけが書物であったからである。その書物の配列と布置と同様に、ベンヤミンには都市が抽出と引用を待つ世界模型に見えたわけだった」。ナチスから逃れるため、ピレネーの山中で服毒自殺したベンヤミンが、熱心に集めた膨大な材料をどう料理(編集)したのか知りたいと思うのは、私だけではないだろう。
「類似を求めて」の章では、「認識の中の『暗黙知』に気がつく方法 アート、スキル、レリバンスが『不意の確証』」を論じたマイケル・ポランニーの『暗黙知の次元』である。
「発見は、現行の知識が示唆する探求可能性によってもたらされることが多い。しかしながら、その発見への手続きには予想のつかなかったことや検証しにくいことが交じっていることも少なくない。マイケル・ポランニーはそれを『暗黙知』と名づけた。暗黙知とは意識の下のほうにあるために取り出せなくなっているぼんやりした知識のことをいうのではない。下意識に隠れ住んでいる知のことではない。どうも一部の経営学者たちがそういう見方を広めたようで、誤解が広まった。・・・そうではなく、ポランニーの言う暗黙知とは科学的な発見や創造的な仕事の作用に出入りした知のことなのである。思索や仕事や制作のある時点で創発されてきた知が暗黙知なのだ。端的に言うなら創発知とか潜在知とか、さらにわかりやすくしたいのなら暗黙能とか潜在能と見たほうがいいだろう。ポランニーにとっての暗黙知は『方法』そのものなのである。知識に方法が従属するのではなくて、方法そのものが知識であるような、そのような脈絡が知識にひそんでいることを提言したのである」。ビジネスの世界に長く身を置いてきた私は、経営学者の「暗黙知」とポランニーの「暗黙知」が異なることを、本書によって初めて知ったのである。
「発見に必要なこと、とりわけ科学的発見に必要なこととは何かという問題だ。いくつもの事例を検討してポランニーがそこに見いだしたのは、推測するためのアート(技芸)感覚、未知のものを見るスキル(技能)、それが妥当である(レリバンス)と判断する標準性、この3つであった。アート、スキル、レリバンスとは、いいかえれば推理を進める方法、未詳に分け入る方法、妥当性に気がつく方法ということになる。ポランニーはこの3つが交差して発見の歯車になっていると考えた。・・・ある個人の知識の総体のなかでその知を新たな更新に導くものは、その知識にひそむ方法知ではないかということなのである。その方法知がアート、スキル、レリバンスで組み立てられていると見たのだ」。
「連想、推理、アブダクション」の章では、「『探偵が推理する』という方法 チャールズ・パースふうの『二十の扉』がすばらしい」トマス・A・シービオク&ジーン・ユミカー・シービオクの『シャーロック・ホームズの記号論』である。
「チャールズ・パースという知の巨人がいた。ある学者によると、『アメリカが生んだ最も独創的で、最も多彩で、しかも2位以下に大きく水をあけた唯一無比の知性』だといわれている。・・・そのパースには『探偵』としての才能もあった。シービオクはそこに目をつけて、パースをシャーロック・ホームズに準えた。これは炯眼だ。パース攻略には搦め手が必要であるからだ。ということはシービオクもパースに匹敵して、なかなか隅におけない探偵だということなのである」。
「重要なのは『問いを言葉にする』ということ、そのたびごとに『次の選択に進む』ということである。それによって推理のオプションが次々に狭ばめられ。また広がっていく。『二十の扉』はその組み合わせによって、当人の思考のプロセスをみごとに浮き上がらせる。・・・仮説形成とは、この問いを『二十の扉』のように適確に続けることにあたる。科学も論理も人々の日常生活も、そしてシャーロック・ホームズのすばらしい探偵術も、この仮説形成によってのみ、すなわち推感編集によってのみ成り立っている。これがパースの思想の中核にある特色である。アブダクションというものの骨格だ」。
「コナン・ドイルは医者だったのである。ドイルはやがてエジンバラ王立病院の実在の医者ジョーゼフ・ベル博士をモデルにして、探偵シャーロック・ホームズを仕立てあげた。探偵小説にするにあたっては、原型としてポオの『モルグ街の殺人』のデュパンがいたが、デゥパンが数学的で詩的であるのに対して、ドイルはホームズをずっと臨床医学的に、論理的に、そして推感編集的につくりあげた。そこが自分も医者だったコナン・ドイルの自慢だった。しかしホームズが最もホームズ的であるのは、シービオクによれば、ホームズがつねにパースのいう『最善の仮説を選ぶ』という原則に従っているときなのだ。シャーロック・ホームズこそは『二十の扉』の発案者なのである」。これにヒントを得た、かつてのラジオ人気番組「二十の扉」を聞いたことがあるかと、女房に尋ねたところ、そういう番組は知らないという回答。ああ、昭和は遠くなりにけり。
「ハイパーテキストと編集工学」の章では、「『想像力の触発連鎖』をおこす方法 『比喩』『ごっこ』『対発送』がイメージ編集力を刺戟する」キエラン・イーガンの『想像力を触発する教育』である。
「すぐれた先例はある。すぐにルドルフ・シュタイナーのヴァルドルフ教育や、『心理学のモーツァルト』と言われた夭折の天才レフ・ヴィゴツキーの模倣と協同を重視した教育観が思い浮かぶ。想像力をいかした学習仮説は群を抜いていた。二人がそもそも独創的で、イマジナティブな教育者だったのである。おそらくイーガンもシュタイナーやヴィゴツキーの影響を受けたと思われる」。
「(イーガンが)次の15の視軸で子供たちに『想像力に富む学習の触発』を試みているのが、断然にすばらしい。こういうものだ。①できるかぎり『物語』を重視する。②柔らかい『比喩』をいろいろ使ってみる。③何でも『いきいき』としているんだという見方をする。④とくに『対概念』に慣れてイメージを膨らませる。⑤『韻』と『リズム』と『パターン』に親しんで、さまざまな言葉になじむ。⑥『冗談』や『ユーモア』で状況がわかるようにする。⑦内外の『極端な事例』や『例外』に関心をもつ。⑧ふだんの『ごっこ遊び』はとことん究める。⑨自分の『手描き』のイメージで何が描けるかを知る。⑩『英雄』とのつながりを感じられるようにする。⑪身の回りにも世界にも、いったいどんな『謎』があるのかという関心をもつ。⑫どんなことも『人間という源』に起因すると知る。⑬好きな『コレクション』と『趣味』に遊べるようにする。⑭事実にもフィクションにも噂にもたえず『驚き』をもって接する。⑮想像力を育む認知的道具の大半は『日々の生活』のなかにある」。日本の小中学校でも、この15の触発法を活用してもらいたいものだ。
「イーガンは、『 』内のそれぞれのアイテムすべてをヴィゴツキーに従って『認知的道具』と捉えている。『物語』も『ごっこ遊び』も『コレクション』も、想像力を触発するための認知ツールなのだ。この言い方も、とてもいい。・・・こういう道具を臆せず提案したイーガンに敬意を表したい。これらは成人の学習にとっても必須なのである。大人こそ想像力が麻痺している」。
松岡の書評のいずれもが、内容が高度なだけでなく、方法が演繹的、帰納的、推感編集的と縦横無尽、自由自在なので、私の貧弱かつ粗雑な頭脳は爆発寸前である(笑)。



