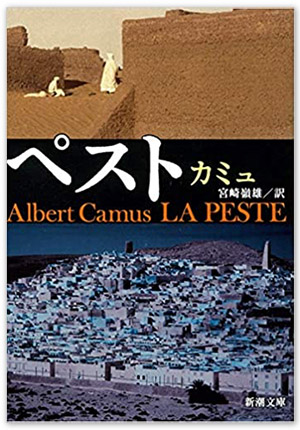
ペストいう不条理に直面した人々は、どう行動したか。そして、その死の荒野から拾い上げられたものとは――
人間は、重大な局面に立たされたとき、どう行動するか。アルジェリアのオラン市が、ペストという死の病に襲われたとき、医師のリウーは、どう行動したか。数週間前にオランに居を定めたばかりの冷静な若き観察者・タルーは、どう行動したか。市の臨時補助吏員・グランは、どう行動したか。老医師・カステルは、どう行動したか。新聞記者のランベールは、どう行動したか。神父のパルヌーは、どう行動したか。予審判事のオトンは、どう行動したか。犯罪者のコタールは、どう行動したか。著者カミュによる、その実験の記録が、『ペスト』(アルベール・カミュ著、宮崎嶺雄訳、新潮文庫)である。
自分の信念に基づき、敢然とペストに立ち向かった人々がいる。一方で、信念が揺らいだ者たちがいる。ある者は、すこぶる困難な状況の中で、自分にできることに力を尽くした結果、ある者はペストに斃れ、ある者は生き延びる。
ランベールは、パリに残してきた恋人に会うためオランからの脱出を試みるが、リウーやタルー、グランの献身的な行動を目の当たりにして、オランに留まり、ペスト患者のために組織された当局抜きの志願制の保健隊で働くことを決意する。
パヌルーは、「ペストは神が邪な者たちに与えたもうた罰だ」と説教していたが、オトンの罪のない幼い息子がペストに命を奪われるのを目にして、その堅い信仰も大きく揺らぐ。
この10カ月に亘った忌まわしく禍々しい実験の結果、惨憺たる死の荒野から、著者が辛うじて拾い上げたものがあった。それは、「誠実」と、「共感」と、「連帯」であった。
「絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いのである」。
「自分一人が幸福になるということは、恥ずべきことかもしれない」。
「ペストと生とのかけにおいて、およそ人間がかちうることのできたものは、それは知識と記憶であった」。
カミュは、33歳の時、『ペスト』で作家としての地位を確立し、44歳という若さでノーベル文学賞に輝き、46歳で交通事故死してしまう。
本書で描かれているのは、ペストという人間性を蝕む不条理だが、私たち読者が、このペストを、死やペスト以外の病、戦争、ナチスに代表される全体主義などに置き換えて読むこともできる、そういう奥行きの深い作品である。



