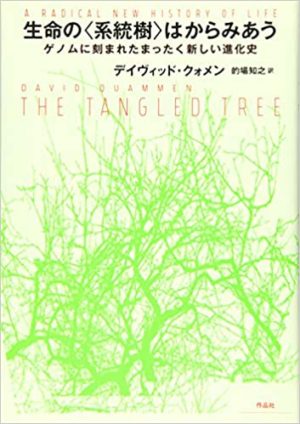
情熱的読書人間・榎戸 誠
生物進化の基本概念がどのように覆されたのかを知ろうとするとき、『生命の<系統樹>はからみあう――ゲノムに刻まれたまったく新しい進化史』(デイヴィッド・クォメン著、的場知之訳、作品社)が、親身になって手引きしてくれる。
本書の魅力は、3つにまとめることができる。
第1は、進化を考える上で衝撃的なサプライズとして、①それまで一切知られていなかった、全く新しいカテゴリーに属するタイプの生物、アーキアの発見、②完全に想定外だった、遺伝子の水平伝播という変異を継承する現象の発見、③40年前には存在することさえ知られていなかった、ヒトの最古の祖先と考えられる生物の発見――の3つに焦点が絞られていること。
「アーキアは長いあいだ、細菌の下位区分と誤認されていた。その発見と分類により、微視的スケールでみた生物世界は、それまで科学者が思い描いてきたものとはまったく違ったものに生まれ変わり、生命の黎明期の歴史は書き換えられた。遺伝子の水平伝播が普遍的な現象とわかったことで、遺伝子は親から子へ垂直に受け継がれるだけで、種間の壁を越えて『横流し』されることはないという、これまでの常識は覆された。アーキアにまつわる最新ニュースは、すべての動物、植物、菌類、そして核内DNAを備えた細胞をもつその他の複雑な生物は、わたしたちヒトも含めて、みなこの奇妙な太古の微生物の子孫かもしれないということだ。その衝撃は、リトアニア生まれだと思っていた自分の曽々々祖父が、実は火星人だったと知ることに等しい」。このユーモアは秀逸だ。
「これら3つのサプライズが合わさって、ヒトのアイデンディティ、個性、健康にまつわる謎が深まると同時に、重要な洞察が得られた。わたしたちは、これまで思っていたような存在ではなかった。わたしたちは生きものの複合体だ。わたしたちの起源は、生命世界の日陰者で、数十年前は科学者でさえ存在を知らなかった生物の一系統にあった。進化は、かつて考えられていたよりも、はるかにトリッキーで複雑だった。生命の樹は混沌の度合いを増した。遺伝子は垂直にだけ移動するわけではない。それは平行に、種の壁や、それよりはるかに深い断絶を超え、生物分類における界さえもまたいで移動する。わたしたちを含む霊長類の系統にも、思いがけない別系統からの遺伝子が紛れ込んでいる。いわば輸血の遺伝子版、あるいは感染によるアイデンティティの変貌だ」。
すなわち、これまで、垂直方向に、単純に枝分かれしたものと考えられてきた生命の系統樹は、実は、縦横無尽に複雑に絡み合う網の目のようなものだったというのである。
第2は、試行錯誤しながら進化の解明に貢献してきた研究者たちの人間ドラマが、臨場感豊かに描かれていること。
1977年にアーキアを発見したカール・ウーズ、1967年に細胞内共生説を甦らせたリン・マーギュリス(最初の夫はカール・セーガン)、1999年に、ウーズやマーギュリスやその他の多くの研究者たちの分子系統学研究を統合して、遺伝子の水平伝播と、絡まり合った網状の生命の樹を提唱したフォード・ドゥーリトル――主役級のこの3人の生き方は、とりわけドラマティックである。
生物は細菌、アーキア、真核生物の3ドメインで構成されていることを主張したウーズ――。
「(1990年に発表されたウーズ、カンドラー、ウィーリスの)論文の最後の力点、それは3ドメインの名称であり、細菌、真核生物、そしてアーキアと呼ぶ。古細菌という単語はここに葬るべきだと、ウーズらは主張した。原核生物も同じく消滅せねばならない。原核生物はひとつの系統学的カテゴリーとしては存在しえない、まちがった単位だ。アーキアと細菌は、根本的に異なる存在なのだから。そしてもちろん、そこには樹があった。まっすぐでシンプルな線で描かれてはいたが、その内容は豊かで挑発的だった。1987年の根のない樹とは違い、この図には根があった。日本の(渡邊力らの)研究チームが新たに開発した、ある複雑な手法を用いることで推定が可能になったのだ。樹の幹は単一の起源から垂直に伸び、そのあと2つの主枝に分かれ、そのうち一方がさらに分岐している。左の主枝は細菌。右の主枝はアーキアと真核生物だ。・・・わたしたちヒトや、その他すべての動物、すべての植物、すべての菌類、すべての真核生物は、1977年以前には科学界にまったく知られていなかった祖先系統から生じた。それは最後の古典的な大系統樹だった。正統で、核心に迫っており、斬新で、ある程度は正しい図だった。しかし、この図は次に訪れる変化を、まったく捉えていなかった」。
分子系統学の成果を統合したドゥーリトル――。
「彼(ドゥーリトル)はこの図を『網状の樹』と呼んだ。そこには伸長し、交差し、分岐し、収束する枝がこんがらかっていた。・・・ドゥーリトルのスケッチは、太いペンで手描きされた、白黒でどっしりした図だった。下層から全体的に絡み合っていて、マングローブの茂みのようだった。複雑だが優雅で、風変わりで、思わず吹き出しそうになる。・・・それでも、ドゥーリトルの2つめの図は、まだまだ単純すぎる漫画でしかなかった。複数の根本から複数の幹が立ち上がり、複数の主枝に分岐しているが、数はさほど多くなく、根本の正体は明示されなかった。矛盾をはらみ、細部が欠けていた。そのまま受け止められるよりも、想像力を刺激することを意図したものだった。その姿はどこからみても風変わりだった。もしかしたら、ドゥーリトルが文章とこの図で述べたように、生命の歴史をありふれた樹として描くことなど不可能なのかもしれない」。
進化の実態をバイオインフォマティクスで実証したエリック・J・アルム――。
「(2011年にMITの)アルムらはこう結論付けた――『(バイオインフォマティクスの)分析結果を総合すると、年代的に新しい遺伝子の水平伝播は、頻繁に大陸を越え、生命の樹を横断して、ヒトのマイクロバイオームを生態学的に構造化されたネットワークとしてグローバルにつなぎ合わせていることが示唆される』。簡単に言えば、わたしたちの体内でも、遺伝子は生命の樹の枝から枝へ、横に移動しているのだ」。因みに、バイオインフォマティクスとは、生命科学と情報科学を融合させた生命情報科学のことであり、マイクロバイオームは微生物叢を意味している。
「分子生物学者はいまや、『細菌が獲得した遺伝子の継承によって跳躍的に進化する』と知っている。ジャン・サップは、世に出ることのなかった(ウーズとの共著の)本の序章の草稿にそう書いた。これがダーウィンよりむしろラマルク的であることを、彼はよく理解していた。彼の頭にあったのは。遺伝子の水平伝播だ。跳躍的進化は細菌の専売特許ではなかった。動物も、時にはこのように進化する。それも、昆虫やヒルガタワムシだけではない。哺乳類にさえみられるのだ。『わたしたちの身体を構成する細胞は、典型的なダーウィン理論に従って、遺伝子の変異と自然淘汰を通じ、漸進的に生じたわけではない』。変化のいくつかは、飛躍的進歩だった。わたしたちはミトコンドリアを突然獲得した。遠い昔、真核生物、あるいは真核生物の前段階の系統に、細菌が取り込まれた時に。植物は葉緑体を同じように獲得した。わたしたちのゲノムはモザイクだ。わたしたちはみな、ヒトも含め、共生複合体なのだ。『もうひとつ考えてみてほしい。わたしたちヒトのDNAのかなりの部分は、ウイルスに由来する』と、サップは書いた。もっとも頻繁に引用される数字では8パーセントだ。ヒトゲノムの約8パーセントが、わたしたちの系統に侵入し(祖先の身体だけでなくDNAのなかにまで忍び込んだあげく)、残留した、レトロウイルスの残骸なのだ。アイデンティティの根幹において、少なくともわたしたちの12分の1はウイルスだ。この事実をよく考えるべきだと、サップは促した」。
第3は、分子系統学の専門的な内容を、文章と図で、私たちにも分かり易く、時にユーモアを交えて、解説していること。
本書に出会ったことで、今後、ダーウィンとラマルクを私の頭の中で、どう位置づけるべきか、頭の痛い問題が生じてしまったなあ。



