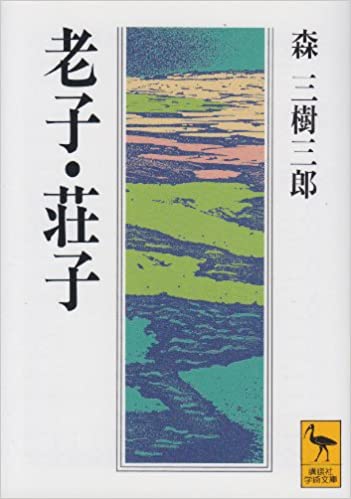
情熱的読書人間・榎戸 誠
『老子・荘子』(森三樹三郎著、講談社学術文庫)のおかげで、老子、荘子に対する理解を深めることができた。
「老子や荘子の、いわゆる道家思想も、戦国時代の中国人の、宗教的、哲学的関心を代表するものにほかならない。それは儒家や法家が政治的現実にたいする関心に終始するのに反して、永遠の世界や人生の問題についての省察に中心をおくものである。もっとも老子と荘子の間には、かなり顕著な相違があって、老子が政治的関心から出発して形而上の世界に歩を進めたのにたいし、荘子は最初から永遠の世界に突入しようとする。それだけに荘子のほうが、より哲学的であり、宗教的である」。老子と荘子を一緒くたにしてはいけないのだ。
老子――。
「老子の根本の立場は、いっさいの人為をなくして自然のままに生きるということであるから、無為自然という言葉によって表現される。それでは自然に反する人為とは、具体的にはどのようなものをさすのか。それは知識、学問、欲望、技術、道徳、法律など、いわゆる文明や文化とよばれるものの内容をすべてふくむものといってよい。それは人間の意識的な計量にもとづいて現われるものであり、人工的なものであるから、これを不自然なものとするのである」。
「それでは、そのように知識で理解できない真理は、何によって捕えることができるのか。それは体験的な直観によるほかはない。老子はそのような直観を『明』とよぶ」。
「知識や欲望を否定する老子は、また道徳をも否定する。孔子を始めとする儒家は、天下の荒廃を救うために仁義忠孝といった道徳の再建をはかった。ところが老子によれば、そもそも政治をもたらした元凶は、このような仁義忠孝の常識道徳なのであるから、これを復興することは、いよいよ混乱を増幅させるという逆効果を招くにすぎない」。
「戦国時代の諸子百家は、唯一の例外である墨子を除いて、すべて無神論の基調の上に立っていたといってよい。老子もその例外ではなかった」。墨子を除く諸子百家が無神論であったという指摘には、正直言って、驚いた。
「老子は小国寡民の理想郷の実現という政治の問題から出発し、ついで無為自然の政治、無為自然の人生の生きかたの問題に発展し、最後には無の形而上学に到達した」。
荘子――。
「人生にはさまざまな対立と矛盾がある。幸と不幸、富と貧、名声と汚辱、長命と短命、さては秀才に生まれるか、鈍才に生まれるか、あるいは美人に生まれつくか、不美人に生まれつくかなど、数えたてれば限りもない。これらのものは、ある程度まで人間の努力によって変えられるにしても、大部分は人力の範囲を越えたものである。なかでも死の必然は、人間である以上はこれを避けることができない。これらの人力を越えた必然性をもつものは。ふつう『運命』とよばれている。したがって万物斉同の立場を、人生の現実に密着させたばあいには、これを『人間の運命をそのままに肯定する立場である』といいかえてもよいであろう」。
「荘子の根本的な立場である無為自然、ないし万物斉同の説が、いかにして運命に結びつくのか・・・荘子の無為自然は、『人為をすてて必然のままに従え』といいかえてもよいことになる。もう一ついいかえれば、それは『一切のはからいをすてて、運命のままに生きよ』ということである」。
「およそ人間の背負う運命のうちで、死ほど強力で無慈悲なものはない。いかに運命を征服するなどと豪語するものでも、ひとたび死の運命の前に立たされたときには、自己の無力を思い知るほかはあるまい。死は人生にとっての一大事である。あらゆる宗教の出発点は死の問題であったといってよいほど、死のもつ意味は重大である。運命の肯定を説く荘子が、死の問題にたいして特に深い関心をよせたとしても不思議ではない。ただ死の運命はあまりにも強力なものであるだけに、さすがに荘子も万物斉同の原則論だけですますことができず、さまざまな角度から死の問題に接近しようとする。・・・特に注意をうながしておきたいことは、荘子が中国の思想家のうちで、死を正面から論じた最初の人であるということである。中国の思想家で死を問題にしたものは、きわめてまれである」。私は、哲学の最大のテーマは死であると考えているので、この件(くだり)を読んで、荘子に親近感を覚えてしまった。
「死を頂点とする運命の全面的な肯定を主張するという意味では、荘子はまさしく運命主義者であった」。
「自然は人為を排除するばかりでなく、神をも排除する。徹底した自然主義者、運命論者である荘子は、また同時に無神論者でもあった」。
「荘子は老子と同じく無為自然を根本としながらも、そこから万物斉同の説を構成し、無限者である運命のうちに包容されることを説く、独特な運命皇帝論に到達した。もちろんこれは荘子個人の体験と反省から生まれたものであるが、しかしそれは突然に出現したのではなく、じつは深く中国民族の運命観に根ざしたものであった」。
「同じ『荘子』の書のうちでも、内篇は荘子の自著、ないしはそれに近いものであるのにたいして、外篇・雑篇は荘子の後継者たちによって書きつがれたと見られる。荘子の後継者たちは、人間性の内にある自然を発見し、その説を展開していったが、そのため、しらずしらずのうちに荘子本来の絶対無差別の立場を忘れ、内と外、我と物との相対差別に陥ったといえよう。思想の世界では、いつでも進歩があるとは限らず、変質や堕落もありうるのである」。この指摘に嬉しくなってしまった。釈迦没後の仏教も。イエス没後のキリスト教も、釈迦、イエスの教えからの変質、堕落と、私は考えているからである。
老荘思想のその後――。
「六朝時代以後の老荘思想は、道教や仏教の成立にさいして、決定的に重要な役割を演じた。道教の成立についていえば、これは本来民衆を中心とした民族信仰であり、老荘思想とは異質のものであったが、老子を教祖に担ぎあげた結果として、両者の結びつきが成立した。老子にとっては迷惑この上もないことであったと思われるが、これによって道教のうちに老荘思想を注入する道が開かれることになった」。
「仏教が中国に定着するさいに、老荘思想の演じた役割は大きい。中国人は老荘思想を媒介とすることによって、はじめて仏教の教理を理解することができたのである。もっとも仏教の理解が本格化するにつれて、両者の間にある異質の部軍が意識されるようになり、つとめて老荘思想を排除しようとする傾向が生まれた。だが、これによって老荘思想の中国仏教にたいする働きかけが終わったわけでは決してない。やがて六朝末から隋唐にかけて、中国仏教のうちでも特に中国的な性格の強い禅宗と浄土教が生まれた」。
老荘思想と道教の関係、老荘思想と仏教の関係、とりわけ禅宗、浄土教への影響――の解説は、私にとって大変勉強になった。



