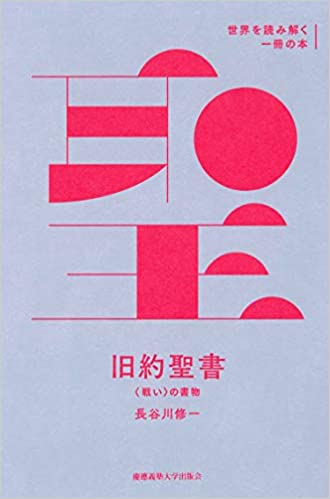
情熱的読書人間・榎戸 誠
ナチスによるホロコーストは、決して許されない犯罪であるが、一方、ユダヤ人(イスラエル人)が、自分たちの遠い祖先が治めていた土地だから、パレスチナは自分たちのものだという主張には、私はかねがね違和感を抱いてきた。
『旧約聖書――<戦い>の書物』(長谷川修一著、慶應義塾大学出版会)が、この違和感を解きほぐすヒントを与えてくれた。
イスラエルを、「歴史的イスラエル」、「原イスラエル」、「聖書的イスラエル」の3つに分ける著者の考え方には、目から鱗が落ちました。「『歴史的イスラエル』とは、史実として実在が確認できるイスラエルのことで、紀元前9世紀以降の『イスラエル』がこれに当たる。これとは別に、『原イスラエル』という概念がある。それは、王国時代に『イスラエル』と自称し、また他称され、旧約聖書が『イスラエル(の子ら)』と呼ぶ人々の先駆者と想定される集団を指す。文献史料で言えばメルネプタハ碑文に言及される『イスラエル』がこれに相当し、考古学的には紀元前12世紀以降、パレスチナ中央丘陵地域に住み始めた人々がこれに当たる。彼らは旧約聖書が言及する『イスラエル』とは同一視できないものの、その源流に当たるだろうという考え方によって生み出された概念である。これに対し、旧約聖書の出エジプト記、ヨシュア記や士師記が語る『イスラエル』は『聖書的イスラエル』とでも呼べるだろう。『聖書的イスラエル』と呼ばれる集団は、出エジプトの物語やパレスチナ先住民を征服した物語の主人公たちである。出エジプトやパレスチナ征服については、それらを裏付ける証拠が不十分であるため、この人々をもって『歴史駅イスラエル』とは言いがたい。ただし、同じ旧約聖書であっても、列王記に記述されている『聖書的イスラエル』は、同時代碑文史料等の裏付けから、『歴史的イスラエル』と重なり合う部分が大きいと言える」。
「一度概念を整理しておこう。『原イスラエル』は考古学的にパレスチナ中央丘陵地域にいた人々を指すという意味では『歴史的イスラエル』であるが、彼らが『イスラエル』と自称する、あるいは他称される集団であったのかどうかについては確証がない。依拠できるのはメルネプタハ碑文のみであり、それも作成年代が紀元前13世紀末と、若干だがこれらの集団の出現年代よりも早い。また、この集団が紀元前9世紀以降にパレスチナに実在が認められる『歴史的イスラエル』に連なるというのも仮説に過ぎない。・・・パレスチナは古来様々な人々が行き交う地域であったから、他地域からの人々の流入もまた頻繁であった。そうであれば、紀元前13世紀末に『イスラエル』と呼ばれた人々と、紀元前9世紀以降の『歴史的イスラエル』を構成する人々との間に、血縁関係を含めどの程度のつながりがあるのかは不明と言わざるを得ない。要するに『原イスラエル』は、後世の歴史上の『イスラエル』と、紀元前12世紀以降にパレスチナ中央丘陵地域に出現した集団との間を橋渡しするためにつくられた概念なのである」。
なぜそのような架橋が必要なのだろうか。「その理由は、旧約聖書内では、『イスラエル』という呼称が、『歴史的イスラエル』が登場する紀元前9世紀をはるかに遡って用いられることにある。しかし、果たしてどこまでが実際に『歴史的イスラエル』なのか、現存する史料では決定できない。そこで、『歴史的イスラエル』とは言えないが、『聖書的イスラエル』と重なる可能性のある、より古い集団を『歴史的イスラエル』とは区別して『原イスラエル』と呼ぶことにしたのである。出エジプト記、ヨショア記、そして士師記の筆者たちが、自らの先祖に関する何らかの伝承の核を膨らませて物語を記した可能性は決して低くない。そのような伝承が伝えられていたことは当然とも言えよう。その伝承の核には紀元前9世紀よりも古い『歴史的イスラエル』の記憶があった可能性はあるものの、その核がどこまで大きいかは不明である。むしろ物語の筆者たちは、伝承を核にしつつも現に存在している『自分たち』=『イスラエル』の『過去』に執筆当時の、つまり『現在』の理想を投影して物語を編んだのだと考えられる。そのために彼らは、『過去』を語る物語の中に、例えば『前の預言者』に特徴的な、『律法』への不従順は破滅をもたらすなどといった、「こうしてはいけない」という、自らが学ぶべき教訓をも織り込んでいる。彼らは自分たちの現在のために、そして未来のために、『過去』をつくったということもできるだろう。そのような仕方で彼らは、自らの起源を神との関係の歴史の中に位置づけようとしたのである」。
では、「歴史的イスラエル」は一体いつ誕生したのだろうか。「紀元前13世紀に始まった『動乱の時代』に、パレスチナに古くから住んでいた人々は自らとは異なる集団と遭遇した。エーゲ海地域を起源とする『海の民』の一部が、パレスチナ沿岸部に移住してきたのである。彼らは自分たちとは異なる言葉を話し、異なる出で立ちをし、凝った装飾の土器を用い、割礼を施さず、そして豚を食事に供した。このような『異質』な集団と遭遇し、交流した結果、当時のパレスチナ住民の間で『自分たち』のアイデンティティが先鋭化したのではないだろうか。この時代以降に見られる、それまでは多少なりとも装飾を施していた土器から装飾がほとんどなくなる、豚を食べていた地域の人々が豚食を忌避するようになる、割礼が徹底される、などといった現象がこうした先鋭化の結果だったのかもしれない。さらに共属意識を強めるためには、このように目に見える形での新たなアイデンティティ形成の他に、古代ギリシアでもそうであったように、共通の『神話』を持つことが有効である。それも自分たちがどういう人々であるのかを説明するような『過去の物語』、すなわち『民族創世神話』が必要とされる。こうした物語は、無からつくられるのではない」。
「古代のパレスチナの人々にとって、彼らを結びつけるような『共通の過去』とは、自分たちが同じ神によって救われたという一つの経験の記憶であった。それが『出エジプト』という出来事である。『出エジプト』という出来事が旧約聖書に記されているような仕方では生じていなかったであろう。おそらくそれは、後に『歴史的イスラエル』を構成した人々の祖先の一部が経験した奇跡的な出来事だったのだろう。出エジプト記をはじめ、旧約聖書のいたるところでこの出来事がヤハウェと強く結びつけられて伝えられていることから考えると、そうした経験をした人々はヤハウェの崇拝者だったのかもしれない。この奇跡的な経験はヤハウェへの感謝につながり、その感謝を表す儀礼が行われるようになったことだろう。こうした儀礼が、やがて今日に至るまで祝われている『過越祭』という祭りの原型になったものと思われる。彼らが『ヤハウェによる救い』と確信した出来事の強烈な記憶は、実際にその経験をしていない人々にも伝わり、さらに世代を重ねるうちに彼らの共通の『神話』となった。・・・こうした『共通の過去の物語』に、パレスチナ諸地域の人々がそれぞれ伝えていた伝承が結合していったのだと思われる。その中には共通の祖先である『イスラエル』という人物の伝承も含まれていたのだろう。こうして『歴史的イスラエル』は、紀元前13世紀末から紀元前9世紀までの間に徐々に形成され、またこうした『共通の過去の物語』の形成はその後も続いていったのである。テクストに反映されるこうした思想上・文学上の営みもまた、直面する現実に対応するために、旧約聖書の筆者らが自らの『共通の過去』を構築すべく奮闘した『戦い』と呼べるだろう」。
本書の著者の独創的な着眼点と説得力のある論理展開には、脱帽するのみ。



