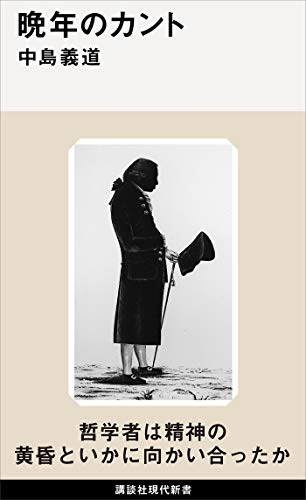
情熱的読書人間・榎戸 誠
『晩年のカント』(中島義道著、講談社現代新書)は、イマヌエル・カントの69歳から80歳までの晩年を、主にその著作に焦点を当てて辿っている。
カントほどの大哲学者は、老境に達したとき、どのように生きたのだろう、その晩年とはいかなるものだったのだろう、精神の荒廃が進む最晩年の数年間、何を考えていたのだろう――という著者の興味から、本書は書かれている。
「これまでわが国で伝えられてきた堅物の結晶のような哲人とはまるで違った血の通った、いや俗物の塊のような、ユーモアのセンス溢れる男に出会い、その難解きわまりない、しかもバカがつくほどの理想主義的な姿勢との乖離にひどく感動したのである。・・・老カントのうちには『老成』とは真逆の、どこまでも真理と格闘し、周囲の哲学者や官憲とさえ戦う血の気の多い姿勢が見られて、私は感動を新たにしたのである。そればかりではない。その老後には、悟りきった『賢人』とは真逆の、加速度的に濃度を増す懐疑論の淵にたたずむ姿勢が見られる。さらに、認知症によって完全に子どもに戻った哀れにも可愛らしい姿がある。私は『純粋理性批判』のあの超人的なほどの強靭な思索からこの無防備な子どもに戻った姿まで、すべてを含んで、あらためてカントを『尊敬している』と言えるようになった。あえて逆説的な言を発すれば、そのスケールの大きいぎこちない下手な生き方に共感するのである」。
私にとって、学問面で興味深いのは、カントがイエスに関して否定的な考えを持っていたことである。「<人類に革命を生じさせ、はかり知れないほど大きな道徳的善を世界にもたらしたとしても、われわれはやはり彼(イエス)が自然的に生み出された人間以外の者であると想定する原因をもたないであろう>。これは、キリスト教の基本教義に対する弁解の余地のない異論である。・・・カントの『聖書』およびキリスト教に対する姿勢は明らかであって、理性的ではない物語を真実とは認めないのだ」。
カントの女性論も、なかなか面白い。「カントは一度も結婚せず、独身の私講師のころからケーニヒスベルクの社交界に出入りしていたが、女性たちとの『恋愛沙汰』は考えられる限り希薄であった。そして、ケーニヒスベルクに住んでいた3人の妹たちともほぼ絶交していた。だが、不思議なことに、あたかも濃厚な体験に基づくかのように生き生きと女性を論ずるのである。<男性は心を探られ易いが女性はその秘密を洩らさない。もっとも女性の場合(彼女がおしゃべりであるために)他人の秘密は容易に守られないが>、<男性は恋しているとき嫉妬深い。婦人は恋していなくとも嫉妬ぶかい>」。
カントは、人生をもう一度繰り返したいと考えていたのだろうか。「<年からいっても円熟し、分別もついた、考えのある男ならば、たとえ、呼びもどされた年月と、現に今生きてもいる時とを、もっとよい条件の下に生きるとした場合でも、もう一度若くなることを選ぶことはまずあるまい、ということは、注目にあたいすることである>。『同じ人生』ではなく『もっとよい条件の下に生きるとした場合でも』、カントはそれを望まないのである。すばらしい人生を送ったと信じている人にとって死ぬことは辛いであろう。しかし、カントのように、人間が、そしてこの世が、根本悪に塗れていると信じている者にとって、そこからの離脱は、それほど辛くはないかもしれない。これは一種の救いであろう」。
読み終えて、カントの人間性に親しみを感じている私。



