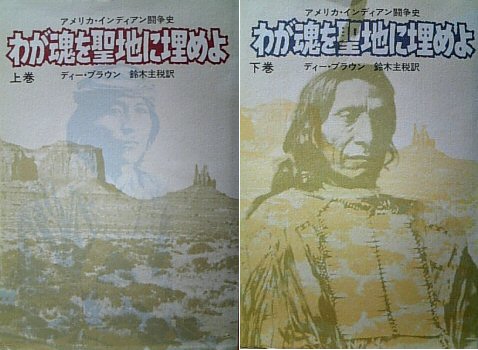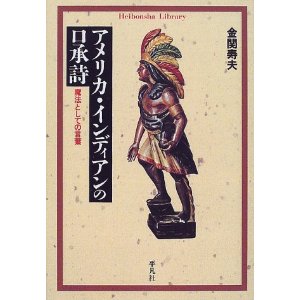日々楽ちんに生きている都会暮らしの人間なのに、何故か先住民族関係の本をよく読んでいた時があった。正確に言えばネイティブ・アメリカンについて。20歳のころの愛読書が、『わが魂を聖地に埋めよ―アメリカ・インディアン闘争史』。分厚い上下約五百頁の単行本だった。(※アメリカ・インディアンは当時の呼称)
フロンティア神話の陰に葬られたアメリカ・インディアンの痛哭の歴史を、彼ら自身の声を通して再現する。それまでの合衆国史に全面的な書き換えを迫った力作。(アマゾン紹介文より)
1972年出版のこの本、まだ絶版になっていない!さすがの草思社。記憶は薄れつつあるが、新大陸に白人たちが上陸してから彼らがいかに腹黒くネイティブたちを騙し、かれらとかれらの土地を侵略・収奪・制圧していったかを、抑圧される側から、淡々と克明に描いた内容だった。
長いノンフィクションは、抵抗の甲斐も無く最後のアパッチ族の酋長・ジェロニモが逮捕されたのちの、最終章≪ウンデット・ニーの虐殺≫で終わる。ウンデット・ニーの虐殺とは、サウスダコタ州ウンデット・ニーで野営していたミネコンジュー・スー族のゴースト・ダンスの集ま りを、1890年12月28日、武装した第7騎兵連隊が一方的に襲撃した 軍事行動。酋長をはじめとする二百数十人が無差別に虐殺された。この時を最後に、ネイティブたちの武力抵抗は終焉を迎えた。
原住民たちは白人によって生活環境を破壊され絶望のどん底に あったが、その中で、ゴースト・ダンスが爆発的に流行していた。 ゴースト・ダンス:「幽霊踊り」を踊ることで、再び原住民た ちの自由な世界とともにバッファローたちが草原に還ってきて、そしてこれを信じるものに与えられる“ゴースト・シャツ”を着れば、白人の銃弾を受けても弾が通らず死なない、というものだった。
ウンデット・ニーは、まさに彼らの聖地で、1970年代のパン・インディアン運動の中、ネイティブの運動団体がこの地を武装占拠し、連邦政府との間で戦闘となった場でもある。(本の原題は「Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West」)
読めば読むほどネイティブたちに感情移入してしまう、そして世の全ての侵略者たちに反発が起こる本だった。しかし私の火の元はここではなく、それ以前に新聞で、詩とともに紹介されていた本にあった。金関 寿夫著『アメリカ・インディアンの詩』(中公新書)。改めて調べると1977年発行。私が高校生の時に、その書評がもとで読んだことになる。すでに絶版だが、いくつか書き写した詩がまだ手元にある。
夜明けの歌
黒い七面鳥が東の方で尾を拡げる
すると その美しい突端が白い夜明けになる
夜明けが送ってよこした少年たちが
走りながらやってくる
かれらが穿いているのは
日光で織った黄色い靴
かれらは日光の流れの中で踊っている
虹が送ってよこした少女たちが
踊りながらやってくる
彼らが着ているのは
日光で織った黄色いシャツ
かれら夜明けの少女たちはおれたちの上で踊っている
山々の横っ腹がみどり色になる
山々のてっぺんが黄色になる
そして今おれたちの上に
美しい山々のうえに
夜明けがある
『アメリカ・インディアン口承詩 魔法としての言葉』金関寿夫 著 平凡社ライブラリー
今読むと結構あっさりした詩だが、色彩の時間経過表現といい、文体自体が踊っていることといい、私は素直に感動して、完全に刷り込まれてしまった。そしてその後しばらく、かれらについての本を読み漁っていくことになる。例えば西部開拓史を白人とインディアンの両方の視点で風刺した小説『小さな巨人』は、のちアーサー・ペン監督、ダスティン・ホフマン主演で“アメリカン・ニューシネマ”として映画化されて、観に行った。これも絶版のようだ。アメリカではしかし、このジャンルのエンターテインメントは、やっぱり白人が主人公なのだった(いろんな意味で)。『ダンス・ウイズ・ウルブス』しかり、『ラスト・オブ・モヒカン』しかり。
こんなことを思い出しているのは、当然ひとつ前の「かぶく本箱」で紹介した映画『セデック・バレ』の影響がある。『セデック・バレ』の主人公たちは正真正銘、リアルな原住民たちで(中国語では、先住民族というと滅んだ民族のことになるそうだ)、彼らは疾走しつつ実によく歌い踊る。あまりに鮮やかで、音楽がずっと脳内再生されているままだ。
私は彼らのような「うた」をうたえるのだろうか、彼らのように「生き様が顔に出る」ようになれるのだろうか。もちろん答えは「否」と言わざるを得ないし、「なれるのだろうか」などと、悠長なことを言っていられる歳ではないことも思い知らされている。だが70年代のノスタルジーに浸ってばかりもいられない。
原住民は実際に昔、意思疎通や感情を歌で示していたらしい。映画内では輪唱もあったが、実際に「相聞歌」方式で会話を行ったようで、旋律は固定的なものがあり、その上に自由に詩をつけていた。70年代に現地調査した音楽学者・小泉文夫氏は、彼らが完璧な純正律の音感を持っていたことを把握していた。純正律の合唱は、“首狩り”などの戦いに出る際に参加者の心を試す手立てでもあり、合唱が少しでも乱れると「これでは負ける」として、戦いを見合わせることになっていたようだ。
彼らは今でも高い身体能力をもち、歌や踊りや、狩りの中で生きている。きっと生まれながらの俳優(わざおぎ)なのだろう。
そして改めて考えると、アイヌ民族、台湾原住民、ハワイ原住民、ネイティブアメリカン、オーストラリアやニュージーランドのアボリジニなどの先住民・原住民の生み出した文化は、文字を持たない裏返しで生まれたのだとも思い到った。(そして同時に、例外なく彼らが、「後から来た」人間たちに侵略され、土地を奪われ、現在も貧困の中に暮らしていることも。)そこで金関 寿夫氏(1996年逝去とのこと。合掌)の述べた概念を、アメリカインディアンに固定せず、先住民・原住民にあてはめてみたが、決して強引ではなく、共通事項があると思う。
・・・・ いわゆる近代文明社会の文学(ぶんがく)が本質的には知的娯楽であるのに反して、先住民・原住民にとっては、文学はもっと生活に密着したもの、実用的、かつ機能的なものだった。 かれらの歌う歌は、しばしば病気を治癒するための呪いであった。戦いの前に歌う戦勝祈願の歌、豊作を祈る歌、雨乞いの歌、狩りの獲物を祈願する歌があり、また恋人を得るための歌、そしてイニシエーション、鎮魂の歌。それらは、すべて「実用」という目的を持っていたのである。
実用とは言っても、それには宗教、ないし神話の裏付けがあってのことである。すなわち、宇宙の目に見えない霊と交流したり対抗したりする、超自然の能力を獲得するための、いわば呪術的な媒介として、歌(時には物語)はあったのだ。そしてそれらは口承伝承で受け継がれていく。近代人のように、詩人の魂の個人的な叫びとか、言語美の表現だとかいう動機でもって、「詩作する」こととは、全く異質の行為、つまり「文学」以前の行為なのである ・・・・・
ネイティブアメリカン関係の本がすぐに「スピリチュアル」ジャンルに入れられてしまうのは、ここが理由なのか、と納得しつつ。私自身はもう少し個人的な 意味合いで、先住民・原住民の表現の「方法」を探っていきたいなあと思っている。それは、日本人の神話であるはずの『古事記』や、日本の芸能のおおもとについて述べた折口信夫の本、そして震災後に考えた森や山や海のことにリンクしていくのです。
by 牛丸