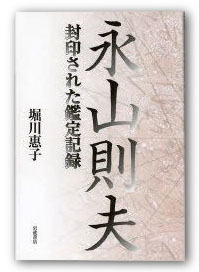19歳の永山則夫が4連続射殺事件を起こした驚くべき真の理由
『永山則夫――封印された鑑定記録』(堀川惠子著、岩波書店)を読み終わるまでの数日間は、重苦しく、やり切れない感情に襲われ、精神的に疲弊してしまった。
1968(昭和43)年10月11日、東京でホテルのカードマンを射殺、10月14日、京都で民間の警備員を射殺、10月26日、函館でタクシー運転手を射殺、11月5日、名古屋でタクシー運転手を射殺――という連続射殺事件を起こした永山則夫(当時19歳)と、その精神鑑定を行った精神科医・石川義博(当時38歳)との278日間に亘るやり取りの100時間を超える録音テープがこの本の骨格を成している。
本書は、私の胸に3つのことを刻み付けた。第1は、幼い子供が情操豊かに成長するためには、母親に代表される家族の愛情が欠かせないこと。第2は、獄中の永山に接する石川の姿勢を通じて、精神科医のあるべき姿が示されたこと。第3は、石川が心血を注ぎ込んで完成させた第二次精神鑑定書(いわゆる石川鑑定)を無視した日本の裁判制度の機能不全が暴かれたこと。
「マスコミの報道では、永山家は子ども8人の大所帯で、父は博打で放蕩して横死、母がリンゴの行商で得る僅かな金で生活するという極めて貧しい環境にあったことが大々的に取り上げられていた」。
永山の逮捕から5年後、弁護団から懇願された石川は精神鑑定を引き受ける。「『永山の逃避行動は、直接的には板柳(=父母の出身地)での母や次男(=永山の2番目の兄)から繰り返された暴力と関連があるように思えます。踏んだり蹴ったり殴ったりという圧倒的な暴力に晒され、抗弁も反抗もできない。物理的にも肉体的にも心理的にも、そこから逃げて離れるということしか彼がとれる手段はなかった。何度も<殴られては逃げる>をやっているうち、<何かあったら逃げる>という、いわば生物の環境への働きかけの中で、永山にとっては逃げること、苦難や危険を避けることが自分の生き方になってしまっています。悪い意味での学習です』」。幼い時期に家族から受けた虐待ともいうべき仕打ちが、その後の永山の行動の原因にあるのではないかというこの石川の見立ては、PTSD(心的外傷後ストレス障害)理論に立脚している。
「永山は、最初は必死に働く。それは不安をかき消すためであり、劣等感の裏返しの行動だ。そして心身ともに疲れ果て、それ以上そこにはいられないという切羽詰まった極限状態に自分が置かれているかのように思い込み、ついには他人から見ればささいなことをきっかけに、すべて放棄して逃げ出す。逃げて、もっと条件の悪い所に行き、そこでまた頑張って、さらに極限状況に陥ってどうにもならなくなって逃げるという悪循環を繰り返していた。石川医師は言う。『人間不信、そして不安、それが異常なレベルで強いと感じました。恐らくその原点は、(故郷の)網走での出来事から始まっています。姉からも母からも捨てられ、後に父もあんな悲惨な死に方をした。これだけ揃えば人間不信になるには十分すぎるほどですが、彼の場合、その後も傷を恢復させるような扱いは受けていない。それどころか、母親からはさらに精神的にも見捨てられている。家族も誰も信じられないし、誰からも誉められず、不安だけが強くなる。全部、人間不信感に繋がっていっているように思われます』」。
全ての聞き取りを終えた石川は、以下の診断を下した。「被告人は犯行前すでに出生以来の劣悪な環境や外傷的情動体験等によって、人格の全体的発達や性格形成を歪められ偏らされていた。中学2年まで続いた夜尿症、小学5年以来顕在化した抑うつ反応や自殺念慮に代表されるように神経症状態も発現していた。また小学2年以来の頻回の家出、長期欠席、頻回転職や非行にみられるような問題が、病的に強いあてつけ真理によって行動化されていた。これらすべては、その後も絶間のないストレスに基いて悪循環を形成しながら慢性化し持続した。犯行直前、被告人は肉親や社会のすべてから見捨てられ、絶望的で進退きわまった窮地に追い込まれ、『糸の切れた凧』のように感じ『自分がこの世で一番不幸な人間』と思っていた。同時に長い間、正常なはけ口を見いだせなかった攻撃衝動は、恨みとしてうっ積にうっ積を重ね、被告人に自分以外のすべてを敵視させ、被告人が統御できなくなるほど原始的で粗野で強烈な怒りを招来し、被告人を根底から激しく衝き動かしていた。・・・犯行時被告人の自我境界は不鮮明となり、自我の統合は殆んど解体に瀕しており、精神病に近い精神状態にあったと診断される。・・・極限状態にあった被告人の絶望感と攻撃衝動を、肉親や社会に対する仕返しの側へ転化させる引き金となった」。永山の連続殺人事件は、当時の報道が一斉に言い立てた「貧困・無知が引き起こした犯罪」ではなく、「肉親への仕返し(永山の言葉に置き換えると<当てつけ>)」が真の理由と判断したのである。
事件前も事件後も、誰に対しても心を閉ざしていた永山が生涯で初めて心を開いたのは、鑑定に当たり、問い詰めるのではなく、永山のこれまでの生活史と精神状態を理解しようと、ひたすら聞くことに徹した石川に対してであった。
「永山は、獄中に入ってから必死に勉強した。あらゆる書物を読破し、マルクス主義を学び、本を出版するまでになった。無知だったかつての自分を否定し、学問を知るひとりの人間として社会に発言することに生き甲斐を見出すようになっていた。その猛勉強ぶりも、石川医師が鑑定書で指摘したような劣等感の裏返しだったのかもしれないが、『精神病に近い精神状態』という、石川医師がぎりぎりまで配慮して表現した診断結果は、彼がようやく手に入れた自尊心をも酷く傷つけることになった」。
一度は石川鑑定に不満を漏らした永山であるが、著者は、死刑執行後の永山の数少ない遺品の中に、永山が何度も何度も読み返したと思われる石川鑑定を見出す。死刑が執行されるその日まで、永山は石川鑑定だけは手放さなかったのである。
「あとがき」に記された著者の言葉が心に残る。「家族との関係をうまく結べない時、第三者の存在によって救われることもあります。『この時、この出逢いがあったから』という宝物を得た人は、たとえそれが家族でなくても道を切り拓いてゆけるはずです。周りの人の心に無関心でいなければ、自分がその第三者となることもあるでしょう」。