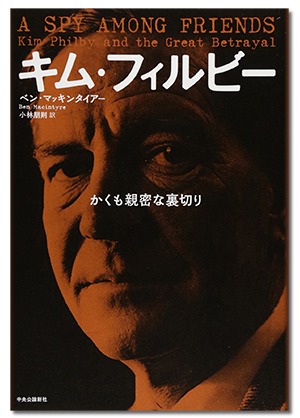人を信じることは生きる上での最上級の御馳走だが、そいつが腐っていた時、どうするんだ。
めちゃくちゃ忙しくて本読む暇がなくて、なんか頭が空白になっている。そして自分の身に起きたある事件での実感を込めて感じたのである。他人を信じることの甘さと苦さ。
『キム・フィルビー かくも親密な裏切り』ベン・マッキンタイアー著 小林朋則訳 を読む。
なぜかこの人物を知っていたのであるが、イギリスMI6、そうですスパイ組織でジェームス・ボンドが所属した(作者イアン・フレミングが所属した)の上級スパイがソ連へ亡命して、世界中が大騒ぎしたことがあった。その人物が主人公のキム・フィルビーである。この本はフィクションではなく、キムと最も信頼関係の厚く、そして見事に裏切られたエリオットの聞き書きを元にして書かれたノンフィクションである。注目すべきはその情報元のエリオットもM16のスパイであったがために、退職後、裏切られたキム・フィルビーについて誰かに言いたくてたまらないのだが、すべてを話すとイギリスの機密に触れるためや自己弁護のためにかなり歪曲した情報を提供しているらしい。その迷路をたどってなかなか意味深長な二重スパイの実態とそれを許して来たイギリスの階級社会の問題性を描いていて、なかなか興味があった。
筆者はイギリスの新聞タイムズのコラムニストで副主筆。どうもスパイに興味があるらしく、『ナチが愛した二重スパイ』、『ナチスを欺いた死体 英国の奇策・ミンスミート作戦の真実』、『英国二重スパイ・システム ノルマンディー上陸作戦を支えた欺瞞作戦』など全てがベストセラーとなっている売れっ子のようだ。
何が興味深いかと言えばこのスパイ、キム・フィルビーはソ連に亡命するまで、2度ほどソ連のスパイの嫌疑がかけられたが、全く尻尾を掴ませなかった。そして30年にもわたって冷戦下のイギリスとアメリカのFBIを出しぬいて多くの情報をソ連に送っていたと言う事なのであるが、そこには、イギリス社会の階級性が厳然と存在していたこと。その基盤は所謂男社会の友情がすべてであるおかしな風習。つまりクラブの存在がある。
そもそもクラブというのは戦後に始まったことではなくて、長い長いイギリスの伝統であり、政治を論じる場であり、そこでは酒を飲み、内輪の馬鹿げた話から高度な政治的な陰謀までが交換されるし、ホモセクシュアルの場でもある。それに加えて、イギリス特有の有名校の男子だけの寮生活、たとえばイートン校、その上のケンブリッジ大学で育まれた友人関係はすべてに優先されて認められると言う、すさまじいエリート主義、男社会優先主義が、このキム・フィルビーがスパイ人生を難なく過ごせた基本であるようだ。
キムの父親は著名なアラブ学者・探検家・作家であったが、社会的にはトラブルメーカーで、父親としては余りに厳しすぎて、馴染めないというキムには初歩的な躓きの石であったようだ。対する裏切られた方のエリオットも父親は著名な登山家で、イートン校の校長で、めちゃくちゃな上流階級出身者といえる。彼ら二人がイギリスのスパイとなる経緯は勿論第二次世界大戦時にドイツの脅威に対して救国意識が働いたのではあるが、その二人がなぜ別の国家に忠誠を誓いながら平然と30年も友情をはぐくんだのか確かに訳が分からない。
キムはケンブリッジ大学時、密かに共産主義を信奉していたようだ。当時ケンブリッジは信じられないが共産主義の「るつぼ」であったらしい。しかし、多くは卒業と共にイギリス上流社会へと帰って行ったのに対して、キムはソ連の二重スパイとして完璧に行動した。キムの最初の妻アリス・コールマンはウィーンの共産主義の地下活動家で、キムにかなりの影響を与えたようだが、後キムがMI6に入るにあたって、切り捨てて別の女性と結婚している。キムがこの国家にとって最重要な部署への就職も、イートン校仲間の推薦一つで入り込んでいるという間抜けさで、キムの行動を早くに怪しんでいたイギリスのもう一つの諜報機関MI5との確執は見方によってはイギリス社会のMI6の貴族性対MI5の庶民感覚という感じが見て取れる。
ともかくもキムは一分の隙もない紳士で、ユーモアにあふれ、誰にでも愛される、心底信用されるという善人が、すべてを利用し、すべてを裏切り、国を売り、自分だけ亡命すると言う最低の人間であったと言うことが劇的である。キムを愛する上司たちに引き上げられ非常な機密に易々アクセスすることが可能になっただけではなく、自ら計画を仕掛け、多数の西側の反共活動家をソ連に売りわたし、殺害された者の数は数知れないのだとか。逆に言えば冷戦時両陣営ともにスパイを送り込み情報戦だけではなく、実際の人名がかかった戦いがなされていたと言う事であろう。今だって分かったものではない。
しかし、二重スパイということはよく聞くフィクションと思っていたが、実際の在り様はすさまじいもんだ。彼らの裏表は実はどっちが本物なんだという関心と共に、人間そんなに人をだましきれるもんなのだろうかと思ってしまう。キムの場合、ともかく周囲が何故か全力でキムの疑念を晴らすために働いてしまうと言うことが摩訶不思議である。キムも重圧に負けていて酒におぼれてしばしばパーティーで泥酔したりしているが、全く疑問を持たれるようなことを口にしなかった。疑問を感じていたのは二度目の妻で、気の毒な彼女は精神に異常をきたしたりしているが、亡命してもまだキムを捨てることはなく、裏切られたエリオットの反対を押してソ連にキムに逢いに行っているが、帰国後ほどなくして死亡している。
最もキムがソ連のスパイだとして追求すべきと主張していたのがアメリカのFBI長官のフーヴァーであったと言うことは、フーヴァーの冷徹ぶりと、誰も信じてはいなかったフーヴァー時代のアメリカのFBIの非人間性が良く現れている。
この本のフィルビー亡命がなぜ易々となされたのかと言う点の分析がこれまたユニークである。つまりこんなに重大な問題をみんなが責任をとりたくない。彼が国内で捕まり裁判になれば、人間関係からそれを許した組織の問題まであからさまになる。それは困るし、やってられないということで、いっそのことソ連に亡命させた方がいいんじゃないかという暗黙の意思が働いて、フィルビーを査問の為に召喚すると告げておきながら、全く監視もつけず、亡命を許したのではないかと言うのである。
事実そのようにことは進んだ。そして世界中が驚いたのであるが、キムもソ連で英雄になるのであるが、どうも自分は最も信頼していたエリオットにはめられたのではないかと思ったらしく、何度かソ連からエリオットおびき出しの秘密の手紙が来たのだという。どっちもどっちだが、フィルビーはソ連で3度目の結婚をして穏やかに生活したと思ったが、実はそうではなかったらしい。「自分は変えようもない完全なイギリス人だ」と述べていて、KGBに信頼されることはなかったらしい。一方彼に騙された多くの人は自己保存のために自分は早くからフィルビーを疑っていたと言いだしたりした。たぶんそれも嘘だろう。ただ誰もがなんで彼の嘘に気付けなかったのか自分を責めたことは想像がつく。
この本を読みながら実は身近に起こったある事件での人の行動について本当に訳が分からないのが人だと言う感慨を持ったのである。誰と誰とが繋がっていて、誰が実は某セクトの人間だとか、秘密裏に話した内容が次の日には外部に漏れている。名簿のリストが某政治団体に流されている。穏やかではない。あの野郎を許せないといった発言が、回って来た時は、渋谷の駅頭で口論していたという事実のごとく変わっている。笑えないが事実であった。隣の人をあなたはどこまで信じられますか?ミステリーはここからだ。
魔女:加藤恵子