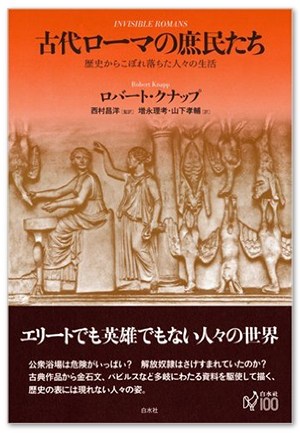古代ローマの庶民たちは、どう考え、どう行動していたのだろうか
古代ローマの皇帝や元老院議員たちが、どう考え、どう行動したかについては、かなりのことを私たちは知っている。しかし、こういうエリート階級に属していたのは、当時の全人口の約0.5%にも満たないごく僅かな人々に過ぎない。残りの99.5%を占める庶民の考え方や行動も知りたいと思っても、これまで私たちには適当な手段がなかったのである。
ところが何と、『古代ローマの庶民たち――歴史からこぼれ落ちた人々の生活』(ロバート・クナップ著、西村昌洋監訳、増永理考・山下孝輔訳、白水社)が、私のこの願いにしっかり応えてくれたのだ。私が漠然と抱いてきた古代ローマ人たちに対するイメージを覆す事実が次々に発掘され、記載されていたからである。
「(エリートたちの)偉業の背後には、そうした偉業を生み出した世界を下支えした幾百万もの人々が、庶民の男女、奴隷と解放奴隷、大金持ちと底なしの貧乏人、さらには一般兵士、娼婦、剣闘士、無法者までが、存在していたのである。彼らも、彼ら自身の目線に立ってその生き方を明らかにするに値する」と考えた著者は、碑文やパピルス、小説、寓話、キリスト教資料、占い書、魔術書など多岐に亘る資料を駆使して、このテーマに精力的に取り組んでいる。
私がイメージを改めざるを得なくなった事実の一つは、当時のローマの公共浴場が汚く、不衛生であったことだ。「庶民にとってもエリートにとっても、浴場は社会的な交流の場というだけでなく、考えるだけでもぞっとするような、衛生観念の欠如がもたらす危険にさらされる場でもあった点である。どれくらいの頻度で湯が交換されたかはわからないが、こまめに交換していたことをうかがわせるものはまったくない。湯につかる前に『先洗い』する習慣もなかった。湯につかる前に身体を洗う行為としては、オイルを体に塗ってからそれをこすり落としていたが、それはつまり、こすり落としたものは浴場の整備係によって湯船に掻き落とされていたということなのである。トイレが備え付けられていることもあったが、なかには湯船でそのまま用を足した者もいたことは明らかである。要は、どんな汚物、垢、体液、排泄物、そして細菌を人々が浴場に持ち込もうと、その浴場の湯はすぐに他の入浴客も一緒に使うことになったわけである。とりわけ、温浴室ではバクテリアの総数は天文学的な数字になったに違いない。このように何もかもが混ざった湯が接触感染病を蔓延させたのは確実だが、何らかの危険に少しでも気がついた者がいた節はまったくない。むしろ実際には、医者が決まって勧めるのは『風呂に入る』ことだったので、病気の人は(今となっては明らかなのだが)実質的に自分の病気を他人にうつすよう勧められていたことになる。しかもその間、病気を治すはずの湯から新しい病気をもらっていたのである」。
もう一つの事実は、奴隷が過酷な境遇に置かれていたこと。「人々が奴隷の身に落とされる理由はさまざまである。共和政時代のローマ支配拡大期には、戦争捕虜が途方もない、ひょっとすると最も多数の奴隷をもたらしたが、アウグストゥスの時代には、大量の捕虜を生み出すような大規模な戦争は比較的少なく間遠になった。もうひとつの供給源は、奴隷の産んだ子を大人にまで育てることである。奴隷から生まれた者は当然奴隷なので、奴隷に子供が生まれれば奴隷として育てられた。自由人の元に望まれない子供が生まれた場合は捨てることができ、実際にままあることで、そうした子供を拾った者は育ててかまわなかった。かくて拾い子は新しい奴隷の安定した供給源であった。第4の、重要度は低いが主要な供給源は、成人した男性・女性を奴隷にすることだった。戦争捕虜もまだときおりはいたが、この形で奴隷をもたらすのはおもに、旅人や町や農村地帯の無防備な人々をいつ誘拐するともしれない盗賊や海賊だった。彼らが孤立した地域や帝国の国境外で自由人を無差別に襲撃する恐怖を、アウグスティヌスが証言している」。「厳密には少なくともローマ市民は自分自身を奴隷として売ることはできなかったが、実際には、金と引きかえに自由人としての権利を放棄し、奴隷になる『契約をする』ことはできた。合法的か否かはともかく、ときどき自由人が自ら進んで奴隷になっていたのは明らかである。最後の可能性として、特に凶悪な犯罪で有罪判決を受けた一般人が、罰として奴隷にされる場合があった。これらの供給源がどれくらいの比率だったかはわからないが、それぞれが奴隷の心理状態に特有の影響をもたらしたであろう。奴隷として育てられた子供は、何年も自由人として過ごしたのち中年以降になってから捕まって奴隷にされた大人とは、物の見方が違ったことは想像に難くない。自ら奴隷になった人はおそらくその覚悟をしていた一方、誘拐された人はなおいっそうのこと、その不条理をかみしめたに違いない」。
「(奴隷の)虐待はいたるところに溢れかえっていた。身体的な虐待は人の体面を傷つけるのに最も頻繁で暴力的なものだった。・・・昔からよく用いられたのは鞭打ち(おそらく好まれた定番の処罰)と鎖につないだうえでの独房への監禁だった。しかし、場合に応じて虐待行為は数限りなく存在し、焼印を入れるといった長期にわたって体面を傷つける目印もしばしば伴った」。「身体的な虐待と同じくらいひどかったのが精神的な虐待だった。作家のアテナイオスは、奴隷が人としての尊厳を貶められていく様子を垣間見せている」。
「『女の奴隷はなんとも恥知らずな主人に奉仕するよう意に反して強いられている。主人は自らの肉欲を彼女たちで満たすが、奴隷の境遇に囚われているゆえに、女たちは抵抗することができない』。しかも被害に遭うのは女だけではなかった」。「奴隷はいつでもどこでも性的な目的で利用できるものとほとんど万人から思われていたので、奴隷たちはこの点を自らの人生に織り込んでおかなければならないのだった」。
著者は奴隷たちの心の中まで探っている。「奴隷として生きていく人生のただ中で、4つのトピックが常に奴隷の心中を占めていた。『私は主人とうまくやっていけるでしょうか』、『私は売られるでしょうか』、そして『私は自由の身になれるでしょうか』である。4番目の質問は奴隷ではなく主人によって問われたものだが、間接的に関係している。『私は逃亡(奴隷)を見つけ出せるでしょうか』。このように、奴隷が関心を持っているのは、主人との関係、売られること、自由の身になることについてであり、一方で主人が逃亡奴隷に焦点を合わせていることは、脱走するという考えを奴隷が頻繁に心に抱いたことを示唆している」。「逃亡を阻むために主人が時としてとったどちらかというとお粗末な方策について、碑文は手がかりを残している。奴隷用の首輪である。こういった首輪には次のような文言が刻まれていた。『私は逃亡しました。私を捕まえてください。我が主人のゾニヌスのもとへ連れ戻してくれたあかつきには、金貨1枚を差し上げます』」。
解放奴隷が、かつて奴隷だったことを隠すことなく、むしろ誇りにさえしていたという事実にも驚いた。「(奴隷の)解放は自由への道であったが、この手段はほぼ完全に主人の手に握られていた」。「確かにすべての奴隷が最終的に解放されたわけではない。多くは死ぬまで働き続けた。おそらく男は30歳を前に解放されることはまずなかったし、女の場合は出産適齢期を過ぎる(40代初め)まではほとんど解放されなかったであろう」。「解放奴隷はどうやら恥じることなく、しばしば明らかな誇りの念をもって、墓石上に自らが『元奴隷』であることを言明している。自身に自由の身をもたらした良き奴隷としての成功に誇りを見出すであろう。現に、ほとんどの場合、解放奴隷が昇格できた(つまり解放された)のは、その人物が主人の望む仕事をうまくこなせたからだった。その人がかつて奴隷の境遇だったのは本人の落ち度ではないし、そこから抜け出したことは人間として優れていることの確かな証であった」。
この他、娼婦や売春の実態、剣闘士の実態(女性剣闘士もいた!)についても、興味深い事実が明らかにされている。