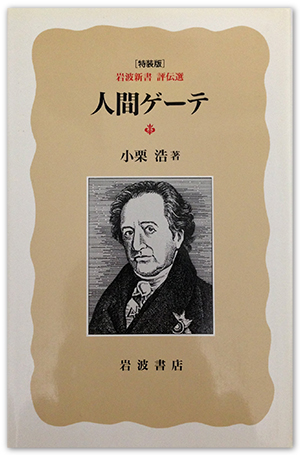
ゲーテは、恋愛は大好きだが、結婚は嫌だという自己中心主義者だった
文豪の評伝でありながら、これほど辛口で辛辣なものが存在していることに驚いた。しかも、その文豪がヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテだというのだから、驚きもひとかたではない。『人間ゲーテ(特装版)』(小栗浩著、岩波新書 評伝選)が、その本である。
辛辣な指摘の第1は、恋愛は望むところだが、結婚からは逃げ出すという、ゲーテの女性に対する姿勢である。
「『自分の明日を貪欲なまでに大切にする』とは、自分の未来の無限な可能性を信じ、それの実現に全力を注ぎ、そのために自分の自由を奪われまいとすることであろう。可能性の発見はゲーテの場合、とりわけ女性との愛の交渉によってなされる。女性こそは彼の心を高く引き上げ、現実の狭隘を打ち破って広大な世界へ連れ出してくれるものであった」。
「ゲーテにとって、恋愛は結婚を目的にはしない。およそ恋愛感情は、男女を肉体的に結びつけるために神が人間に与えたものであろう。恋愛における精神の高まりが彼らをおのずから結合にみちびく。恋する者たちは、愛の高揚において至福を感じながら、それが永延には続きえないという危機感にさらされ、それゆえに愛する今の瞬間がいよいよ尊く思われてくる。たいていの場合、彼らは結婚という形でこの瞬間を永遠化しようとする。しかしいったん結婚が成立すれば精神は平静に戻る。むろん、結婚においても精神は向上を続け、少なくとも変化はしているであろうが、最初の緊張した高まりをそのまま持続することはない。だから、恋愛感情の高まりにおいて精神がもっともよく活動するのを知った人は、いわば神の意志に逆らってでも、この高まりをくり返し経験したいと思う。そこで、結婚を予想しない、自己目的としての恋愛というものが考えられることになる。日常性への頽落をいさぎよしとせず、たえず精神の高揚を求めるこの姿勢は、一種の理想主義といってさしつかえない」。
「けれども、恋愛が結婚を予想することを世間の常識とするならば、ある女性を愛した男は、しかるべき理由なしにはこの女性から去ることは許されない。もしそんなことをすれば背信の行為となる。理想主義が反道徳を避けえないという、恋愛に固有なジレンマがここに生じる。この窮地におちいるまいとすれば、人ははじめから恋愛を避けるか、あるいは結婚という形にしたがう他はない。それは大きな妥協であるにはちがいない。しかし妥協なしでは現実を生きてゆけぬこともまた自明なのである。だが一方では、こういう妥協を極力排して、反道徳の危険もかえりみず、高揚した瞬間を積み重ねてゆこうとするタイプの人もいる。この人々は、裏切りを避けえないゆえにその倫理性を非難されるにもかかわらず、精神の高揚を求める理想主義のために、男性の生き方の一つの理想とされているといってもよい。ゲーテがその代表的な人間の一人であろう」。
このゲーテの姿勢に対して、私は著者・小栗浩とはいささか意見を異にする。相手の女性に対する最終的な裏切り行為は、反道徳とか倫理性の欠如というレヴェルの問題ではなく、単なる利己主義、自己中心主義に他ならない。その恋愛経験が優れた作品を生み出したのだから免罪されるだろうとゲーテが考えたとしたら、それは驕りに過ぎない。
「(小説『若いヴェルテルの悩み』の)ヴェルテルがゲーテの分身であることは確かだとしても、彼がけっしてヴェルテルでなかったばかりでなく、その純情繊細とはかなり裏腹な、友人の気持や立場を察するゆとりもない、わがまま無礼な振舞にも及ぶことのある人間だったことを私たちは知っておく必要がある」。ある意味、ゲーテは手前勝手な、始末におえぬ男だったのである。
辛辣な指摘の第2は、長年、ゲーテのために尽くした16歳年下の内縁の妻に対する煮え切らない態度である。相手のクリスティアーネ・ヴルピウスが身分の低い、教養もない町の娘であったことが、ゲーテに正式な結婚を躊躇わせたのである。
「ゲーテがクリスティアーネに何より感謝していたのは、彼女が気むずかしい存在ではなかったことである。クリスティアーネはいつも彼のためにあった。彼女の世界はゲーテだけだったといってもよい。彼女にとってヴァイマルの生活がどんなにつらかったか、それは私たちの想像をはるかにこえるものがある。人々の悪口が直接間接に耳に入るだけではない。たとえばゲーテに来客がある場合、正妻でない彼女はその場に姿を見せることができなかったのである」。
「クリスティアーネが酒ずきで野卑なところがあったのは確かであろう。しかし彼女が家事と育児のすべてをじつによく見て、ゲーテから一切の煩労を除いてやったのもまた疑いえない事実である。・・・彼が正式の結婚式をあげたのは1806年のことである。ゲーテは57歳、クリスティアーネは41歳になっていた。よく知られるように、ナポレオンの軍隊がヴァイマルに攻めこんで、彼の生命も危なかったとき、クリスティアーネはけなげに彼を守ってやった。彼女の献身的な振舞に、さすがにゲーテは感心させられずにはいなかった。久しい内縁関係を清算する気になったのには、たしかに彼女への感謝の気持が働いていたと思われる」。
真に愛している女性に長いこと辛い思いをさせて平気でいられるというゲーテの無神経ぶりが、私にはどうしても理解できない。
辛辣な指摘の第3は、私たちには意外なことだが、ゲーテの作品は売行きが芳しくなかったという事実である。
「『ヴェルテル』が大変な世評を呼んだのは確かであるが、それはゲーテの一生でただ一度の例外であって、それ以外では、彼の作品が(当時の)一般から拍手をもってむかえられたことは皆無だったといってよい」。
「ゲーテは生前何度も著作集を刊行しているが、その売行きはいずれもはなはだ思わしくなかった。彼は自分の作品に読者の反響を期待するのをやめるようになる。とくに『ファウスト』はただひとりで筆を進め、折にふれて少数の親しい人たちに原稿を送ることで満足していたのである。生前から文豪の名をほしいままにしたゲーテが、誰に読まれる当てもなしに、30年ものあいいだこつこつと原稿を書きすすめていったということは、あまり知られていないが、私たちが記憶していてよいことであろう」。
辛辣な指摘の一方で、『ゲーテとの対話』の著者、ヨハン・ペーター・エッカーマンに対する高い評価が目を惹く。「もしエッカーマンがゲーテとの対話を後世に伝えてくれなかったならば、ゲーテの晩年はもとより、私たちがゲーテについて知っていることの半ば近くは世に知られぬままに終わったのではあるまいか。・・・エッカーマンは、ゲーテとの日毎の対話を通じてゲーテを私たちに知らせてくれただけでなく、晩年のゲーテの仕事に対して他の何人も及ばない愛と尊敬と理解をよせ、それによってゲーテの創作活動(=『ファウスト』の完成)のかけがえのない支えともなった」。ゲーテの言葉をできるだけ正しく伝えようと、自分自身は努めて透明な媒体になることを願ったエッカーマンの文体を、フリードリヒ・ニーチェがドイツ散文の至宝と称えている。
著者が「結び」でこのように語っていることを付記しておく。「本文を書き終えてみてとくに感じるのは、私がゲーテをあまりに人間くさく、あるいは否定的に書きすぎはしなかったかということである。しかしこれは、私なりのゲーテへの感謝の書なのである。もしゲーテについて、迷信に近い偏見がこれほど世に行なわれていないならば、私はここまで書く必要がなかったにちがいない。盲目のゲーテ崇拝がゲーテに親しむ妨げになっている場合が少なくないのである」。私も、父親譲りのゲーテ大好き人間であることを、念のため申し添えておきたい。



