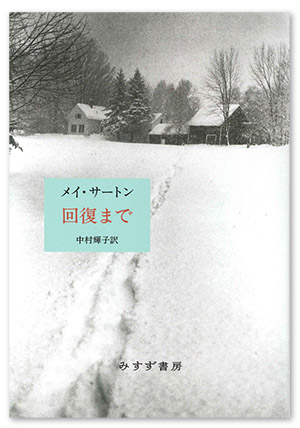
66〜67歳のメイ・サートンは、辛い1年間をどう乗り越えたのか
『夢見つつ深く植えよ』(メイ・サートン著、武田尚子訳、みすず書房)で、その魅力に取り憑かれて以来、著者58歳時の『独り居の日記』
(メイ・サートン著、武田尚子訳、みすず書房)、『70歳の日記』
(メイ・サートン著、幾島幸子訳、みすず書房)を読んできたが、今回、手にした66〜67歳時の日記『回復まで』
(メイ・サートン著、中村輝子訳、みすず書房)には、彼女にとって辛かった1年間の出来事が綴られている。
35年に亘り、心身共にパートナーであったジュデイ(ジュディス・マトラック)の耄碌進行による別居、自身の小説『総決算の時』に対する有力紙ニューヨーク・タイムズの酷評、乳がんの宣告と手術、しつこく付きまとう鬱気分が、サートンに降りかかってきたからだ。
しかし、サートンは不死鳥のように甦る。心許せる友人たち、周囲の静寂な自然、読書と執筆、愛読者たちの手紙に支えられ、癒やされて、彼女はゆっくりと回復していく。
「(80歳の)ジュディは(クリスマス・プレゼントの)包みをほどこうともせず、優雅なグレーのスラックスにもぜんぜん関心を示さない。『坂を転げるように衰えていく』様子に、どう対処したらいいのかわからなくなる。・・・まだ図書室をうろついていた彼女を見つけ、窓辺まで引っぱっていったときには、もう(ポーチの窓に近づいた)雉子は消えていた。そのとき、ジュディはこの家にわたしといっしょにいても、もうなんの意味もない遠くへ去ってしまったのだと悟った」。
「ジュディとわたしは30年以上も家族以上に、いちいち言葉にせずとも理解しあって安らぐことができていた。ジュディみたいに、くつろげる気持ちをともにできる人はいない。彼女はわたしの欠点もなにもかも理解し、昔からそのすべてを受け入れてくれた。それはこちらも同じ、それこそがほんとうの愛だったのだから」。
「ことし多すぎるほどに経験した精神的苦痛のことを考えても、苦痛から抜け出す唯一の道は、それをじっくり経験すること、つまりそれはなにか、どんな意味があるのか、よく考え、究め、理解することだと思う。苦痛にたいして扉を閉ざしてしまうと、ひとは成長する機会を逃すことになりはしないだろうか。身にふりかかることは最悪のショックでさえ、無駄であるものはなく、食べ物がからだを形づくるように、なにごとも人格を構築する骨組みに取り込まれるべきなのだ」。
「『ニューヨーク・タイムズ』の日曜版を急いで開き、『総決算のとき』の書評を読んだ。話では、やっと好意的な書評が載るだろうとのことだったので、『フリーランスのライター』を名乗る、ロア・ディクスタインが、ほとんど小説の内容を理解していず、わたし自身について、またわたしの作品についてアプリオリな思い込みから批評していることがあきらかな、卑劣な書評にひどいショックを受けた。・・・彼女はレズビアン小説という偽りの名をあたえて誤読している。・・・ふつう、人は攻撃されればそれに対応し、身を守ることができる。しかし、悪質な書評が残酷である理由のひとつは、作家は黙って座っているしかなく、なにひとつ対応できないことにある」。
乳がんの手術から1か月後。「あまりぐあいがよいとはいえなくても、うれしいことがたくさん・・・至高の1時間をうつらうつらと過ごした。朝のいろいろな音、海の波のかすかなつぶやき、飛び交う黄金ひわの楽の音のようなさえずり、もり鳩のクークー鳴く声、池に飛んでいく青鷺の低いひと声を耳にしながら。ここの静けさは、たくさんのいのちに満ちた静けさで、機械音などの聞こえない部屋での目覚めは信じがたい・・・とても静かなので、階段を歩く猫の足音も聞こえる。花壇には雑草がはびこっているけれど、うっとりするような歓びもくれるようになった・・・キンセンカが咲きはじめた。明るいオレンジ色と黄色の、鳥の羽のように柔らかく、みごとな配色のつやつやした花びらは、このごろの蒸し暑さにほかの色が褪せて見えるなか、新たないのちを家のなかにもたらしてくれる。百合も開きはじめ、それに大きなサフラン色のワスレグサも。薔薇の小さな束を毎日デッキチェアのかたわらの水鉢に入れている。・・・もうひとつ、最近でうれしかったのは、『海辺の家』を読んでくれた92歳の女性からの手紙で、60年間にわたる親友を失った難局も乗り越えて、生命力に溢れている。相当な高齢者からと、かなり若い人からの手紙が、なぜいちばんわたしを喜ばせるのだろう。おそらく、本を読んでくれる人より自分が若いというのはいいことだし、第二にわたしがずっと年上であっても、まだ若い人とつながりをもてるというのがうれしいからだろう。・・・炎からふたたび立ち上がる不死鳥は、別のことをわたしに告げる。わたしたちの肉体が弱れば弱るほど、心は虚飾を捨て、もっとも必要なものへの要求が強まり、ありのままの自分であることや感じるままの自分であることを恐れなければ、もっと自然で、愛情豊かになれる、と。まだわたしは不死鳥ではなく、灰のなかにいて、苦痛はそこから抜け出すために新しい羽を広げようとする痛みなのかもしれない」。
「この日記は10か月前に、自分自身を取り戻すため、昨年の鬱状態から身を引き離すために書きはじめたのだったが、いまは、たしかに上昇カーブに入ったと言えそう。奇跡的な変化をみせたのは心の風景で、それまでは、自分が自分でないような、暗澹たる苦しさが1年以上もつづいたのだ。・・・なにが起きたのだろう。数週間前に、風景が突然光に満ちて穏やかになり、怒りも苛立ちも消え、まるでこの地域で時折霧がさっと晴れあがるのを見かけるように、わたしたちを長いこと隔てていた幕が上がったかのようだった。・・・そろそろ、こんな内省をしばし休んで、かくも長く不在だった愉悦と賛美を迎え入れよう」。
やはり、メイ・サートンの世界は格別だなあ。



