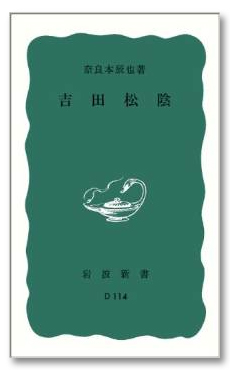吉田松陰は、なぜ、あれほど過激だったのか
私の吉田松陰好きは、父譲りである。それは私が学生の時だったが、話題が松陰に及ぶや、読書が唯一の趣味の父が、本箱に入り切らず書斎の床に雨後の筍のように積み重なっている書物の中から取り出してきたのが、玖村敏雄の『吉田松陰』であった。「これは少し難しいかもしれないが、面白いぞ」と渡されたのは、戦前に岩波書店から出版された箱入りのいかめしい感じの本であった。
玖村は、『吉田松陰』(玖村敏雄著、文春学藝ライブラリー)の中で、教育者・松陰の姿を生き生きと描き出している。年齢的に、人間として教育者として未完成ではあるが、このままでは日本は海外列強に後れを取ってしまうという危機感のもと、牢獄の中で、小さな私塾の中で、弟子たちに熱心に教えを説く松陰の姿勢から、迸るような熱い思いが伝わってくる。「塾はその外面的形態に於ては一つの漢学塾に過ぎなかつたが、その内面的精神に於ては日本的自覚に立つて難局打開の力を陶冶する教育所であつた」。彼の教育の理想は「当時としては教育の根本的革新を要求する」もので、「松陰のこの考へ方は一種の危険思想であるとする者もあつたのである」。塾では「常に当時の世界の形勢我国の実情に通じ、塾生等が各自の個性と境遇とを顧みながらかかる時代に如何に作用(はたら)くべきかの方策を考究した」。「塾では厳正なる規則を立てて生徒を率ゐることはしないで、相互に親和扶助し尊敬信頼し互に魂の扉を開いて交るやうにした」。「(塾の増築が)塾生の自発的労作によつて成つたことは松陰の教育の成功した一証として尊い。塾生中には士分の者も足軽の子も平民の出もあつたが、皆一体となつてこの精神的道場の建設に協力し土木木工に従事したのである。この労作の成功は階級の親和と協同の見地からも特筆せらるべきことである。松陰はこの増築後幽室を出て塾に常居し、文字通り塾生と一切の生活を共にすることとなつたのである」。松下村塾から多くの幕末・維新期の逸材が輩出したことは、松陰にとっては目的というよりも、結果論に過ぎないであろう。
玖村の著書に接してから数年後に手にしたのが、奈良本辰也の『吉田松陰』(奈良本辰也著、岩波新書。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)であった。これは、革命家・松陰を前面に大胆に打ち出した画期的な書物であった。
「天皇至上主義と幕府の実力に対する現実的な評価の結びつき・・・狂信的な理想主義と全く冷静な現実主義の奇妙な取り引き、その結合、これが吉田松陰の火のような行動を規定している政治思想であったといえば、まことに滑稽なようでもある。しかし、松陰においては、それは決して滑稽どころではなかった。彼は、そのために生命さえも惜しいとは思わなかったからである。彼には、外国の圧迫によって生れた祖国愛があるのみであった。天皇に対する狂信的な崇拝は、祖国のために生命を投げ出そうとする、その行動のより所であり、生命の代償であった」。
「(松陰の態度は)師、佐久間象山や、彼より4歳も年の若い橋本左内の理性的な、そしてより政治家的な型の態度ではなかった。象山や左内は、松陰と違って藩政改革の実際に建策し、その政治の枢機にも参じていた。彼等の世界観と結びついた洋学は松陰よりも遥かに進んでいた。松陰が殆ど読書で知ったことを象山や左内は原書で読むことも出来たのである。象山や左内は何物をも頼らず、自分の力で運命を切り拓いて行く人物であった。彼等は自身で、双肩に国家を担っていると自負できる人間であった。彼等には自己の行動を酔わせるための宗教的な権威は必要ではなかったのだ。左内や象山に天皇に対する神秘的な熱情を探してみてもどこにもみつからない。象山や左内は、常に既存のものを足場にして一歩一歩前進して行こうとした。一挙に目的に近づくような行為はなさなかった。彼等は偉大な改革者の型であったのだ。しかし、熱狂的な松陰は、さきの二人と違って戦闘的な過渡期の革命家の型に属した。彼は自分で政治の実際に画策し、自分でそれを運営して行こうなどとは思ってはいなかった。彼は自分一個の力を信ずるよりも、同志の結束を信じ、また後に続くものの善意を信頼した。だから彼は、常に身を犠牲にして同志のために、また主義のために、前進の突破口をつくる役目を引き受けていた」。この奈良本の「象山、左内=改革者」対「松陰=革命家」という図式化によって、なぜ、松陰が死をも恐れず、あれほど急進的、狂信的な行動を取ったのか、そして、弟子たちに共に立ち上がることを迫ったのかが明らかにされたのである。
「江戸居の諸友久坂・中谷・高杉なども皆僕と所見違ふなり。其の分れる所は僕は忠義をする積り、諸友は功業をなす積り」という、弟子たちに送った松陰の怒りの書簡が遺されている。「長州藩に渦まいている焔のような尊攘の魂、これは誰が燃え立たせたのだ。自分だ。自分以外の何者でもない。生きている限りは、この焔の中で燃え続けようとする松陰のすさまじさは、遂に高杉も久坂も、人格の範疇を異にされてしまう。忠義――国家・社会に殉ずるということは、目の前の大敵が退いて、さてこれからゆっくりお茶でも飲もうかというような呑気な話ではない。君たちは、革命のあとでせいぜい立身出世をすることだ。だが、僕は、その革命にこそ全身全霊を打ち込もう」。
松陰という人物とその思想を深く知ろうとするとき、上記の玖村の『吉田松陰』と奈良本の『吉田松陰』は欠くことのできない書であるが、これらとは趣の異なる『吉田松陰の恋』(古川薫著、文春文庫。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)という興味深い短篇がある。女っ気の全く感じられない松陰だが、ほのかに心を通わせ合った女性がいたというのである。
24歳の松陰が野山獄に入れられた時、同じ獄に収監されていた年上の女囚・高須久子との物語である。
「(獄中で囚人たちに講義を行う松陰は)時には古いシナの故事などを引いて、随分むつかしい話を長々とされ、一同あっけにとられるということもありました。ひとり興奮なさって、目を剥き、唾をとばしながら、まるで譫言のように喋り散らされるので、剽軽な獄卒政右衛門などはゲラゲラ笑い出してしまうという失礼な場面もありました。・・・以前は三百石取りの武士の妻だったわたくしが、このような小者(わたくしが非礼をたしなめた政右衛門)に馬鹿にされる現在の境遇を悲しんでみたところで仕方のないことだと思いつつ黙って睨みつけてやりました」。
「政右衛門ごときがどういおうと、何か惹かれるものがあって、わたくしは毎日欠かさず講義を聴きに行きました」。
「世間では跳ねあがり者などといわれているらしい寅次郎(松陰)様が、わたくしには不思議な力をそなえた人にしか見えなくなりました」。
「わたくしは変りました。寅次郎様が入獄されたころ37歳だったのが、この安政5年で40になりました。40の声を聞いたとたん、(出獄した)寅次郎様とお別れしてたかだか3年しか経っていないというのに、それがずっと遠い昔のできごとのようにも思えてくるのでございます。部屋にくすぼっているせいか、自分でも厭になるほど、むっちり肉がつきはじめ、家から持ってきた着物の身幅が狭くなってしまいました」。
野山獄に再入獄させられた松陰が、江戸の獄に送られる日が近づいた、ある日の「午すぎ、房の前を通りかかったというふりをして、『高須さん、これを・・・』と、一枚の紙片を格子の間から、寅次郎様が差し出されました。『高須うしのせんべつとありて汗ふきをおくられければ』と前詞して、歌が書きとめてありました。箱根山越すとき汗の出でやせん君を思ひてふき清めてん 松陰」。
「皆の見守っている前で腰縄が打たれ、寅次郎様は、錠前付きの駕籠の中の人となられました。それに網をかぶせ、役人5人、中間15人にとりかこまれた駕籠は、降りしきる梅雨に濡れながら、静かに獄を出て行きました。それから部屋へ駆け戻るのももどかしく、寅次郎様からいただいた便箋を開封いたしますと、『高須うしに申上ぐるとて』とあり、一声をいかで忘れんほととぎす 松陰。雨で湿ったためなのか、涙を溜めたわたくしの目にそううつるのか、別れの句が、ぼんやりと紙の上に滲んでおりました」。
これは高須が語る形をとった小説であるが、作中の松陰の歌と句は著者の古川が資料の山の中から探し出したもので、小説家の創作ではない。
松陰の妹で、久坂玄瑞の妻となる文(ふみ)がNHK大河ドラマ『花燃ゆ』の主人公になっているが、『吉田松陰――久坂玄瑞が祭り上げた「英雄」』(一坂太郎著、朝日新書)に興味深い逸話が記されている。松陰から文との結婚を勧められた久坂が、「あれは不美人だから気が進まない」と友への手紙に書いているというのだ。
高杉晋作、久坂玄瑞、入江九一と並び松下村塾の四天王と謳われながら、書物で取り上げられることのほとんどない吉田稔麿(としまろ)については、『吉田稔麿――松陰の志を継いだ男』(一坂太郎著、角川選書)がある。